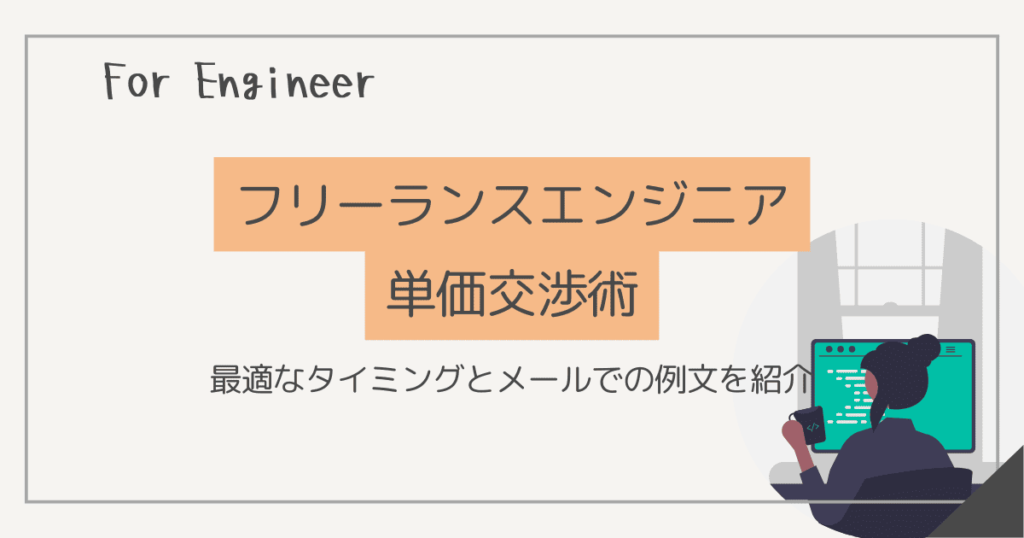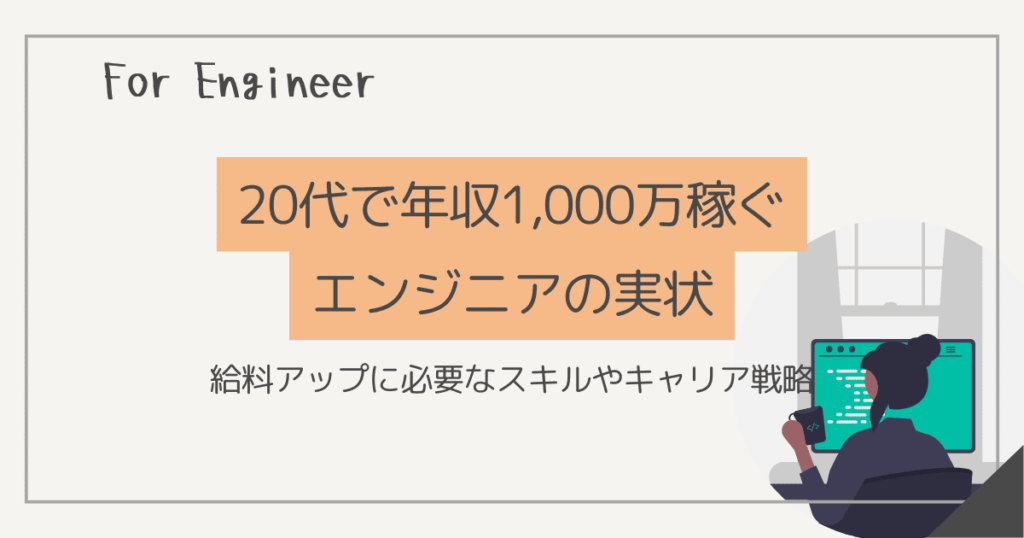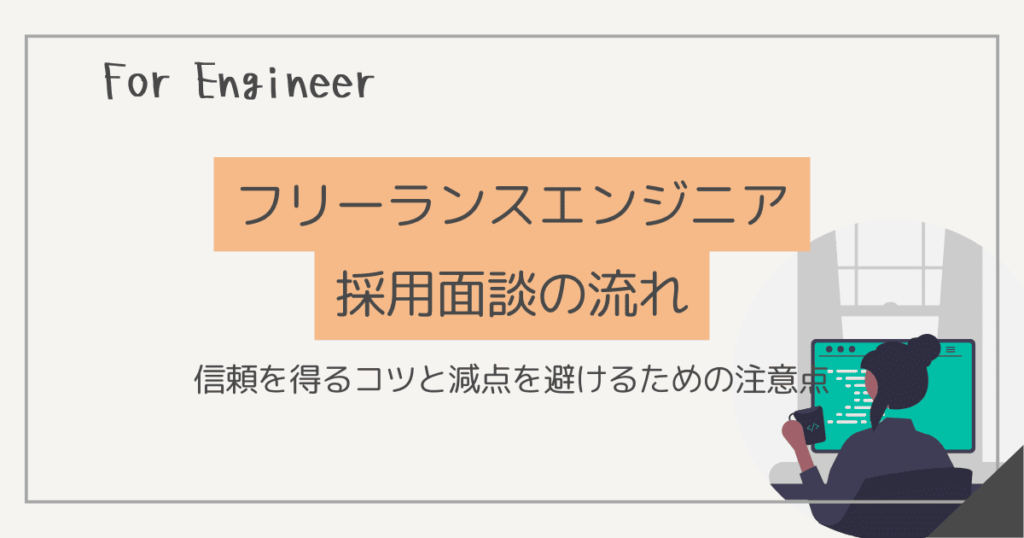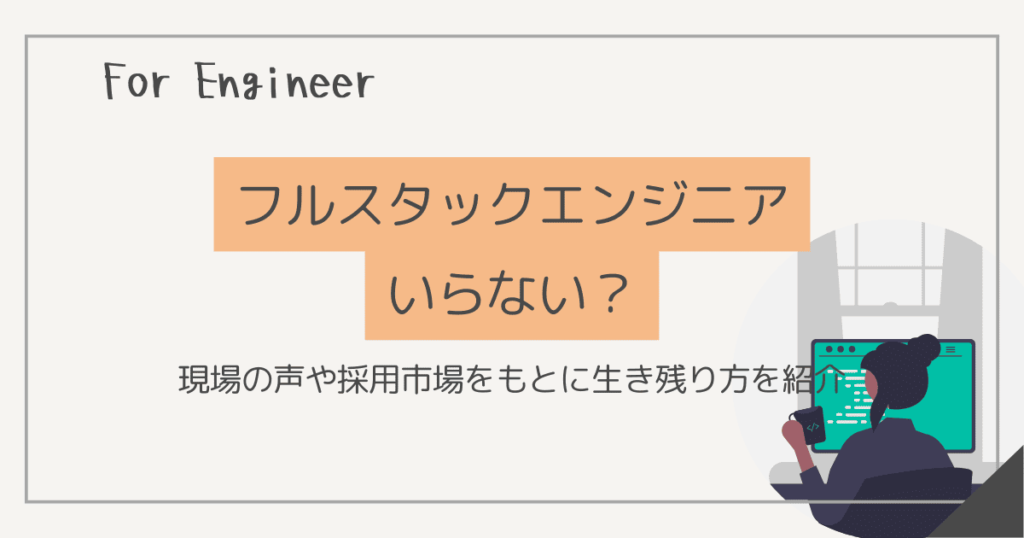個人事業主とは?フリーランスとの違いや毎月のやることも解説

フリーランスと個人事業主の違いを知っていますか?
2つを分けるポイントは開業届です。この記事では個人事業主となるために必要な手続きと、得られるメリットを解説します。フリーランスや個人事業主にとって重要な、税金や確定申告、節税、年金対策に有効な方法もお伝えするので参考にしてください。
FLEXYはフリーランスや副業の求人案件をお探しのエンジニア・CTO・技術顧問の方々にお仕事をご紹介するサービスです。
お仕事をお探しの方はお気軽にご連絡ください。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む目次
フリーランスと個人事業主
フリーランスと個人事業主は個人で仕事をしていることは同じですが、違う点があります。ここでは、フリーランスと個人事業主は何が違うのかや他に存在しているこの2つに似た働き方について紹介します。
フリーランスと個人事業主の違い
まずはフリーランスと個人事業主の違いについて解説します。
違いは「開業届」を出したかどうか
フリーランスと個人事業主は対等に比較できる言葉ではありません。結論から言ってしまうと、「フリーランス」というカテゴリの中に、一定数の「個人事業主」が含まれている構図と考えるのが適切でしょう。
あえて言うと、両者の違いは「税務署に開業届を出したか」という一点に絞られます。後述しますが、開業届の有無によって税務制度上の扱いに違いが出ます。
フリーランスはひとつの「働き方」
フリーランスとはさまざまある「個人の働き方」のひとつです。企業や団体に所属することなく自力で案件を獲得して、対価として報酬を得る仕事のスタンスをそのように呼びます。
仕事の内容や報酬額によって案件を受けるか決められるなど、企業と雇用関係を結んでいない分、自由に仕事をできる点が最大の魅力です。こうした活動自体は、税務署に開業届を提出しなくても行えます。
税務署に開業を申請したのが個人事業主
個人事業主とは「税務署に開業届を提出して何らかの事業を行っている人」を指します。ここで言う「事業」とは、内容に継続性と反復性が認められる仕事のことです。こうした要件を満たさない一部の仕事は開業が認められないことがありますが、エンジニアの場合は問題なく開業できます。
こちらの記事ではフリーランスのなりかたや、失敗しないためにするべきことを詳細にまとめていますので、是非合わせてご覧ください。
フリーランスや個人事業主の方が新しい仕事を探している場合、FLEXYへの登録がおすすめです。FLEXYでは、エンジニアやデザイナーなどIT人材が活躍できる案件を多数取り扱っています。登録を完了させ、FLEXY担当者と面談すると希望に沿った案件を紹介することが可能ですので、まずはFLEXYサービスの内容をご覧ください。
フリーランスや個人事業主に似た働き方
フリーランスや個人事業主に似た働き方はどのようなものがあるでしょうか。ここからは混同されがちな自営業、業務委託、ノマドワーカーという働き方との違いについて解説します。
自営業
自営業とは、シンプルに表すと自分自身で事業を営む人の総称です。個人事業主として事業経営を行うケースが多いですが、フリーランスも含まれます。自営業のなかで場所や時間にとらわれることなく働く場合をフリーランスと言います。ジャンルは飲食店からエンジニア、コンサルタントなど幅広く、職種は限定されていません。また法人を持ち従業員を雇用している場合も自営業に含まれますが、その場合は個人事業主ではありません。
業務委託
業務委託とは、雇用契約を結んでいない会社や個人に業務を委託する際に交わす契約方法のことです。よって個人事業主やフリーランスという働く方法とは違います。
業務委託契約には請負契約、委任契約、準委任契約があります。請負契約は成果物の納品に対して報酬が発生する契約です。委任契約は法律行為を伴う業務を行うことに対して報酬が発生し、準委任契約は法律行為を伴わない業務を行うことに対して報酬が発生する契約のことを言います。
こちらの記事では業務委託のエンジニアのニーズが高まっている理由などについて解説しています。是非合わせてご覧ください。
ノマドワーカー
ノマド(nomad)とは元々は英語で【食料などを求めて移動し定住地を持たない集団、遊牧民、放浪者】という意味ですが、現代での使い方は、自由に働く場所や時間を変えられる働き方を差すケースが多いです。またそういった場所や時間にとらわれない働き方をする人をノマドワーカーと言います。
ノマドワーカーは働く場所や時間を自由に選べることを差しているので、フリーランスや会社員であることとは関係がありません。会社に属さず自由に働く場合はもちろんのこと、会社員として働きながらも場所や時間が限定されていなければノマドワーカーと言えるでしょう。
個人事業主に必要な開業届
上記で紹介したように個人事業主になるには開業届を提出しなければいけません。この開業届の提出にはどのようなメリット・デメリットがあるのかや提出する場合どのような手続きが発生するのか紹介します。
開業届を出す3つのメリット
ここからは開業届を出すメリットを3つご紹介します。
社会的な信用を得やすくなる
個人で事業を始める場合は、原則として開業届を提出するべきとされています。ただし、独立時に開業届を提出しないことに対する罰則は特に設けられていません。基本的には適切に確定申告を行い、納税の義務を果たしさえすれば問題はありません。
一方で開業届を提出し、個人事業主として活動することでいくつかのメリットを受けられます。
1. 屋号付きの銀行口座が開設可能
開業届の提出時には、自身の商業上の名前である「屋号」を付けられます。特に駆け出しのフリーランスは組織に所属していない分、どうしても社会的信用が低くなりがちですが、屋号があれば個人事業主として実体のある事業を行っていることが一定程度保証されます。そのため、屋号がない状態に比べると社会的信用を得やすい可能性があります。
また、屋号付きの銀行口座の開設もできるようになります。プライベートの口座と区別して事業資金を管理しやすくなりますし、屋号のない口座に比べるとクライアントからの信頼度が高まりやすいという利点があります。
2. 家族の給与を経費計上可能
個人事業主であれば、配偶者や子どもなどの親族を「事業専従者」にして給与を支給し、経費として計上することが可能です。事業専従者とは「個人事業主と生計を一にして事業を行う」人物のことです。
税法上、家族への給与支払いは原則的に認められていませんが、事業専従者として申告すれば可能です。これによって一定程度の節税が図れるでしょう。ただし、扶養控除、配偶者控除などの所得控除が利用できなくなるので注意してください。
3. 青色申告が可能
確定申告の方法は「青色申告」と「白色申告」の2種類がありますが、個人事業主として開業し申請することで「青色申告」が行えるようになります。詳しくは後述しますが「青色申告」は「白色申告」よりも節税効果があるので、確定申告はぜひ「青色申告」にしたいところです。
4. 各種支援制度を受けやすくなる
個人事業主は国や地方自治体、商工会議所が実施するさまざまな支援制度を受けられます。応募期間が決まっているものや、支援条件が付いているものもあるので注意しましょう。
小規模事業者持続化補助金を受けられる
幅広い範囲のフリーランス、個人事業主を対象とした補助金制度です。商工会議所または商工会に経営計画を提出して、アドバイスを受けることを条件に、50万円を通常枠の上限としていくらかの補助を受けられます。小規模事業者とはこの場合、常時使用する従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、 それ以外の業種の場合20人以下である事業者 です。
小規模事業者の販路開拓等の取り組みに対する支援を充実させるため、2022年10月現在、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠といった特別枠が拡充されています。インボイス枠は上限が100万円、それ以外の枠は上限が200万円です。補助金活用例として以下のような事例があります。
- 古民家カフェに厨房を増設し地元商店街とのコラボメニュー開発や地域住民のためのイベントを開催することで売り上げが増えた
- 蕎麦屋が高性能フライヤーを導入し、新メニュー開発と地元メディアへの出稿で新規顧客獲得に成功した。
税務署に開業届を提出してあっても、開業届に記載された開業日が補助金の申請日より後であった場合や、申請時点ではまだ実際に事業を開始していなかった場合などは、補助金の対象外となるので注意が必要です。
出典:小規模事業者持続化補助金
ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進事業(ものづくり補助金)を利用できる
「ものづくり補助金」となっていますが、製造業だけでなく幅広い範囲の業種を支援する補助金制度です。クラウドサービス利用時の専用ソフトウェア購入費、その他の情報システムの購入経費などが補助対象となる可能性があります。補助金額の上限は1億円で、下限は100万円です。
元々は従業員の雇用改革のための制度として導入されているため、業務委託だけではなく自分でチームを作り開発していくような、スタートアップ志向のある方向けの補助金です。
出典:令和元年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領〔ビジネスモデル構築型〕(4次公募)
個人事業主やフリーランスを支援する助成金・給付金について内容をまとめた記事がありますので合わせてご覧ください。
開業届を出すデメリット
開業届を出すメリットについて解説したので、続いては開業届を出すことによるデメリットについて解説します。
扶養に入れない可能性がある
開業届を出す際に注意したいのは、不要に入っている場合、もしくは不要に入りたい場合です。 まず抑えておきたいのは、不要には【税法上の扶養】と【健康保険上の不要】の2種類あるということです。税法上の扶養に関しては、開業届提出の有無に関わらず、給与所得が103万円以下であれば扶養の対象となります。
しかし健康保険上の扶養に関しては開業届を出した場合だと扶養の対象から外れる可能性があります。扶養から外れると健康保険料が自己負担になるため、開業届を出す前に扶養に関してどうしたいか検討しましょう。
失業給付金を受け取れない可能性がある
失業給付金は、退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あり、再就職の意思があると認められる場合は受給できます。再就職をするための失業給付金であるため、開業届を提出して事業主になると再就職の意思がないとみなされ失業給付金の対象とならない可能性があります。
開業届を出しているにも関わらず失業給付金を受給していると不正受給になる恐れがあるため、詳しいことは必ずハローワークに相談しましょう。
開業のために必要な手続き
実際に個人事業主として開業するために必要な手続きの方法を紹介します。
1. 開業届を入手する
開業届は税務署を直接訪問するか、国税庁のWebサイトからPDFをダウンロードすることで入手できます。税務署に提出する分と自分の控え用として2部用意しましょう。なお、開業届の提出は事業開始後1ヶ月以内が期限とされています。
2. 必要事項の入力と書類の準備
住所や氏名、業種といった基本事項のほか、屋号なども記載する必要があります。この際に事前に従業員を雇うことが決まっている場合は、従業員の数や給与の支払状況などの情報も求められます。事業専従者給与に関する届け出や青色申告をする場合は、一緒に申請書を用意しておきましょう。
写真付きマイナンバーカードのコピーも提出が求められますので、事前に準備しておくとよいでしょう。
また、書類の準備を始める前には個人事業主の開業届の書き方を画像解説付きで紹介している記事を確認しておくことがおすすめです。
3. 提出
提出方法は税務署の窓口で直接渡す方法と郵便で送る方法の2通りがあります。窓口提出の場合は、提出用と控え用として、開業届を2部提出します。郵送では、提出用の開業届と控えのほか、マイナンバーカードの両面コピーと、切手を貼り付けた返信用封筒を、すべて封筒に入れて投函します。開業届が無事に受領されれば、返信用封筒に控えを入れて送付してくれます。
こちらの記事では、さらに詳しく個人事業主になるには何をやる必要があるのかを紹介していますので、個人事業主になることを考えている方はやるべきことを確認してみてください。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込むフリーランスと個人事業主のお金
フリーランスと個人事業主の税金や年金などのお金に関わる情報を紹介します。生活に役立つiDeCoや節税のことも紹介しますので、是非ご覧ください。
フリーランスや個人事業主になった場合の税金は?
フリーランスや個人事業主は会社員と違い、自分で税金を計算し支払わなければなりません。また、会社員には課されないけれど、個人事業主やフリーランスには課される税金もあります。
税金は大きく分けて5種類ある
フリーランスや個人事業主が支払う税金として知っておくべきものは、大きく5種類に分けられます。所得税、復興特別所得税、住民税、消費税、個人事業税の5つで、このうち最も重要なのが、事業により稼いだお金を元に課される所得税です。
所得税は、収入から必要経費と各種控除の額を引いた後の値が大きいほど高い税率が適用される、累進税率という仕組みの税金です。基本的には収入が多くなるほど税率が高くなり負担が重くなるという特徴があります。フリーランスや個人事業主の所得税で注意が必要なのは、報酬の種類によっては源泉徴収されていることがあるという点です。
すべての収入や必要経費などを合わせて算出した支払うべき所得税額よりも、源泉徴収されていた金額の方が大きかった場合は、納めすぎていた分が確定申告により還付され、少なかった場合は足りない分を納付します。自分の報酬からいくら源泉徴収されているのか、きちんと把握しておきましょう。
フリーランスの源泉徴収についてはこちらのフリーランスが源泉徴収で気を付けることの記事にまとめていますので、合わせてご覧ください。
また、個人事業主の収入から税金を差し引いた手取り額を知りたい場合には、こちらの記事をご確認ください。
確定申告はしなければいけない?
所得税については法律により、1月1日から12月31日までの1年間で得た所得について、次の年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をして納めるべき税額を算出し、納付することと定められています。
収入が必要経費よりも少ない場合など例外はありますが、基本的に確定申告は期限内に行わなければなりません。定められた期間より遅れて申告をしたり所得金額の決定を受けたりすると、本来納めるべき所得税だけでなく、無申告加算税も課されます。申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告すれば、場合によっては無申告加算税が課されないこともあります。
申告期限を過ぎてから納付する所得税には、利息にあたる延滞税が課されます。申告期限を過ぎてしまったら、1日でも早く申告することが重要です。
また、年末調整をしなければいけない場合もあります。個人事業主は、自身の事業以外で給与所得を得た場合や従業員を雇っている場合に年末調整を行う必要があります。年末調整が必要か分からない方やどのような手続きがあるか知りたい方は、個人事業主の年末調整について調べてみるとよいでしょう。
FLEXYでは、確定申告などの税金に関する記事やセミナーのコンテンツをご用意しています。ご登録いただくと税金に関する情報をキャッチアップしやすくなったり、高単価案件の紹介も受けやすくなりますので、ぜひFLEXYのサービス内容をご覧ください。
フリーランスや個人事業主になった場合の年金対策は?
国民年金は日本国内在住の20歳~60歳未満の全員が加入する公的年金です。また、会社員や公務員であれば厚生年金にも加入できます。フリーランスや個人事業主は厚生年金に加入できないため、会社員や公務員に比べて老後に受給できる年金額が少なくなります。
よって以下ではフリーランスや個人事業主ができる年金対策について解説します。
付加年金
自営業者などの第1号被保険者であれば、付加年金の対象者となります。月々の国民年金保険料に400円を追加することで「200円×付加保険料納付済期間の月数」の付加年金が受給できます。ただし後述する国民年金基金と併用できないため注意が必要です。
国民年金基金
国民年金基金とは、フリーランスや個人事業主でも、厚生年金のように国民年金に上乗せして年金を2階建てにできる公的制度です。65歳から亡くなるまで受給できる終身年金や、60歳から一定期間受給できる確定年金があり、細かく分けると7種類の型があります。
国民年金基金は加入後にプランを変更できる柔軟さがあり、また掛金の全額が所得控除の対象になり、確定申告をすることにより所得税と住民税を減額できるというメリットがあります。ただし一度加入すると基本的に自己都合ではやめられないため、加入前には慎重に検討しましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は65歳未満であればフリーランスや個人事業主の方でも加入できる年金制度です。投資信託・定期預金・保険商品から商品を選び自身で運用するタイプの年金であるため、運用成績によって年金額が変わるのが特徴です。月々5000円から6万8000円までの枠の中で、1000円単位で掛け金の調整が可能です。
またiDeCoも国民年金基金のように掛け金の全額が所得税控除の対象になるため、節税対策としても有効です。
年金制度については会社員など事業者に雇用されて働く場合、公的保険の一つである厚生年金制度にも加入して、より厚い年金対策が可能です。フリーランスが加入できる保険とその必要性について解説した記事では、このような会社員とフリーランスの加入できる保険の特徴や違いをわかりやすく紹介していますので、保険制度についても興味がある方はご覧ください。
確定申告は青色申告?それとも白色申告?
確定申告には2つの方法があります。「青色申告」と「白色申告」です。「青色申告」は「白色申告」に比べ、税金面で有利になる特長があります。個人事業主として開業し、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで「青色申告」が行えるようになります。
2つの違いは会計帳簿
「青色申告」とは、日々の事業活動を帳簿へ適切に記帳し、その記帳に基づいた正確な申告をすることにより、税金の取り扱い上いくつかの特典が得られるようになる制度です。「青色申告」と「白色申告」の大きな違いは、会計帳簿にあります。
「青色申告」をする人は、原則として正規の簿記の原則に基づき記帳することが求められます。正規の簿記とは、損益計算書と貸借対照表を導き出せる組織的な簿記の方式をいい、一般的には複式簿記による記帳が該当します。仕訳帳・総勘定元帳といった主要簿のほか、現金出納帳・売上帳・仕入帳・商品有高帳・売掛金元帳・買掛金元帳・固定資産台帳といった補助簿も記帳します。
そして年末に、商品や消耗品の棚卸しを行い棚卸表を作成したり、減価償却費の計算をしたりといった決算処理をして、損益計算書と貸借対照表を作成します。作成した帳簿や損益計算書・貸借対照表などは、7年間保存しなければなりません。
「白色申告」の人も、収入金額や必要経費に関する事項を記帳し、定められた期間保存する必要がありますが、形式の指定はありません。
白色申告にメリットはないって本当?
「白色申告」は、「青色申告」のように税金面で有利になる点がありません。「白色申告」が「青色申告」と異なるのは帳簿の形式に指定がない点で、簡易なものでも問題がありません。
しかし、原則として複式簿記のような正規の簿記の原則に基づく記帳が求められる「青色申告」でも、簡易な帳簿による記帳は認められており、額は少なくなりますが税金面で有利になる青色申告特別控除が受けられます。また、「白色申告」では経費とならないけれど、「青色申告」であれば経費に計上できるものがあります。家族へ支払った給与を経費にできる「青色事業専従者給与」の仕組みや、未回収の売掛金などを損失の見込み額として経費に計上できる「貸倒引当金」(一括評価によるもの)は、青色申告者のみが利用できるものです。
さらに、主に自宅で仕事をする人の場合は、家賃や電気代などを一部経費として計上でき、白色申告よりも経費として認められやすくなっています。「白色申告」でも「青色申告」でも、日々の取引について記帳し、帳簿を保存しなければいけないという点は同じです。税金面で何も優遇されない「白色申告」には、メリットがあまりありません。
青色申告は控除によって納付する税金を大幅に減らせる
正規の簿記の原則に基づく記帳をしている「青色申告」の人は、その記帳に基づいて作成した損益計算書及び貸借対照表と確定申告書を、申告期限内に提出すると、最高で55万円の青色申告特別控除を受けられます。
上記の人のうち、e-Taxによる電子申告を行うか、優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録により保存している人は、最高で65万円の青色申告特別控除を受けられます。
正規の簿記の原則による記帳が難しくてできないという場合でも、「青色申告」の人は簡易な帳簿を作成することで、一定の要件の下で最高10万円の青色申告特別控除を受けられます。「青色申告」をすると、青色申告特別控除の額だけ利益が少なく計算されるので、納付する税金を減らせるというメリットがあります。
確定申告について知りたい方向けに、フリーランスや副業初心者向けに確定申告の基本について解説していますので、合わせてご覧ください。
確定申告の対応には時間がかかります。個人事業主の方は確定申告の対応以外にも報酬を増やしたい、追加で案件を受けたいなどの理由によって案件探しをされると思います。FLEXYに登録していただくと、担当者が案件探しをサポートできますので時間を有効活用できます。ぜひFLEXYサービスの内容を確認し、登録をご検討ください。
節税対策に有効な方法も把握しておこう
「青色申告」以外にも、節税対策として有効な方法があります。使える制度を知らないと、過剰な税金を支払うことになってしまうので、しっかり把握しておきましょう。
経費や控除の見直しを行う
所得税は収入から必要経費や所得控除の額を引いた値に税率をかけ、そこからさらに税額控除額を引いて算出します。収入から引ける必要経費や控除の額が大きいほど、支払うべき税金は少なくなります。経費や控除を見直し計上漏れをなくすことは、すぐにできて有効な節税対策です。
経費とは、事業を行うためにかかった費用のことを指します。同じものに対する支出でも、その目的によって経費に該当するか否かという違いが生じます。例えば、自分の昼ご飯として支払ったレストランの飲食代は経費にできませんが、取引先とのランチミーティングとしての飲食代は経費にあたると考えられます。
その支払いが経費に含まれるか否かを決めるポイントは3つあります。
事業との関わりを客観的に証明できるか
ひとつめは、「事業との関わりを客観的に証明できること」です。税務署から指摘を受けたときに、売り上げとの関連性を証明して正当性を主張できるのであれば、経費として認められる可能性が高いです。
収入に対して釣り合いが取れているか
2つめは、「収入に対して釣り合いが取れているか」です。収入を大幅に超えるような接待交際費を計上したり、常識的に考えて不要と思われるほどの消耗品費を計上したりといった、不自然な経費については認められない可能性が高まります。
事業主自身のための支払いでないか
3つめは、「事業主自身のための支払いでないか」です。個人事業主に対しては福利厚生費という概念がなく、自分のためにした健康診断の代金や生命保険料などを経費に含めることはできません。従業員のための支払いであれば経費に含めることが可能です。事務所を他に借りず自宅と兼用している場合は、家賃や水道光熱費などの支払いについて、一部を事業のための支払いとして経費に計上できます。これを家事按分といい、費用によって按分の仕方が異なるので、計上漏れがないように確認することが大切です。
控除には、所得から引かれる所得控除と、算出された所得税額から引かれる税額控除があります。社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料・医療費・寄付金など、支払った金額に基づいて控除額が決まるものや、ひとり親控除・寡婦控除などの家族関係に基づくもの、配当控除のように収入に基づくものなどさまざまな制度があります。自分が該当する控除はないか、きちんと確認しましょう。
こちらの記事ではフリーランスが経費にできるものや必要経費について解説しています。是非合わせご覧ください。
減価償却の特例を上手く活用する
ひとつあたり10万円以上の資産は減価償却資産とされ、原則として費用に一括計上することはできません。税法上定められた耐用年数に渡り分割し、減価償却費として計上します。10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産の特例を使えば3年間で均等に償却できます。
「青色申告」をしている人は、さらに有利な少額減価償却資産の特例を使えます。これは、年間で300万円を上限として、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得したときに一括で経費に計上できる制度です。収入が多いときに資産を購入し、特例の適用を受ければ、節税効果が高まるので上手く活用しましょう。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む個人事業主のお役立ち情報
書類や法律など個人事業主が知っていると役に立つ情報を紹介します。また、FLEXYが公開しているフリーランスに関連する記事も紹介していますので、税金や節税などへの理解を深めるのにご活用ください。
個人事業主の取引に関連する書類
納品書や請求書など個人事業主の取引に関連する書類について紹介します。
納品書
納品書は商品やサービスの納品が行われたことを証明する重要な書類ですが、個人事業主に発行義務はありません。しかし、納品書を発行しておくことでクライアントに安心感を与えられるといったメリットもありますので、個人事業主の方は納品書の書き方を一度調べておくことをおすすめします。
請求書
請求書は個人事業主にとって、提供したサービスや販売した商品の代金を取引先に対して請求するための重要な書類です。請求書の発行は、ビジネスの信頼性や円滑な取引を確保する過程でとても重要なため、個人事業主の方はしっかりと請求書の書き方を理解しておきましょう。
マイナンバー
個人事業主は、確定申告や取引先企業との報酬・契約金のやりとりなどでマイナンバーが必要です。さまざまな場面でマイナンバーが求められるため、個人事業主の方はマイナンバーについて理解を深めておくとよいでしょう。どのような場面でマイナンバーが必要なのかやマイナンバーを扱う注意点が書かれたこちらの記事をご覧ください。
個人事業主の取引に関連する法律
個人事業主は電子帳簿保存法やすでに施行されているインボイス制度に対応する必要があります。ここでは個人事業主の取引に関連する法律の情報を紹介します。
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法では、2024年の1月からは電子取引情報のデータ保存が義務化されます。レシートや領収書などの処理が多い個人事業主は取引情報を電子保存をする機会が多くなるでしょう。そのため、義務化前に個人事業主の方は電子帳簿保存法の対応について理解を深めておくとよいでしょう。
また、今後電子帳簿保存法への対応を考えている方は、会計ソフトの導入も検討してみてください。個人事業主向けの電子帳簿保存法に対応しているソフトを導入することによって電子保存の作業を効率化できます。
インボイス制度
個人事業主はインボイス制度からも影響を受けます。インボイス制度に対応しない場合には、契約継続や新規契約に影響が出てくる場合もありますので、まだ対応していない方は、個人事業主にとってインボイス制度はどのような影響があるのか調べておき、今後対応するのかどうか考えてみてください。
個人事業主として会社に所属しながら活動できるか
会社に属して会社から給与をもらいながらでも、開業届を出して個人事業主として収入を得ることは可能です。その場合は副業として個人事業主になることになります。近年では副業を認める会社も増えてきていますが、そうでない会社もあるため、所属している会社の就業規則についてきちんと確認しておきましょう。また副業所得についての確定申告が必要になるため、確定申告の作業については自身で行う必要があります。
会社に所属しながら副業として起業を考えている方は、一度どのような方法があるのか、メリットなどを調べてみてください。
個人事業主が毎月やること
個人事業主として事業を継続させるのであれば、経営者としてやらなければならないことがたくさんあります。税理士などに依頼しないのであれば、会社に属していると経理や総務といった部門でやってくれる雑務を個人で行わなければなりません。
売上や収支の確認、請求書の発行や送付、支払いや振込確認、税金の計算や申告、顧客管理、営業などさまざまな雑務があります。またこういった雑務を行いながらも、業務を遂行するだけではなく、スキルアップのための学習も必要です。
よって毎月のルーティンとして行うなり、アウトソーシングやサポートしてくれるツールやサービスを利用してなるべく雑務を減らしていくことが大切です。
フリーランスエンジニア向けエージェントのFLEXY(フレキシー)では、面倒な事務処理のサポートや案件のご紹介を行っています。個人事業主様が毎月やるべき雑務を減らして業務に集中できるようサポートしていますので、FLEXYにご登録の上、お気軽にご相談ください。
フリーランス関連記事のご紹介
こちらの関連記事も合わせてご覧ください。
フリーランスになるために行うべきこと
フリーランスになりたい方向けに、フリーランスとして活動していくための注意点や準備すべきことを詳しくまとめています。
フリーランスの税金
フリーランスの税金について知りたい方向けに、フリーランスが支払うべき税金と、その計算方法などについて紹介しています。
フリーランスの節税ポイント
フリーランスの方向けに、フリーランスができる節税のポイントについて解説しています。
フリーランスを支援する助成金や給付金
フリーランスとして活動していくなら、フリーランスを支援する助成金や給付金はチェックしておかなければならないポイントです。こちらの記事で解説していますので是非ご覧ください。
フリーランスの必要経費
会社員ではほとんど気にかけることがなくても、フリーランスになれば気になってくるのは経費です。こちらではフリーランスの必要経費について解説しています。
フリーランスの確定申告
確定申告について知りたい方向けに、確定申告のメリットや手順について解説しています。フリーランスの確定申告が知りたい方は是非お読みください。
フリーランスの源泉徴収
こちらでは源泉徴収について網羅的に解説してます。フリーランスの源泉徴収で気を付けるべきことなど気になる方におすすめです。
まとめ
個人事業主として開業することのメリットを簡単にまとめると、「社会的信用力の向上」や「各種税金の控除や補助金などの恩恵を受けやすくなる」ことにあります。特に開業することで可能になる「青色申告」は、節税効果の高い制度です。副業としてフリーランス活動を行う場合でもこうしたメリットを踏まえて、個人事業主として開業することを一度検討してみてもよいのではないでしょうか。
FLEXYはフリーランスや副業の求人案件をお探しのエンジニア・CTO・技術顧問の方々にお仕事をご紹介するサービスです。
是非、FLEXYに登録し、専任のコンサルタントにお気軽にご連絡ください。
フリーランスと個人事業主の違いを知っていますか?2つを分けるポイントは開業届です。この記事では個人事業主となるために必要な手続きと、得られるメリットを解説します。フリーランスや個人事業主にとって重要な、税金や確定申告、節税対策に有効な方法もお伝えするので参考にしてください。
h2>フリーランスと個人事業主の違い
h3>違いは「開業届」を出したかどうか
フリーランスと個人事業主は対等に比較できる言葉ではありません。結論から言ってしまうと、「フリーランス」というカテゴリの中に、一定数の「個人事業主」が含まれている構図と考えるのが適切でしょう。
あえて言うと、両者の違いは「税務署に開業届を出したか」という一点に絞られます。後述しますが、開業届の有無によって税務制度上の扱いに違いが出ます。
h3>フリーランスはひとつの「働き方」
フリーランスとはさまざまにある「個人の働き方」のひとつです。企業や団体に所属することなく自力で案件を獲得して、対価として報酬を得る仕事のスタンスをそのように呼びます。
仕事の内容や報酬額によって案件を受けるか決められるなど、企業と雇用関係を結んでいない分自由に仕事をできる点が最大の魅力です。こうした活動自体は、税務署に開業届を提出しなくても行えます。
h3>税務署に開業を申請したのが個人事業主
個人事業主とは「税務署に開業届を提出して何らかの事業を行っている人」を指します。ここで言う「事業」とは内容に継続性と反復性が認められる仕事のことです。
こうした要件を満たさない一部の仕事は開業が認められないことがありますが、エンジニアの場合は問題なく開業できます。
h2>開業届を出す3つのメリット
h3>社会的な信用を得やすくなる
個人で事業を始める場合は、原則として開業届を提出するべきとされています。ただし、独立時に開業届を提出しないことに対する罰則は特に設けられていません。基本的には適切に確定申告を行い、納税の義務を果たしさえすれば問題はありません。
一方で開業届を提出し、個人事業主として活動することでいくつかのメリットを受けられます。
h4>(1)屋号付きの銀行口座が開設可能
開業届の提出時には、自身の商業上の名前である「屋号」を付けられます。特に駆け出しのフリーランスは組織に所属していない分、どうしても社会的信用が低くなりがちですが、屋号があれば個人事業主として実体のある事業を行っていることが一定程度保証されます。そのため、屋号がない状態に比べると社会的信用を得やすい可能性があります。
また、屋号付きの銀行口座の開設もできるようになります。プライベートの口座と区別して事業資金を管理しやすくなりますし、屋号のない口座に比べるとクライアントからの信頼度が高まりやすいという利点があります。
h4>(2)家族の給与を経費計上可能
個人事業主であれば、配偶者や子どもなどの親族を「事業専従者」にして給与を支給し、経費として計上することが可能です。事業専従者とは「個人事業主と生計を一にして事業を行う」人物のことです。
税法上、家族への給与支払いは原則的に認められていませんが、事業専従者として申告すれば可能です。これによって一定程度の節税が図れるでしょう。ただし、扶養控除、配偶者控除などの所得控除が利用できなくなるので注意してください。
h4>(3)青色申告が可能
確定申告の方法は「青色申告」と「白色申告」の2種類がありますが、個人事業主として開業し申請することで「青色申告」が行えるようになります。詳しくは後述しますが「青色申告」は「白色申告」よりも節税効果があるので、確定申告はぜひ「青色申告」にしたいところです。
h4>(4)各種支援制度を受けやすくなる
個人事業主は国や地方自治体、商工会議所が実施するさまざまな支援制度を受けられます。応募期間が決まっているものや、支援条件が付いているものもあるので注意しましょう。
h3>小規模事業者持続化補助金を受けられる
幅広い範囲のフリーランス、個人事業主を対象とした補助金制度です。商工会議所または商工会に経営計画を提出して、アドバイスを受けることを条件に、50万円を通常枠の上限としていくらかの補助を受けられます。小規模事業者とはこの場合、常時使用する従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、 それ以外の業種の場合20人以下である事業者 です。
小規模事業者の販路開拓等の取り組みに対する支援を充実させるため、2022年10月現在、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠といった特別枠が拡充されています。インボイス枠は上限が100万円、それ以外の枠は上限が200万円です。補助金活用例として以下のような事例があります。
- 古民家カフェに厨房を増設し地元商店街とのコラボメニュー開発や地域住民のためのイベントを開催することで売り上げが増えた
- 蕎麦屋が高性能フライヤーを導入し、新メニュー開発と地元メディアへの出稿で新規顧客獲得に成功した。
税務署に開業届を提出してあっても、開業届に記載された開業日が補助金の申請日より後であった場合や、申請時点ではまだ実際に事業を開始していなかった場合などは、補助金の対象外となるので注意が必要です。
参考:
小規模事業者持続化補助金
h3>ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進事業(ものづくり補助金)を利用できる
「ものづくり補助金」となっていますが、製造業だけでなく幅広い範囲の業種を支援する補助金制度です。クラウドサービス利用時の専用ソフトウェア購入費、その他の情報システムの購入経費などが補助対象となる可能性があります。補助金額の上限は1億円で、下限は100万円です。
元々は従業員の雇用改革のための制度として導入されているため、業務委託だけではなく自分でチームを作り開発していくような、スタートアップ志向のある方向けの補助金です。
参考:令和元年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領〔ビジネスモデル構築型〕(4次公募)
h2>開業のために必要な手続き
実際に個人事業主として開業するために必要な手続きの方法を紹介します。
h3>(1)開業届を入手する
開業届は税務署を直接訪問するか、国税庁のWebサイトからPDFをダウンロードすることで入手できます。税務署に提出する分と自分の控え用として2部用意しましょう。なお、開業届の提出は事業開始後1ヶ月以内が期限とされています。
h3>(2)必要事項の入力と書類の準備
住所や氏名、業種といった基本事項のほか、屋号なども記載する必要があります。また、事前に従業員を雇うことが決まっている場合は、従業員の数や給与の支払状況などの情報も求められます。事業専従者給与に関する届け出や青色申告をする場合は、一緒に申請書を用意しておきましょう。
写真付きマイナンバーカードのコピーも提出が求められますので、事前に準備しておくとよいでしょう。
h3>(3)提出
提出方法は税務署の窓口で直接渡す方法と郵便で送る方法の2通りがあります。窓口提出の場合は、提出用と控え用として、開業届を2部提出します。郵送では、提出用の開業届と控えのほか、マイナンバーカードの両面コピーと、切手を貼り付けた返信用封筒を、すべて封筒に入れて投函します。開業届が無事に受領されれば、返信用封筒に控えを入れて送付してくれます。
h2>フリーランスや個人事業主になった場合の税金はどうなる?
フリーランスや個人事業主は会社員と違い、自分で税金を計算し支払わなければなりません。また、会社員には課されないけれど、個人事業主やフリーランスには課される税金もあります。
h3>税金は大きく分けて5種類ある
フリーランスや個人事業主が支払う税金として知っておくべきものは、大きく5種類に分けられます。所得税、復興特別所得税、住民税、消費税、個人事業税の5つで、このうち最も重要なのが、事業により稼いだお金を元に課される所得税です。
所得税は、収入から必要経費と各種控除の額を引いた後の値が大きいほど高い税率が適用される、累進税率という仕組みの税金です。基本的には収入が多くなるほど税率が高くなり負担が重くなるという特徴があります。フリーランスや個人事業主の所得税で注意が必要なのは、報酬の種類によっては源泉徴収されていることがあるという点です。
すべての収入や必要経費などを合わせて算出した支払うべき所得税額よりも、源泉徴収されていた金額の方が大きかった場合は、納めすぎていた分が確定申告により還付され、少なかった場合は足りない分を納付します。自分の報酬からいくら源泉徴収されているのか、きちんと把握しておきましょう。
h3>確定申告はしなければいけない?
所得税については法律により、1月1日から12月31日までの1年間で得た所得について、次の年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をして納めるべき税額を算出し、納付することと定められています。
収入が必要経費よりも少ない場合など例外はありますが、基本的に確定申告は期限内に行わなければなりません。定められた期間より遅れて申告をしたり所得金額の決定を受けたりすると、本来納めるべき所得税だけでなく、無申告加算税も課されます。申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告すれば、場合によっては無申告加算税が課されないこともあります。
申告期限を過ぎてから納付する所得税には、利息にあたる延滞税が課されます。申告期限を過ぎてしまったら、1日でも早く申告することが重要です。
h2>確定申告は青色申告?それとも白色申告?
確定申告には2つの方法があります。「青色申告」と「白色申告」です。「青色申告」は「白色申告」に比べ、税金面で有利になる特長があります。個人事業主として開業し、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで「青色申告」が行えるようになります。
h3>2つの違いは会計帳簿
「青色申告」とは、日々の事業活動を帳簿へ適切に記帳し、その記帳に基づいた正確な申告をすることにより、税金の取り扱い上いくつかの特典が得られるようになる制度です。「青色申告」と「白色申告」の大きな違いは、会計帳簿にあります。
「青色申告」をする人は、原則として正規の簿記の原則に基づき記帳することが求められます。正規の簿記とは、損益計算書と貸借対照表を導き出せる組織的な簿記の方式をいい、一般的には複式簿記による記帳が該当します。仕訳帳・総勘定元帳といった主要簿のほか、現金出納帳・売上帳・仕入帳・商品有高帳・売掛金元帳・買掛金元帳・固定資産台帳といった補助簿も記帳します。
そして年末に、商品や消耗品の棚卸しを行い棚卸表を作成したり、減価償却費の計算をしたりといった決算処理をして、損益計算書と貸借対照表を作成します。作成した帳簿や損益計算書・貸借対照表などは、7年間保存しなければなりません。
「白色申告」の人も、収入金額や必要経費に関する事項を記帳し、定められた期間保存する必要がありますが、形式の指定はありません。
h3>白色申告にメリットはないって本当?
「白色申告」は、「青色申告」のように税金面で有利になる点がありません。「白色申告」が「青色申告」と異なるのは帳簿の形式に指定がない点で、簡易なものでも問題がありません。
しかし、原則として複式簿記のような正規の簿記の原則に基づく記帳が求められる「青色申告」でも、簡易な帳簿による記帳は認められており、額は少なくなりますが税金面で有利になる青色申告特別控除が受けられます。また、「白色申告」では経費とならないけれど、「青色申告」であれば経費に計上できるものがあります。家族へ支払った給与を経費にできる「青色事業専従者給与」の仕組みや、未回収の売掛金などを損失の見込み額として経費に計上できる「貸倒引当金」(一括評価によるもの)は、青色申告者のみが利用できるものです。
さらに、主に自宅で仕事をする人の場合は、家賃や電気代などを一部経費として計上でき、白色申告よりも経費として認められやすくなっています。「白色申告」でも「青色申告」でも、日々の取引について記帳し、帳簿を保存しなければいけないという点は同じです。税金面で何も優遇されない「白色申告」には、メリットがあまりありません。
h3>青色申告は控除によって納付する税金を大幅に減らせる
正規の簿記の原則に基づく記帳をしている「青色申告」の人は、その記帳に基づいて作成した損益計算書及び貸借対照表と確定申告書を、申告期限内に提出すると、最高で55万円の青色申告特別控除を受けられます。
上記の人のうち、e-Taxによる電子申告を行うか、優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録により保存している人は、最高で65万円の青色申告特別控除を受けられます。
正規の簿記の原則による記帳が難しくてできないという場合でも、「青色申告」の人は簡易な帳簿を作成することで、一定の要件の下で最高10万円の青色申告特別控除を受けられます。「青色申告」をすると、青色申告特別控除の額だけ利益が少なく計算されるので、納付する税金を減らせるというメリットがあります。
h2>節税対策に有効な方法も把握しておこう
「青色申告」以外にも、節税対策として有効な方法があります。使える制度を知らないと、過剰な税金を支払うことになってしまうので、しっかり把握しておきましょう。
h3>経費や控除の見直しを行う
所得税は収入から必要経費や所得控除の額を引いた値に税率をかけ、そこからさらに税額控除額を引いて算出します。収入から引ける必要経費や控除の額が大きいほど、支払うべき税金は少なくなります。経費や控除を見直し計上漏れをなくすことは、すぐにできて有効な節税対策です。
経費とは、事業を行うためにかかった費用のことを指します。同じものに対する支出でも、その目的によって経費に該当するか否かという違いが生じます。例えば、自分の昼ご飯として支払ったレストランの飲食代は経費にできませんが、取引先とのランチミーティングとしての飲食代は経費にあたると考えられます。
その支払いが経費に含まれるか否かを決めるポイントは3つあります。ひとつめは、「事業との関わりを客観的に証明できること」です。税務署から指摘を受けたときに、売り上げとの関連性を証明して正当性を主張できるのであれば、経費として認められる可能性が高いです。
2つめは、「収入に対して釣り合いが取れているか」です。収入を大幅に超えるような接待交際費を計上したり、常識的に考えて不要と思われるほどの消耗品費を計上したりといった、不自然な経費については認められない可能性が高まります。
3つめは、「事業主自身のための支払いでないか」です。個人事業主に対しては福利厚生費という概念がなく、自分のためにした健康診断の代金や生命保険料などを経費に含めることはできません。従業員のための支払いであれば経費に含めることが可能です。事務所を他に借りず自宅と兼用している場合は、家賃や水道光熱費などの支払いについて、一部を事業のための支払いとして経費に計上できます。これを家事按分といい、費用によって按分の仕方が異なるので、計上漏れがないように確認することが大切です。
控除には、所得から引かれる所得控除と、算出された所得税額から引かれる税額控除があります。社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料・医療費・寄付金など、支払った金額に基づいて控除額が決まるものや、ひとり親控除・寡婦控除などの家族関係に基づくもの、配当控除のように収入に基づくものなどさまざまな制度があります。自分が該当する控除はないか、きちんと確認しましょう。
h3>減価償却の特例を上手く活用する
ひとつあたり10万円以上の資産は減価償却資産とされ、原則として費用に一括計上することはできません。税法上定められた耐用年数に渡り分割し、減価償却費として計上します。10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産の特例を使えば3年間で均等に償却できます。
「青色申告」をしている人は、さらに有利な少額減価償却資産の特例を使えます。これは、年間で300万円を上限として、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得したときに一括で経費に計上できる制度です。収入が多いときに資産を購入し、特例の適用を受ければ、節税効果が高まるので上手く活用しましょう。
h2>まとめ
個人事業主として開業することのメリットを簡単にまとめると、「社会的信用力の向上」や「各種税金の控除や補助金などの恩恵を受けやすくなる」ことにあります。特に開業することで可能になる「青色申告」は、節税効果の高い制度です。副業としてフリーランス活動を行う場合でもこうしたメリットを踏まえて、個人事業主として開業することを一度検討してみてもよいのではないでしょうか。
–>
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む