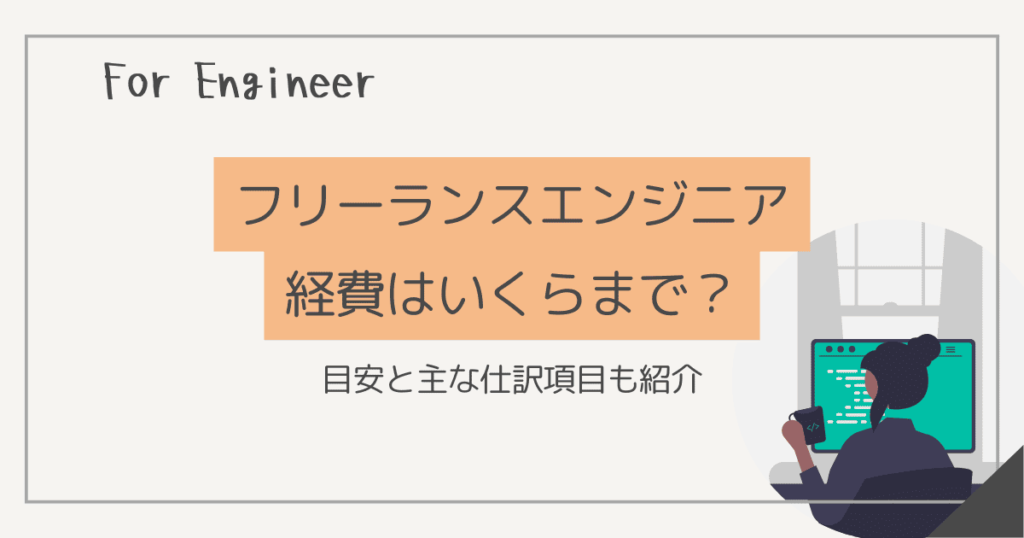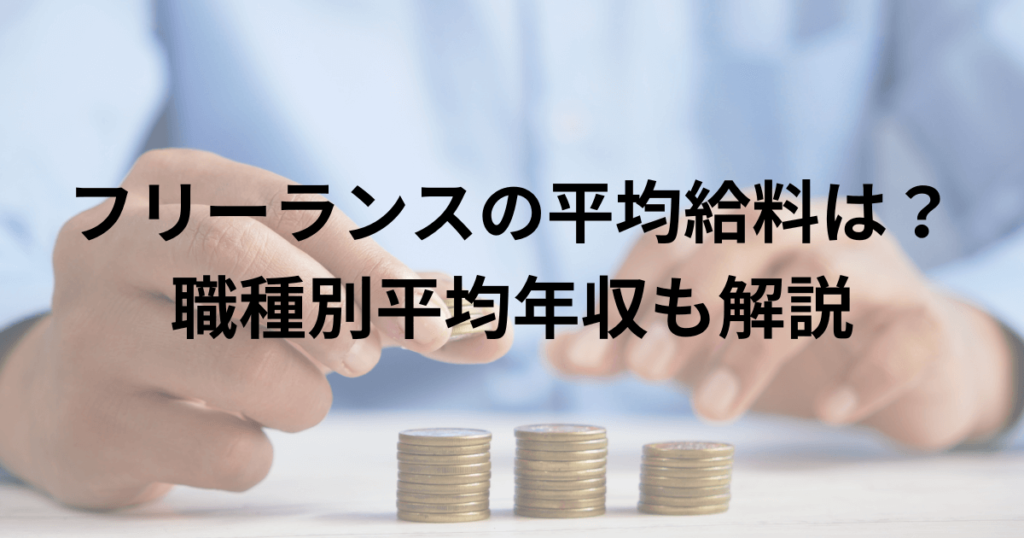フリーランスにおすすめの保険とは?保険が必要な理由もわかりやすく解説
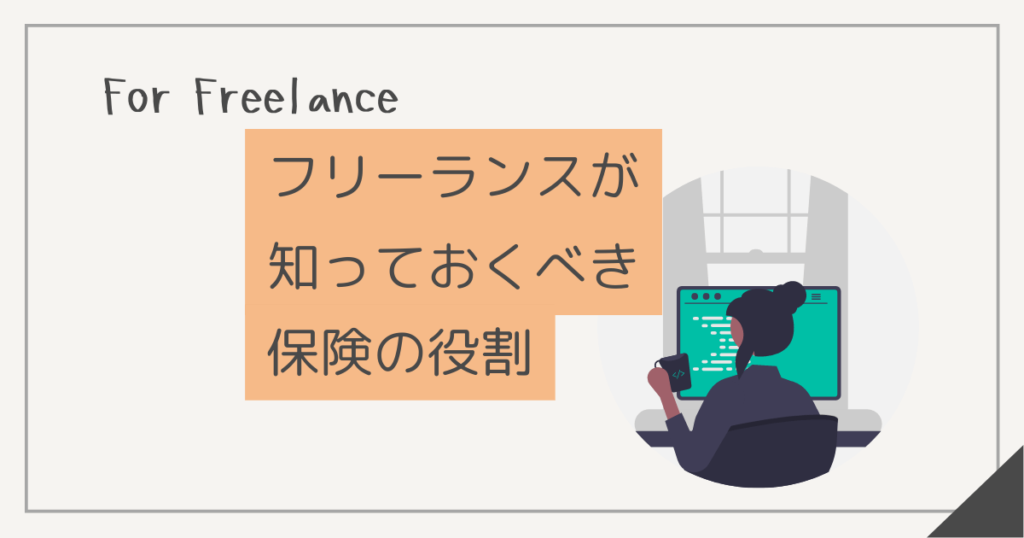
フリーランスは会社員に所属していた頃とは違い、健康保険と国民年金への加入・支払いを自分で行うことになり、保険料も大幅にアップします。それだけでなく、個人で働くには報酬未払いやトラブルへの賠償などのリスクが伴います。
フリーランスは働き方の自由度が高い分、リスク管理も自分次第です。フリーランスが加入することになる健康保険・年金と、リスクへの備えについてご紹介します。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む目次
保険には公的保険と民間保険の2種類がある
まずは、日本国内の保険制度についておさらいしましょう。
そもそも保険には、国や地方公共団体といった公的な機関が運営・管理を行っている公的保険と民間企業が商品として販売する民間保険の2種類が存在します。公的保険はさらに社会保険と労働保険に区分されます。
以下の表は、それぞれの役割や制度内容の違いについて比較したものになります。
| 項目 | 公的保険 | 民間保険 |
|---|---|---|
| 目的 | 最低限の生活保障 | 幅広いリスク保障 |
| 強制力 | 加入義務 | 加入は任意 |
| 加入審査 | なし | あり |
| 保険料 | 所得ごとに変動 | 契約ごとに変動 |
| 保険内容 | 一律 | 契約ごとに変動 |
| 解約 | なし | あり |
日本では、国民の最低限の安心や安全を守るため「国民皆保険制度」を採用しており、全ての人がなんらかの公的保険に加入することが義務付けられています。
一方で民間保険は、公的保険では賄いきれないリスクをカバーするために用意されている民間企業の商材で、加入は任意です。カバーしたいリスクやどこまでサポートしてもらうかを自由に選択することができるため、ご自身で不安がある部分を補うことができるプランを選択すると良いでしょう。
会社員とフリーランスで加入できる保険の違い
前章では公的保険と民間保険の違いについて紹介しましたが、公的保険の中でもいくつか分類が別れています。特に企業などの事業者に雇用されて働く会社員が加入できるものとフリーランスや個人事業主、自営業者が加入できるもので大きな違いがあります。
ここでは、それぞれで加入できる保険の違いについて紹介します。
会社員が加入できる公的保険の種類
会社員などが加入できる公的保険には以下のようなものがあります。
- 健康保険
- 雇用保険
- 労災保険
- 厚生年金保険
- 船員保険
- 共済組合
- 後期高齢者医療制度
このうち、特に加入者の多い健康保険/雇用保険/労災保険/厚生年金保険について以下で詳しく紹介します。
健康保険
健康保険は会社などに雇用される被用者の業務外のケガや病気、出産などの医療事案に対して必要な給付を行う公的医療保険です。
会社勤めをしている方は、基本的に全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入し、会社と折半で毎月の保険料を納付しています。企業によっては、企業グループで独自に設立した組合管掌健康保険に加入され、同じく会社と折半で毎月の健康保険料を納付することになっています。
雇用保険
雇用保険は失業した場合や育児、介護など働くことが難しい状況に置かれてしまった場合に、約3ヶ月から1年間給付金の支給を行う労働保険の一つです。
雇用保険の保障内容には、健康保険と同様に傷病手当金の給付も含まれていますが、再就職に向けた必要最低限の生活を保障するもので、健康保険とは目的が異なります。
健康保険と同じように事業者と被用者の双方が保険料を負担しますが、折半ではなく事業者の方が多く支払う仕組みになっています。
労災保険
労災保険は業務上または通勤中に発生した被用者のケガや病気、死亡に対して本人や遺族に必要な給付を行う労働保険の一つです。
健康保険や雇用保険の保険料は事業者と被用者が双方負担しますが、労災保険の保険料は全額事業者負担となります。事業主が支払う賃金総額から保険料を算出し、それぞれの労働者がもらっている給与に紐づいて給付金の額が決まります。
厚生年金保険
厚生年金保険は公的年金の一つで、主に厚生年金保険の適用事業所に勤務する会社員が加入し、定年退職後や被用者の障害・死亡に対して、その本人や家族に支払われる年金になります。
厚生年金保険料は事業者と被用者が折半で負担することになっています。そのため、後述する国民年金と併用することで、将来受け取る年金額が厚くなる仕組みになっています。
フリーランスが加入できる公的保険の種類
前章の会社員が加入できる保険に対して、フリーランスが加入できる公的保険は以下のようなものがあります。
- 国民健康保険
- 国民健康保険組合
- 所属していた会社の健康保険の任意継続
- 家族の扶養に入る
それぞれについて詳しく解説していきます。
国民健康保険
国民健康保険とは、都道府県および市町村が保険者となって運営する、公的な医療保険制度です。保険料は都道府県や市町村によって毎年保険料率が算定され、前年の所得や世帯の人数などをベースに算出されることとなります。よってこの保険料のことを国民健康保険税とも言い、事業所得に応じて納税額が変動します。
国民健康保険の他にもフリーランスに関わる税金は6種類あるので、あわせて確認しておくことをおすすめします。
国民健康保険には扶養という考え方はありません。世帯ごとに保険料を納付する方式を採っており、家族一人ひとりが被保険者という扱いになります。
保険給付の種類については、おおむね会社員が加入する健康保険と同じです。ただし、病気や怪我をしたときに一定期間給付される「傷病手当金」と出産に際して一定期間給付される「出産手当金」については、国民健康保険者が任意で行うものとなっていますが、実質給付はありません。
国民健康保険組合(国保組合)
国民健康保険の団体のひとつに、国民健康保険組合(国保組合)があります。これは医師や弁護士、建築業界、美容業界といったように、同種の職業・業界ごとに組織されている健康保険組合の団体です。
都道府県・市町村が運営する国民健康保険と異なり基本的に保険料は定額なので、保険料が安く抑えられる可能性があります。
国民健康保険組合は各地域・業種でさまざまで、例として以下にいくつか実在の保険組合を挙げています。
- 文芸美術国民健康保険組合
- 東京都医師国民健康保険組合
- 全国土木建築国民健康保険組合
- 大阪府小売市場国民健康保険組合
- 福岡県薬剤師国民健康保険組合
所属していた会社の健康保険の任意継続
会社に所属していて退職した場合には、会社の健康保険への加入を任意で続けることができます。条件は2ヶ月以上被保険者であることや期日内に申請することなどで、期間は最大2年間です。保険料の算出方法は会社に在籍していたときと同じです。
ただし傷病手当金や出産手当金は、条件を満たす場合のみ給付されることになるので注意しましょう。
家族の扶養に入る
家族が入っている健康保険の被扶養者となるのも手段です。被扶養者となると保険料を払わずに健康保険の制度を利用することが可能ですが、扶養の場合も年収が130万円未満であるなど、一定の条件を満たす必要があります。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込むフリーランスが民間保険にも加入した方がいい理由
公的保険に入っておけば、生活に困らないくらいの保障があり、民間保険に入る必要はないと感じられる方もいるかもしれません。ですが、一般にはフリーランスや自営業の場合、より幅広いリスクに備えておいた方がいいと言われています。
その代表的な理由を3つ紹介します。
仕事上のトラブルや賠償責任を自分で対処する必要がある
フリーランスとして仕事をする以上、複数の企業の企業秘密や外部に漏らしてはいけない情報を扱うことが多々あることでしょう。それらの情報の扱いについて、悪意がなくとも機密ファイルの紛失やウイルス感染で情報が外部に漏れたり抜き取られてしまうリスクがあります。
他にも納品物に不備があった、納品期日に間に合わず、クライアントに実害を与えてしまった場合などは非常に大きなトラブルに発展しかねません。
そうした場合には損害賠償請求をされてしまうことがあります。企業に雇用される立場であれば、企業が守ってくれますが、フリーランスの場合はこれらの賠償責任を自己負担しなければならないため、保険によって万が一のリスクに備えておくことが重要です。 また、仕事上のトラブルに関しては、依頼内容に適切に対応したにもかかわらず、不当な報酬減額や中途解約なども起こるケースがあります。そうしたケースでは保険ではなく、フリーランス新法に則り、依頼者側への対応是正勧告ができる場合があります。この法律は2024年秋頃までに施行される予定ですが、フリーランスとして働く方にとってメリットの大きい法律のため、こちらもあわせて理解しておくと良いでしょう。
ケガや病気で働けない場合の手当てがない
フリーランスは雇用保険と労災保険といった労働保険に加入できません。
雇用保険に加入していると、会社員が失業した際や育児休業、介護休業となった際などにそれぞれ、基本手当(いわゆる失業手当)や育児休業給付金、介護休業給付が支払われます。労災保険は、労働者が仕事で怪我をしたときに障害の程度によって一定額が給付される制度です。
フリーランスは労働基準法に適用される“労働者”ではないため、労働保険を利用できず給付も受けられないのです。したがってフリーランスとして働く場合は、妊娠、病気や怪我などで働けない場合、その治療費は全額自己負担になりつつ、働けない期間収入がゼロになるリスクがあります。ケガや病気はいつ起こるかわからず、一度起きてしまうとまた元の生活に戻ることは容易ではありません。
そのため、保険で備えておくことが安心につながります。
老後の生活や自身が亡くなった場合の家族が困窮するリスクがある
厚生年金保険の適用事業所に勤務する会社員であれば、国民年金と厚生年金をあわせた2階建て構造で年金積み立てが行われ、その分老後の受け取り金額も厚くなっています。
一方で、フリーランスの場合は国民年金のみの積み立てで老後に受け取れる金額も老齢基礎年金のみとなります。令和4年6月支払い分からの老齢基礎年金は満額で月64,816円で、それまでと変わらない生活をしていくには物足りない資金と言えます。
また、遺族年金や障害年金も受給額が少ないため、老後のリスク管理を見据えて今から保険加入することも大切です。
フリーランスにおすすめの民間保険
前章で紹介したようなリスクに対して、どのような民間保険で備えるのがいいかお悩みであれば、以下にそれぞれのリスクに対応した保険を挙げましたので参考にしてみてください。
情報漏えいや納期遅延に関する保険
情報の漏えいや著作権侵害などによる事故の補償を行う保険や、報酬未払い等の法的トラブルを解決するための弁護士費用を負担する保険があります。
GMOの「FREENANCE」では情報漏えいや納品物の瑕疵などについての損害賠償請求、病気や怪我で働けなくなったときの補償があります。
「フリーランス協会」では会員(年会費1万円)になると、フリーランスに起こりがちなビジネス上のリスクを幅広くカバーする賠償責任保険が自動で付与されます。
また任意加入である「フリーガル」(引受保険会社:損害保険ジャパン日本興亜株式会社)は、報酬未払いなどのトラブルに対し弁護士を介して解決する場合に、弁護士費用が保険金として支払われるサービスです。
これらを利用した場合は年会費を必要経費とすることが可能です。
生命保険の休業補償
病気や怪我で働けなくなったときの補償は、会社員よりも手厚く考えておきたいところです。
例えば住友生命には、就労不能の場合に一時金が受け取れる「生活障害収入保障特約」などの保障があります。病気や怪我のための保険は時代によって新しい商品が出るため、定期的に見直しをするのがよいでしょう。
自身や家族が困窮するリスクに関する保険
自身や家族が困窮するリスクへの対策は、収入保障保険や個人年金保険がおすすめです。
収入保障保険は、保険対象者が保険期間中に死亡したり重度の障害を負った場合、その時点から満期まで死亡保険金をお給料のように月々の給料のような形で受け取ることのできる掛け捨てタイプの死亡保険です。
個人年金保険は年金の補てん目的で加入する私的年金の1つになります。あらかじめ定められた期間もしくは保険対象者が亡くなるまで一定額の年金を受け取ることができます。また、特定の条件を満たせば確定申告の際、「個人年金保険料控除」を受けることもできます。
個人年金については次章でも詳しく説明しますので参考にしてみてください。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込むフリーランスが加入する年金
国民年金
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人に加入が義務付けられている公的な制度です。
働いている状況によって第1号、第2号、第3号という区分があり、国民年金にのみ加入するフリーランスの場合は第1号被保険者となります。
フリーランスが入る年金制度は、基本的に国民年金のみです。会社員は国民年金に加えて厚生年金に加入することになり、保険料は労使折半で給与から天引きされますが、フリーランスは自分で年金制度に加入し、保険料も全額自分で支払わなければなりません。
【任意】付加年金制度や国民年金基金制度
国民年金にのみ加入する自営業・フリーランスは会社員と比べて将来貰える年金の額が少なくなるため、将来受給する年金の額を増やすための制度として「付加年金制度」と「国民年金基金制度」があります。
付加年金制度を使えば、毎月の国民年金保険料に月400円の付加保険料を上乗せして納めることで、将来受給する年金の額を増やせます。国民年金基金制度も同じく月々の保険料に上乗せして納める公的な個人年金で、こちらは上限が月68,000円です。
付加年金制度と国民年金基金制度に同時に加入することはできません。
【任意】個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)
年金増額のための制度はほかに、証券会社や保険会社が行っている私的な個人年金があります。個人型確定拠出年金iDeCoは掛け金を自由に決めて毎月積み立て、60歳になるまで任意の金融商品を運用し、60歳以降に老齢給付金または一時金として受け取ることができる商品です。給付額は掛け金と運用益の合計額なので、運用成績次第では年金額を掛け金以上に増やすことが可能です。
自営業の場合、拠出額は5,000円~68,000円(国民年金基金または国民年金付加保険料との合算)までとされます。
掛け金を運用する商品を自分で決めることになり運用方法も幅広いため、資産運用の知識が必要です。
フリーランスと個人事業主の違いを解説した記事でもフリーランスになった場合の年金対策についてまとめています。こちらの記事では確定申告や節税対策の観点から解説していますので、効果的な節税方法も知りたい方はぜひご覧ください。
まとめ
労使折半の会社員と違い、フリーランスは各種保険料が高くなりがちです。時代が進むにつれて法律は変わる可能性がありますし保険サービスも新しいものが登場しますが、誰かが教えてくれるとは限らず、知らないことで損をするかもしれません。
法律上何らかの形で必ず支払うことになる健康保険・年金と、フリーランスならではのリスクを払拭するための保険サービスについては、折に触れてチェックしておきましょう。
保険や税金のほかにも、スキルシートの作成やキャリアプランの設計などフリーランスになるとすべき大事なことがさまざまあるのでこちらも確認しておくことをおすすめします。