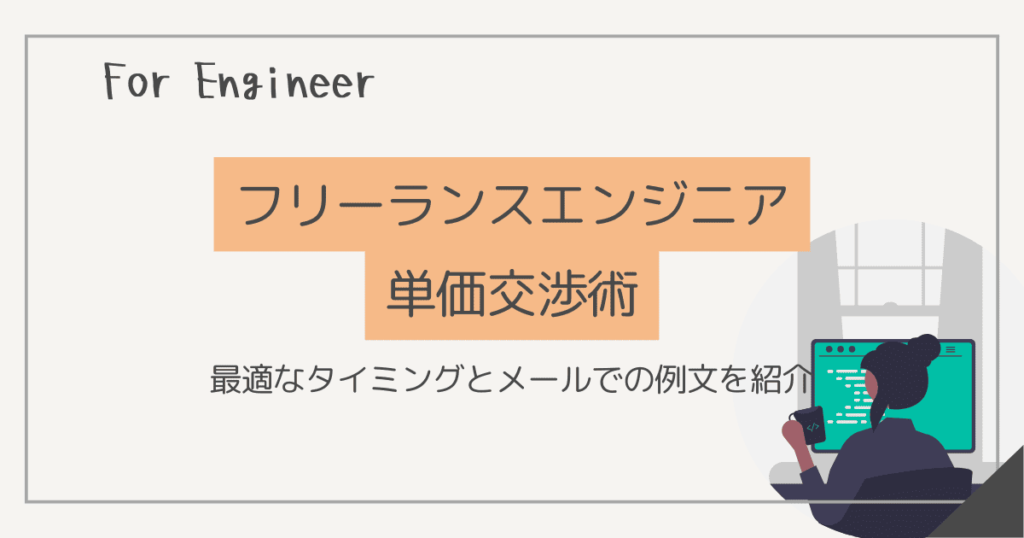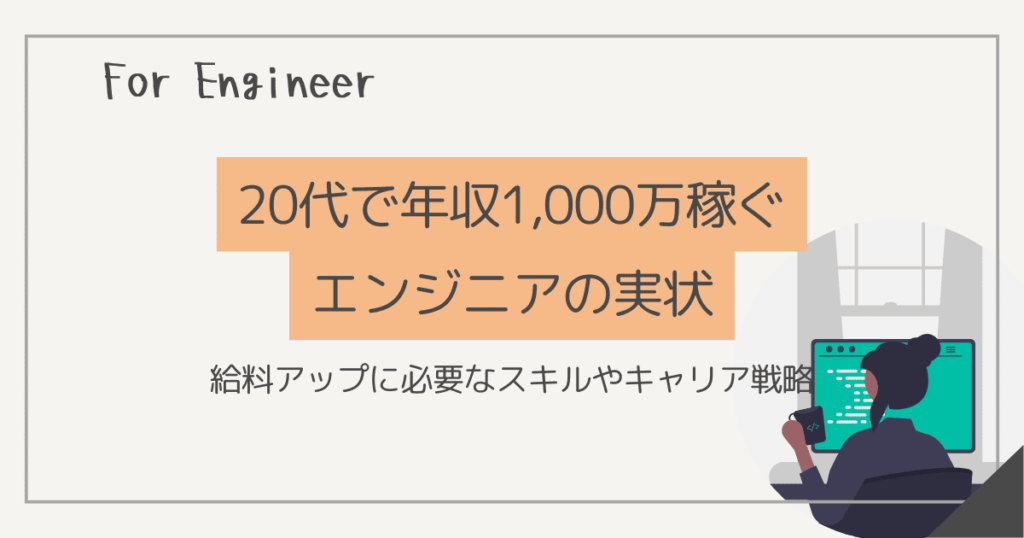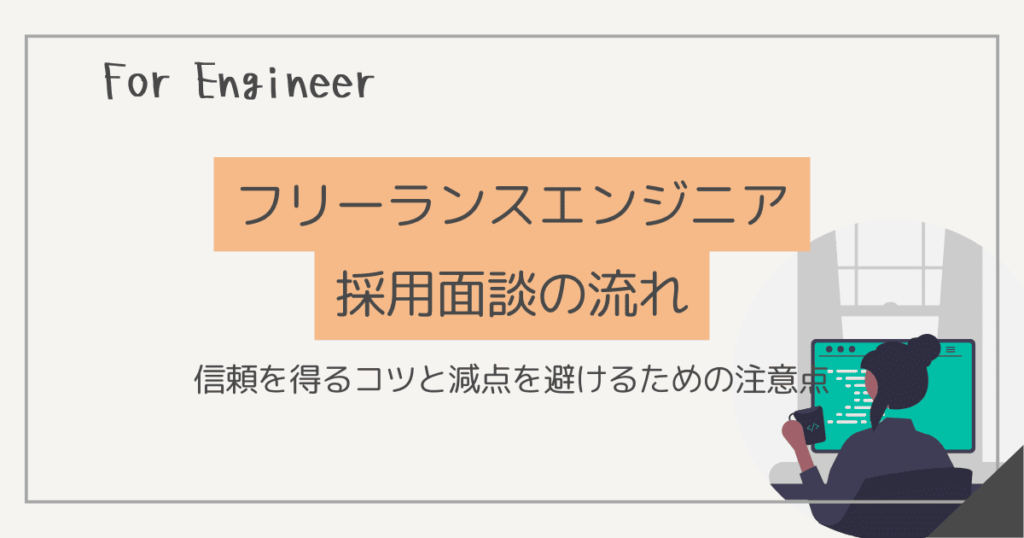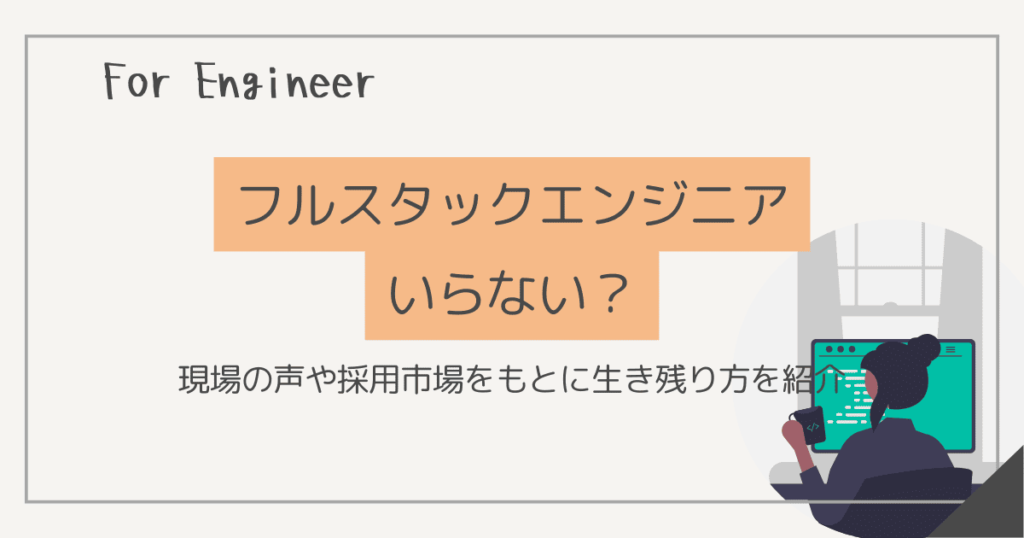クラウドエンジニアはやめとけといわれる理由とは?未経験からの難易度や将来性も含めて解説
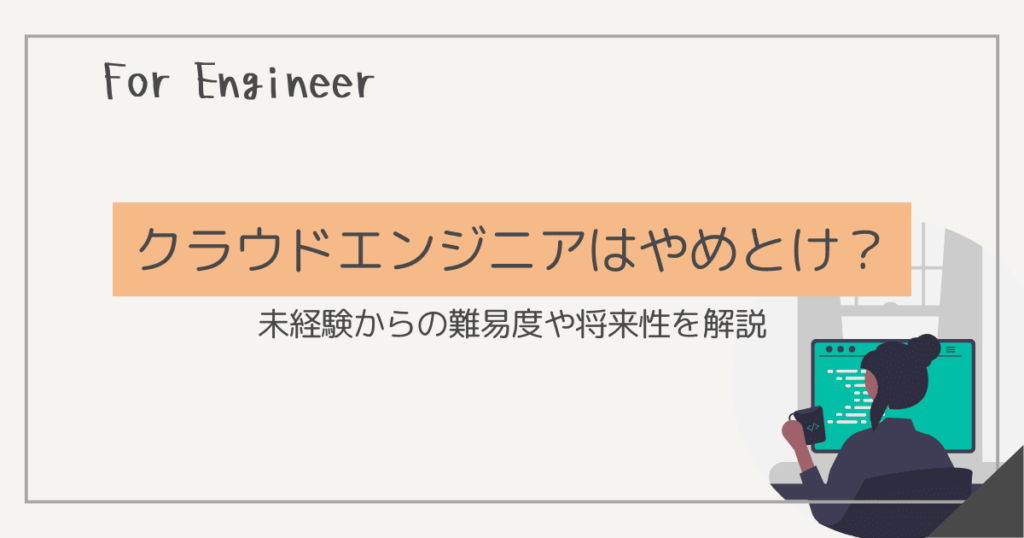
AWSやMicrosoft Azureなどのクラウドサービスが広まるにつれて、クラウドエンジニアへの注目が高まっています。一方で「エンジニアは残業が多すぎる」「最新情報を追いかけるのが大変」という声もみられ、「クラウドエンジニアはやめとけ」という人もいるのが現状です。
本記事ではクラウドエンジニアの実情に注目し、「やめとけ」と言われる理由も深掘りします。未経験からクラウドエンジニアを目指せるのか、将来性があるのかといった点も解説するので最後までご覧ください。
なお、フリーランスや副業でクラウドエンジニアとして働きたい方は、FLEXY(フレキシー)をご活用ください。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む目次
クラウドエンジニアはやめとけといわれる6つの理由
クラウドエンジニアは最新技術を扱う魅力的な職種である一方で、実際の現場からは「やめとけ」との声があがるのも現実です。ここでは、「クラウドエンジニアはやめとけ」と言われる理由について、以下の6つの視点で解説します。
- 納期前や障害対応で残業が増えやすいから
- 技術の進化が早く勉強し続けなければならないから
- 障害対応やミスの責任が重くプレッシャーが大きいから
- 年収(単価)に対して見合わない責任や労力が負担になるから
- 顧客や社内との調整がストレスになりやすいから
- オンコールや24時間対応で生活リズムが乱れることもあるから
納期前や障害対応で残業が増えやすいから
クラウドエンジニアの仕事は納期前になると残業が常態化する傾向にあります。厚生労働省が公表している「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、情報サービス業に従事している人の超過実労働時間数は月11時間とそれほど多くはありません。ただしプロジェクトの終盤にもなると月80時間以上の残業を強いられる場合もあり不満につながっています。
また無事にサービスが稼働を開始しても、障害対応が常に付きまといます。仮に、24時間365日サービスを提供している場合、深夜や休日であっても即座に対応しなければなりません。さらに、障害が発生しても通常業務を行う必要があるため、必然的に残業時間が増える傾向にあります。
技術の進化が早く勉強し続けなければならないから
クラウド技術は驚異的なスピードで進化しており、AWS、Microsoft Azureなどの主要プラットフォームは毎年数多くの新機能やサービスをリリースしています。2025年のデータによると、AWSだけでも300を超えるサービスが存在しており、新機能の追加やアップデートのたびにクラウドエンジニアはキャッチアップしなければなりません。
業務時間内だけでは到底習得できないため、平日の夜や週末を自己学習に費やすクラウドエンジニアもいます。継続的な学習負担がプライベートの時間を圧迫するため、不満の声があがる要因となっているのです。新サービスに即座に対応できないと市場価値が急速に下がるというプレッシャーも大きな負担です。
障害対応やミスの責任が重くプレッシャーが大きいから
障害対応やミスに対する責任の重さも「やめとけ」と声があがる理由です。クラウドシステムで障害が発生しサービスが停止してしまうと、企業に大きな経済的損失をもたらしてしまうからです。システム障害対応が遅れると、生じる損失額は平均で50億円との調査結果もあります。
このような状況下で働く場合、クラウドエンジニアには膨大なプレッシャーがかかります。復旧作業中に冷静さを維持し、二次障害を起こさないための慎重さと、迅速に問題を解決するスピードの両立が求められるのです。もし障害が自分のミスによるものだとわかれば、心理的負担はかなりのものになるでしょう。プレッシャーに強いメンタルを持っていないエンジニアにはおすすめできない職種です。
年収(単価)に対して見合わない責任や労力が負担になるから
クラウドエンジニアの年収は一般的に高めと思われがちですが、実際には負う責任や求められる労力と比較すると必ずしも釣り合ってはいません。求人ボックスで公開されている2025年2月時点の平均年収は正社員の場合で545万円です。
24時間365日のシステム稼働を支える責任と、それに伴う労働時間や精神的負担を考慮すると決して高いとはいえません。特にSES企業に所属するエンジニアの場合、案件報酬の一部が企業の取り分となるため市場価値の70%程度しか報酬が得られないケースも存在します。
クラウドエンジニアには技術スキルに加え、プロジェクト管理能力やコミュニケーション能力まで求められる場合もあります。求められるスキルに比べて報酬が低いため、「やめとけ」という声があがっても仕方ないでしょう。
顧客や社内との調整がストレスになりやすいから
クラウドエンジニアの業務は純粋な技術作業だけではありません。顧客や開発部門、営業部門、社内インフラ部門など、異なる背景や目標を持つ部署との連携が求められます。
ストレスになりやすい場面に、技術に詳しくない顧客や営業担当との調整があげられます。「なぜその方法ではできないのか」「なぜそれほど時間がかかるのか」という質問に、専門用語を使わずに納得してもらうためのコミュニケーションスキルは、誰しもが持ち合わせているわけではありません。
複数のステークホルダーから相反する要求が出された場合、クラウドエンジニアは板挟みとなりつつ調整を行う必要があります。対人コミュニケーションが得意でないエンジニアにとって大きなストレス要因となりうるのです。
オンコールや24時間対応で生活リズムが乱れることもあるから
多くのクラウドサービスは、24時間365日稼働しています。そのため、多くのクラウドエンジニアは「オンコール」と呼ばれる緊急時対応体制に組み込まれている場合が多いです。
オンコール体制では、深夜や早朝、週末や祝日であっても発生した障害に対応しなければなりません。予定していた家族との外出をキャンセルしたり、深夜の緊急トラブルで睡眠不足になったりする場合もあります。
さらに、国際的なプロジェクトに関わると、海外のチームとの会議のために深夜や早朝の時間帯に打ち合わせが設定されるため生活リズムが不規則になりがちです。身体的な疲労だけでなく、精神的な疲労や家族関係の悪化など、長期的な問題につながる可能性もあります。
リモートワーク廃止の流れもクラウドエンジニアはやめとけの声の追い風に
クラウドエンジニアの魅力に「リモートワークで働ける」点があげられます。ただし、コロナ禍で一気に普及したリモートワークも近ごろでは多くの企業が方針転換し、出社を推奨または義務化するようになってきました。
リモートワークには「通勤時間の削減」「集中できる環境での作業」「地方在住でも都市部の案件に参画可能」といったメリットがあります。なかでも不規則な勤務時間や深夜対応が必要なクラウドエンジニアにとって、通勤の負担がなくなるリモートワークは働きやすさを向上させる重要な要素です。
出社を求める企業が増えるにつれて、クラウドエンジニアの働き方の柔軟性が失われつつあり、「クラウドエンジニアはやめとけ」という声にさらに拍車がかかっています。
未経験からクラウドエンジニアを目指すのもやめとけ?
未経験からクラウドエンジニアを目指すのは不可能ではないものの、相当に険しい道のりであると言わざるを得ません。その理由を以下の2つの視点で解説するので、クラウドエンジニアを目指す未経験者は最後までご覧ください。
- 前提となるネットワーク・インフラ関連の知識の学習コストが高い
- 知識・資格よりも実務経験を重視される現場がほとんど
前提となるネットワーク・インフラ関連の知識の学習コストが高い
クラウドエンジニアとして働くには、クラウドサービス自体の知識だけでなくネットワークやインフラの知識が必須です。TCP/IP、ルーティング、ファイアウォール、ロードバランサーなどの基本概念に加え、セキュリティやデータベース、仮想化技術など、幅広い知識が求められます。
独学では体系的に理解するのは非常に難しいのが現実です。専門書を読んでも実機での検証環境がなければ理解が深まりませんし、概念だけを学んでも実際の運用に役立てるのは容易ではありません。
ネットワーク・インフラ関連の技術も、常にアップデートを繰り返しています。一度学んだ知識がすぐに陳腐化するリスクもあるため継続的な学習が必要です。この高い学習コストが「やめとけ」の声につながっています。
知識・資格よりも実務経験を重視される現場がほとんど
クラウドエンジニアの現場では、資格や知識よりも実務経験が重視される傾向にあります。仮に、AWSやAzureの認定資格を持っていたとしても実務経験がなければ、採用時に苦戦するでしょう。実際の案件でも、資格保持を要件にしている場合は少なく実務経験を重視している場合が大半です。
未経験者の中には「資格を取れば就職できる」と考える人もいますが、現実は甘くありません。資格はあくまで知識を証明するツールでしかなく、現場で使える人材であることの証明にはならないからです。座学だけでは身につかない予期せぬトラブルや複雑な要件に対応する能力をアピールする必要があります。実務経験を積みづらい環境が、「やめとけ」と声があがる要因となっているのです。
やめとけとの声もあるクラウドエンジニアの将来性は?
「やめとけ」という声も聞かれるクラウドエンジニアですが、市場としての将来性は依然として高いと言えます。総務省の「令和6年版 情報通信白書」によると、世界のパブリッククラウドサービス市場規模は毎年大幅に増加しており、今後も高い成長率を保つと予想されています。
ただし、単純な運用やインフラ構築のみを担当するエンジニアは、自動化ツールやAIの進展により代替されるでしょう。クラウドエンジニアとして生き残るためには、身につけたスキルを活用したキャリアパスも含めて、計画的な取り組みが求められます。
クラウド市場の成長とともに、高いスキルを持つエンジニアの市場価値は今後も上昇していく可能性が高いと言えます。この追い風にのって、活躍できるクラウドエンジニアを目指しましょう。
クラウドエンジニアとして独立・副業で実務経験を積むならFLEXY(フレキシー)
クラウドエンジニアを目指すにはハードルが高いと感じた方もいるでしょう。それでもクラウドエンジニアとして独立・副業で実務経験を積みたいのであればFLEXY(フレキシー)をご活用ください。
FLEXYが保有する多くの案件の中から、あなたに最適な案件を紹介します。専任のコーディネーターが、スキルや経験、希望の働き方などを丁寧にヒアリングを行い、あなたのキャリアパス構築を支援します。
クラウドエンジニア経験がない場合でも、戦略的な案件獲得を通じて着実なステップアップが可能です。「やめとけ」と言われるクラウドエンジニアでも、FLEXYとの二人三脚であれば必ず実現できるでしょう。登録は無料で60秒で入力できます。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込むこんな人はやめとけ!クラウドエンジニアが不向きな人の特徴
ただでさえハードルの高いクラウドエンジニアは、誰にでも向いているわけではありません。特に以下のような特徴を持つ方は、クラウドエンジニアとして活躍するのは難しいでしょう。
- 新しい技術に興味が持てない
- プレッシャーや責任のある仕事が苦手
- 人と関わるのが極端に苦手
- 柔軟な発想ができない人
新しい技術に興味が持てない人は、日進月歩で進化するクラウド技術を追いかけられずスキルが陳腐化してしまいます。「一度覚えたやり方を変えたくない」という考えであれば、活躍し続けるのは困難です。
プレッシャーや責任のある仕事が苦手な人や、人と関わるのが極端に苦手な人も注意が必要です。重大な責任とプレッシャーの中で顧客や他部門との調整が求められるため、戦力として期待できません。
柔軟な発想ができない人も苦労します。システム障害やセキュリティインシデントなど予期せぬ事態に直面した際、臨機応変に対応できる思考力が求められるからです。
クラウドエンジニアが合わないと感じたら検討したいキャリアの選択肢
クラウドエンジニアとして働くなかで「自分には合わないかも」と感じたら、IT業界内でのキャリアチェンジを検討しましょう。ここでは、クラウドエンジニアとしての経験やスキルが活用できる選択肢を4種類紹介します。
- Webエンジニアやアプリ開発職への転向
- 社内SEやITコンサルなど比較的安定した職種への転向
- セキュリティ系・データ分析系の職種への転身
- フルスタックエンジニアとして幅広く対応できるスキルの習得
Webエンジニアやアプリ開発職への転向
クラウドエンジニアからWebエンジニアやアプリ開発職への転向は、おすすめのキャリアパスです。クラウドエンジニアが持つインフラ知識が、パフォーマンスチューニングやアプリケーション設計に活用できるため開発チームでも重宝されるからです。
Webエンジニアの主な仕事は、フロントエンドからバックエンドまでWebサービスの開発・保守です。クラウドエンジニアと比較すると、大規模障害のリスクが低く、精神的プレッシャーが軽減されます。
アプリ開発職では、iOS/AndroidなどのモバイルアプリやPCアプリの開発に携わります。オンコール対応が少なく、比較的規則的な勤務体系で働けるため、ワークライフバランスを重視する方におすすめです。
社内SEやITコンサルなど比較的安定した職種への転向
社内SE(https://flxy.jp/media/article/481)やITコンサルタント(https://flxy.jp/media/article/25849)など比較的安定した職種への転向は、クラウドエンジニアとして培った技術力と経験を活用できるキャリアパスです。
社内SEの場合、顧客は自社内のみであるため、複数の顧客対応によるストレスが軽減されます。緊急度の高い障害も少ないため、夜間や休日の対応頻度は限定的です。ワークライフバランスを重視する方におすすめします。
ITコンサルタントは、クライアント企業のIT戦略立案や最適なクラウド導入を支援する役割を担います。技術的知見を活かしつつ上流工程に関わり、戦略立案やコミュニケーションが主な業務となるため、「技術は好きだが実装や運用の負担は避けたい」という方におすすめです。
セキュリティ系・データ分析系の職種への転身
クラウドエンジニアの知識や経験を活用してステップアップできる選択肢に、セキュリティエンジニアやデータアナリストへの転身があります。これらの職種は、需要の高まりと専門性により高水準の年収も期待できます。
セキュリティエンジニアは、セキュリティ設計や脆弱性診断、インシデント対応などが主な業務です。クラウドエンジニアがすでに持っているネットワークやインフラの知識は、セキュリティ分野でも大いに有効です。専門家が不足している分野でもあるため、今後も市場価値が大きく向上する可能性があります。
データアナリストは、データ基盤を活用してビジネス課題の解決を支援する仕事です。クラウドデータウェアハウスの知識があれば、スムーズに転向可能です。
フルスタックエンジニアとして幅広く対応できるスキルの習得
フルスタックエンジニア(https://flxy.jp/media/article/28612)へのキャリアパスもクラウドエンジニアにとって魅力的な選択肢です。フルスタックエンジニアは、フロントエンド開発からバックエンド、インフラ構築まで幅広く対応する職種です。
フルスタックエンジニアとしてのスキルを身につければ、特定の技術領域だけに依存せずさまざまなプロジェクトに対応できます。小規模なプロジェクトであれば、一気に巻き取ることもできるためフリーランスとして独立する際にも有利です。
スタートアップ企業では少人数で多くのことをこなせる人材を求める傾向にあるため、一人で完結できるスキルを持つフルスタックエンジニアは、高い報酬で迎えられる可能性もあります。ただし、相応の学習コストが求められるため継続的な学習姿勢が不可欠です。
適性を見極めるために副業から取り組んで将来的に独立を目指すのもあり
クラウドエンジニアに興味を持ったとしても、急激なキャリアチェンジはおすすめしません。まずは週1から働けるエンジニア向け副業案件でスタートし、少ないリスクで自分の適性や市場価値を確認しましょう。
現在の働き方に不満があったとしても、原因が職種ではなく労働環境にある場合も多々あります。副業でさまざまな案件や環境を経験すれば、そこから自分に合う働き方が見えてくるはずです。
週末や平日夜の数時間を使って、小規模なクラウド構築案件や技術コンサルティングなどから始めるのがおすすめです。経験を積み重ねていけば独立という選択肢も見えてくるでしょう。もしひとりで活動するのが不安な場合は、フリーランス・副業専門のエージェント・FLEXY(フレキシー)を利用ください。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込むフリーランス・副業のクラウドエンジニアとして活躍するならFLEXY(フレキシー)
本記事では「やめとけ」との声があがるクラウドエンジニアについて詳しく解説しました。「やめとけ」と言われる6つの理由や、未経験から目指すべきではない理由についてもまとめています。
それでも将来性のあるクラウドエンジニアは魅力的な職種であることは間違いありません。クラウドエンジニアの働き方を理解し、適切なキャリアパスを描ければ必ず活躍できるはずです。
もし、クラウドエンジニアの働き方に興味があるのであれば、FLEXY(フレキシー)にご相談ください。週1~2日から始める副業案件から、高額な報酬ができる案件まで幅広い提案が可能です。専任のコーディネーターがあなたの希望を引き出し、理想のマッチングに導きます。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む