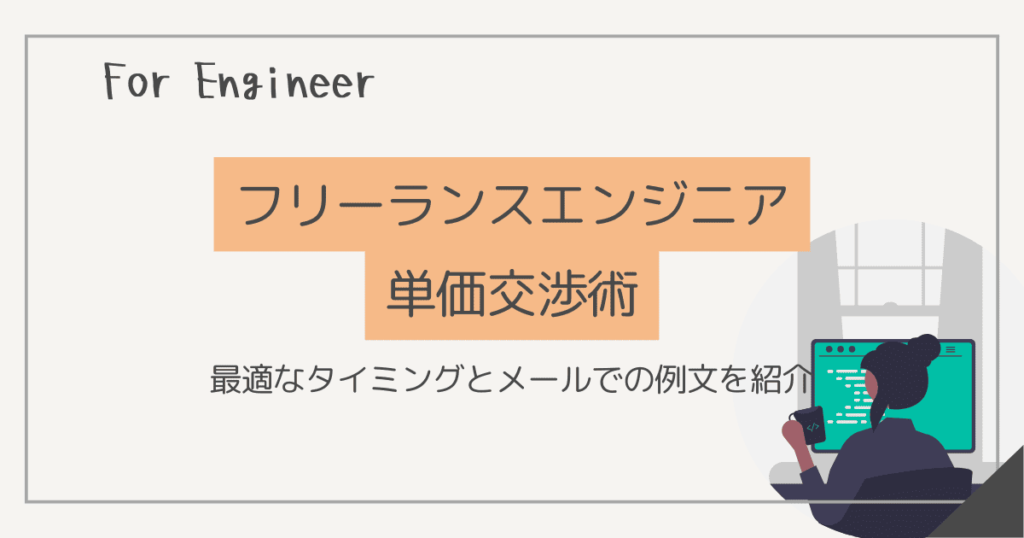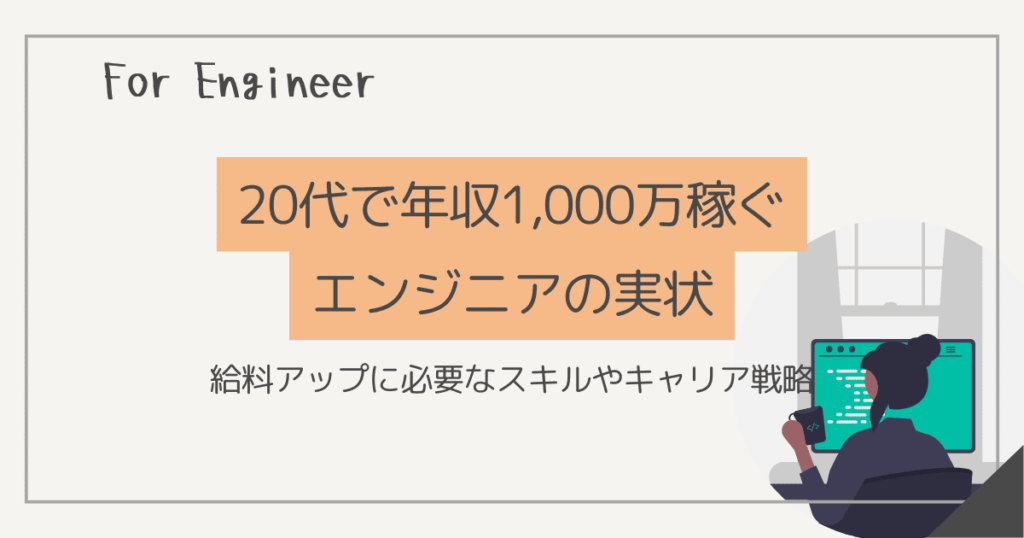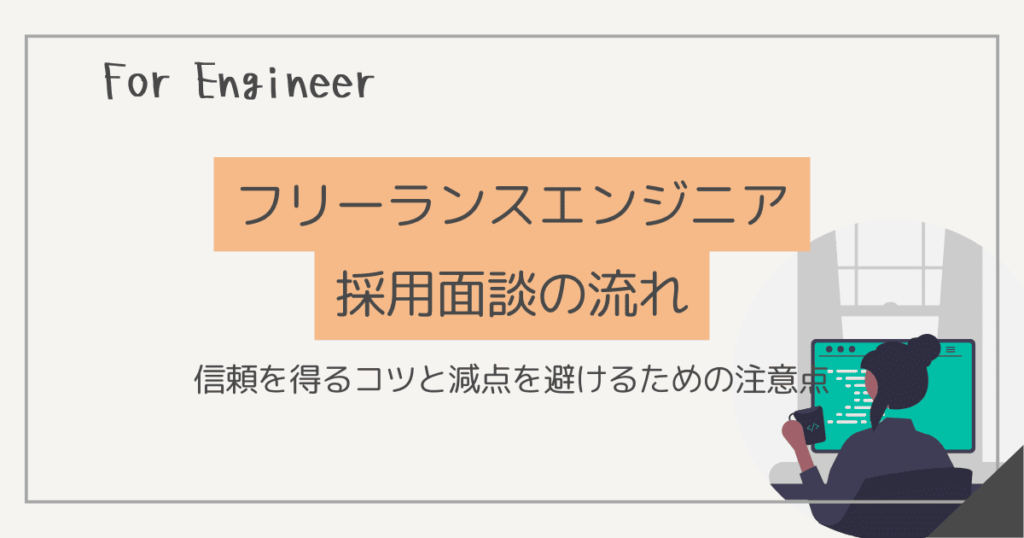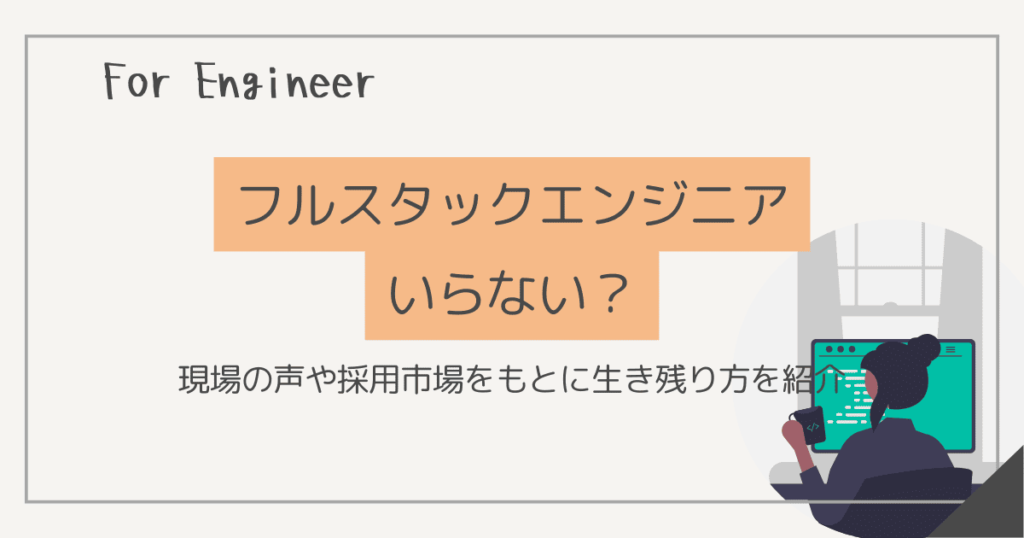GCPエンジニアが稼げるフリーランス&副業案件を多数掲載!資格のおすすめも紹介

2013年からサービスが開始された「GCP」。「Google Cloud Next in Tokyo」が東京で開催され、足を運んだエンジニアの方もいらっしゃるかもしれません。
今後、フリーランスエンジニアとして活躍するのにも「GCP」は深めておくと業務の幅が広がる技術の一つです。
そこで、ここでは「GCP」とはどのようなサービスなのか、エンジニアにとってどのような案件につながるのかをご紹介します。
FLEXYではGCP案件を多数取り扱っています。まずGCP案件を見たい方はこちらからご確認ください。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む目次
GCPとは?
「GCP(Google Cloud Platform)」とは、Googleが社内でも活用しているインフラやシステムの一部を、一般のエンジニアにも解放したクラウドコンピューティングサービスです。
例えば、Google Chromeをはじめ、MapやGmail、YouTubeなどにも活用されています。
前身としてリリースされたのが2008年の「Google App Engine」。現在でも、「GCP」の主要サービスとしてあります。その後、2011年に「BigQuery」、2012年に「Compute Engine」と少しずつサービスが拡張されていき、2013年に「GCP」に統合されました。
GCPの主なサービス内容
「GCP」の魅力は、Googleのインフラやシステムと同じものを利用できる点です。中には、データ解析や機械学習など近年注目されるものもあります。
例えば、下記が主なサービスです。
- App Engine:
アプリケーションの開発から実行、管理までをクラウド上でできる - BigQuery:
億単位のビッグデータでもわずか数分で高速処理できるデータ解析技術 - Cloud Machine Learning:
専門知識がなくともモデル構築が可能な機械学習ツール - Compute Engine:
マシンやネットワークのインフラ環境をクラウドで構築できる - Cloud Storage:
自動バックアップ機能を搭載した容量無制限のストレージサービス - Cloud Datastore:
データを自動スケーリングし、アプリケーション開発を簡素化する - Cloud IAM:
アカウントに「参照者」や「管理者」などの権限設定ができるサービス
GCPを使うメリット
GCPには、高レベルのセキュリティやAI・機械学習サービスが充実しているなどの使用するメリットがあります。ここでは、そのメリットについて詳しく解説します。
必要な機能が集約されている
前述の通り、「GCP」にはアプリケーション開発からインフラ整備、データ解析とさまざまなサービスがあります。エンジニアが求める開発環境が1つにパッケージされているわけです。
インフラ環境が安定している
インターネット事業で世界トップのGoogleが提供するサービスなだけあり、インフラ環境は強固に構築されています。開発したアプリケーションにアクセスが集中しても安心です。
高いセキュリティ基準をクリア
世界の金融機関や政府機関にも採用されている、厳しいセキュリティ基準をクリアしています。クラウドサービスはセキュリティが大きな課題ですが、その点も安心できるでしょう。
従量課金制で運用コストが低い
「GCP」では従量課金制が採用されているので、全てのサービスを使うこともできますし、必要なサービスだけチョイスして使うことも可能です。限られた予算でも十分運用できるわけです。
AI・機械学習サービスが充実
前述の通り、「GCP」はBigQueryやCloud Machine Learningなどデータ解析や機械学習のサービスが充実しています。今後、AI技術の導入を検討している方には魅力的でしょう。
G Suite製品との相性が抜群
「GCP」はGoogleが社内での製品開発にも活用していて、GmailやMeetなどG Suite製品との相性が抜群です。そのため、連携を想定した製品を開発するときには欠かせません。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込むGCP関連の主な案件内容
GCPの案件で活躍できるのはインフラエンジニアだけではありません。アプリ開発の案件もあるためアプリエンジニアも活躍することができます。ここでは、どのような案件内容があるのか解説していきます。
インフラエンジニア
「GCP」に関連するエンジニアとしてまず名前が挙がるのが「インフラエンジニア」です。ただ、案件としてはインフラ関連の業務だけを求められるのではなく、LinuxやWindowsサーバーの設計、セキュリティの構築、運用、保守など周辺のさまざまな業務も関わってきます。
アプリエンジニア
GCPのサービスのなかにはApp EngineやCloud Datastoreなどアプリケーション開発に関わるものがあるため、「アプリエンジニア」の案件も豊富です。ただ、こちらも開発だけでなく、セキュリティやSLA(業者間の品質保証規定)などさまざまな知識、経験が求められます。
GCPの代理店業務
直接何かを設計したり、開発したりはしないのですが、「GCP」関連の案件としては「代理店業務」もあります。例えば、Googleと企業との仲介や、「GCP」の知識を生かした開発支援など。「GCP」は勢いのあるサービスなので、代理店は優秀な人材を求めています。
ここではGCPの主な案件を紹介しましたが、FLEXYではGCPと同じクラウドサービスであるAWSの案件も多数取り扱っています。AWSの案件を受けることも考えている方は、AWS案件の主な内容や報酬相場もチェックしてみてください。
案件を獲得するためには
GCPの案件を獲得するためにはどのような方法があるのでしょうか。ここでは、おすすめの案件獲得方法を紹介します。また、FLEXYで取り扱っているGCPの案件も紹介しますので、参画したい案件があればFLEXYにご登録の上、案件にご応募ください。
案件を獲得するおすすめの方法
GCPの案件を獲得するにはフリーランスエージェントに登録することがおすすめです。エージェントに登録すると「希望に沿った案件の紹介」や「企業とのやりとりをサポートしてくれる」といったメリットがあります。自分の希望に合う案件がなかなか見つからない方や案件を受けるのが初めてで誰かにサポートをして欲しい方などはエージェントへの登録をご検討ください。
フリーランスエージェントであるFLEXYは、IT人材のフリーランスや副業希望の方向けに週1〜5日、100万円以上/月、フルリモート可などさまざまな案件を紹介することが可能です。登録していただくと専任のコンサルタントが希望に沿った案件を紹介できますので、エージェントに登録するか悩んでいる方は、ぜひFLEXYのサービスをご覧ください。
FLEXYで取り扱っているGCP案件
ここからは、FLEXYで取り扱っている実際の案件を紹介します。ぜひ、自分の希望に合う案件を探してみてください。
【〜90万円/月】サービスを提供する企業で自社サービスのフロントエンド開発支援
■案件概要
- 職種:フロントエンドエンジニア
- 稼働日数:週4〜5日
- 報酬:〜90万円/月
- 勤務地:六本木一丁目
- リモート:可
■業務内容
- 自社サービスの機能開発やシステム改善
■必須要件
- React.Js を用いた SPA開発経験
- Fluxベースの状態管理ライブラリ(Redux,Vuex etc..)を使用した開発経験
【〜90万円/月】バックオフィス業務に関するサービスを提供する企業でサービスのバックエンド開発支援
■案件概要
- 職種:サーバサイドエンジニア
- 稼働日数:週4〜5日
- 報酬:〜90万円/月
- 勤務地:六本木一丁目
- リモート:可
■業務内容
- 自社サービスの機能開発やシステム改善
■必須要件
- Webアプリケーションの静的型付言語を用いたバックエンド開発経験
- 静的型付言語を用いてのAWS lambda の開発経験
- AWS/GCP/Azure によるインフラの運用・構築経験
- GraphQLを使用したAPI開発経験
【〜80万円/月】DX支援を行う企業で自社サービスのフロントエンド開発支援
■案件概要
- 職種:フロントエンドエンジニア
- 稼働日数:週5日、ビジネスタイム以外の空き時間
- 報酬:〜80万円/月
- 勤務地:西新宿
- リモート:可
■業務内容
- 自社サービスのフロントエンドの開発支援
■必須要件
- WEBアプリケーション/APIの開発実務経験
- Vue.jsを使用した開発経験2年以上
- Nuxt.jsの開発経験
- Githubを使用したチーム開発経験
- クラウドプラットフォーム(AWS, GCPなど)でのdocker経験
- 保守性を意識したコーディングスキル
【〜80万円/月】ブロックチェーン基盤のサーバサイド開発支援
■案件概要
- 職種:サーバサイドエンジニア
- 稼働日数:週2〜5日
- 報酬:〜80万円/月
- 勤務地:小川町
- リモート:可
■業務内容
- ゲーム開発におけるブロックチェーン基盤の要件定義、設計、開発、運用
- ブロックチェーン関連処理のシステム実装
- ブロックチェーンゲーム内でブロックチェーンと深く関わりのあるアウトゲーム部分のサーバサイド機能の要件定義、設計、開発
- ブロックチェーンの運用に必要な情報ツール・バックオフィスツールの要件定義、設計、開発、構築、運用サポート
- ゲーム開発チームとの機能要件に関する伝達、交渉
- 各システムの対外マニュアル等、共有ドキュメントの作成
- 上記のシステムを実行するためのクラウドサービスを使ったインフラの構築
■必須要件
- AWS/GCPを活用したシステムアーキテクチャ設計経験
- 大規模サービスの負荷を考慮したバックエンドの設計・開発・運用スキル
- 英語の情報源からキャッチアップできること
【〜80万円/月】Web3ゲームのフルスタック開発支援
■案件概要
- 稼働日数:週2〜5日
- 報酬:〜80万円/月
- 勤務地:小川町
- リモート:可
■業務内容
- Web3ゲーム新規開発、運用における企画仕様全般の取り仕切り、パラメーター設計のディレクション
- 企画、クリエイティブとの連携
- Web3ゲームのバックエンド及びWebクライアントの実装
- システム要件定義・設計
- サーバーインフラとしてのゲームクラウドの検証・導入
- システムサイドから見た企画の実現性、開発工数、企画への改善案提案
- 運用の負荷軽減に対する効率化、およびアップデートの作業軽減における効率化
- 開発環境やワークフローの構築・改善
- 開発技術のスキルアップ、ノウハウ共有
■必須要件
- フロントエンド~バックエンドまで幅広い知識/経験を有している方
- AWS/GCPを活用したシステムアーキテクチャ設計経験
- JavaScript(React.js, Next.js, Vue.js, Nuxt.js)を用いたWebサイト開発の実務経験
- PHP/Laravelを用いた、大規模サービスの負荷を考慮したバックエンドの設計・開発・運用スキル
- ゲーム開発経験、特にバックエンドの実務経験
【〜80万円/月】物流業界のDXに挑む企業でAPIプラットフォーム基盤構築支援
■案件概要
- 職種:サーバサイドエンジニア
- 稼働日数:週3〜5日
- 報酬:〜80万円/月
- 勤務地:内幸町
- リモート:可
■業務内容
- MuleSoftを用いた環境構築、運用設計
- APIテスト(Gatlingのようなツールを用いたテスト)
■必須要件
- AWS、GCP、Herokuなどのクラウド環境構築経験者、運用設計、手順書作成経験
- GUIのテストではなく、APIテスト(Gatlingのようなツールを用いたテスト)経験者
- ウォーターフォールでのシステム開発と基幹システムとのデータ連携の設計・開発経験
【〜80万円/月】コンテンツビジネス特化型ID発行プロダクトを開発する企業でフロントエンド開発支援
■案件概要
- 職種:フロントエンドエンジニア
- 稼働日数:週5日
- 報酬:〜80万円/月
- 勤務地:護国寺
- リモート:可
■業務内容
- コンテンツビジネス特化型ID発行プロダクトのフロントエンド開発
■必須要件
- Reactでの開発経験2年以上
- AWSもしくはGCP環境でのフロントエンド開発経験
【〜80万円/月】採用マッチングアプリを開発する企業でアプリ開発支援
■案件概要
- 職種:iOSエンジニア、Androidエンジニア
- 稼働日数:週3〜5日
- 報酬:〜80万円/月
- 勤務地:赤坂
- リモート:可
■業務内容
- 採用マッチングアプリの開発
■必須要件
- 新規サービスの立ち上げに関する強い興味や関心
- Flutter開発経験
- iOS/Androidの基礎的な知識
- iOS/Androidのストア対応経験
- GitHub等を使ったチームでの開発経験
- クラウド環境(GCP/AWS)の実務経験
- フロントからDB設計(RDB/NoSQL/NewSQL)まで携わったことのある開発経験
- CI/CDを含むDevOpsの改善や構築経験
- リスト型アタックやスプレー攻撃など、セキュリティの一般的な知識とセキュアな実装経験
【〜80万円/月】個人事業主向けのサービス販売プラットフォームを提供する企業でプロダクト開発支援
■案件概要
- 職種:サーバサイドエンジニア、フロントエンドエンジニア
- 稼働日数:週4〜5日
- 報酬:〜80万円/月
- 勤務地:渋谷
- リモート:可
■業務内容
- プロダクトのフロントエンドまたはサーバーサイドの機能実装や企画
- テックリードを支える開発メンバー
■必須要件
- TypeScriptを用いたWebフロントエンド開発経験
- AWS/GCPなどクラウド環境での開発経験
- 自社サービスの開発経験
【〜64万円/月】医療現場でのIT活用を目指す企業でデータエンジニア支援
■案件概要
- 職種:フロントエンドエンジニア
- 稼働日数:週5日
- 報酬:〜64万円/月
- 勤務地:護国寺
- リモート:可
■業務内容
- BigQuery内でデータレイク、データウェアハウス、データマートの構築や各種DBからのデータパイプライン構築
■必須要件
- BigQueryを利用したデータ分析基盤の運用経験
- dbtの実務経験
- データウェアハウスにおけるデータモデリングのご知見
- コミュニケーションが円滑であること
- 年齢、学歴、経験業界、居住地問わない
GCPのスキルだけで案件獲得は難しいのが現状
App EngineやCloud Machine Learningなどのサービスを見ると分かるように、「GCP」はあくまで開発環境を提供しています。つまり、これだけで完結するわけではないのです。
例えば、アプリケーション開発にはC言語やC++、Java、Objective-Cなど、インフラ設計にはBashやTTL、BAT、Perl、Pythonなど、それぞれ開発に適した言語知識が必要です。
「GCP」だけでは案件の獲得は難しいので、アプリケーション開発やインフラ設計など周辺の知識、技術も身に付けて、周りのエンジニアとの差別化を図ることをおすすめします。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む案件獲得におすすめのGCP資格
もちろん、前述した「代理店業務」のように「GCP」の知識だけで勝負できる案件もあります。ただ、そこでは相当な知識が求められるので、関連資格を取得しておくのがいいでしょう。「GCP」に関連する資格としてはGoogleが提供する「Google Cloud認定試験」があります。難易度は「User certification」「Associate」「Professional」の大きく3つです
- User certification:
Google Workspaceの活用スキルがあるのかが問われる - Associate:
クラウドソリューション環境の設計や構築、運用のスキルが問われる - Professional:
アプリケーション開発やデータ処理、機械学習モデルの設計などに関する全8種類の試験が提供されており、試験ごとに対応するスキルの知識や技術が問われる
最初は難易度の低い「User certification」と「Associate」から挑戦するのがいいですが、フリーランスのエンジニアとして勝負するのなら「Professional」の資格をチェックしましょう。
「Google Cloud認定試験」は秋葉原や池袋など各地のテストセンターで受験できるほか、申込時に「遠隔監視オンライン試験」を選択すると、自宅や会社からでも受験できます。なお、資格の有効期限は2年間。期限前には通知が届くので、忘れず再受験しましょう。
まとめ
「GCP」はこれからさらに伸びることが期待されるサービスで、関連する案件は増えてくると考えられます。少なくともGoogleがすぐにサービスを停止させるとは考えにくく、すでにエンジニアで活躍されている方も、これからエンジニアを目指される方も狙い目です。
ただ、「GCP」の案件を自分だけの力で獲得するのは難しいので、フリーランスエージェントのFLEXYに登録し、専任のコンサルタントから案件紹介を受けることをおすすめします。