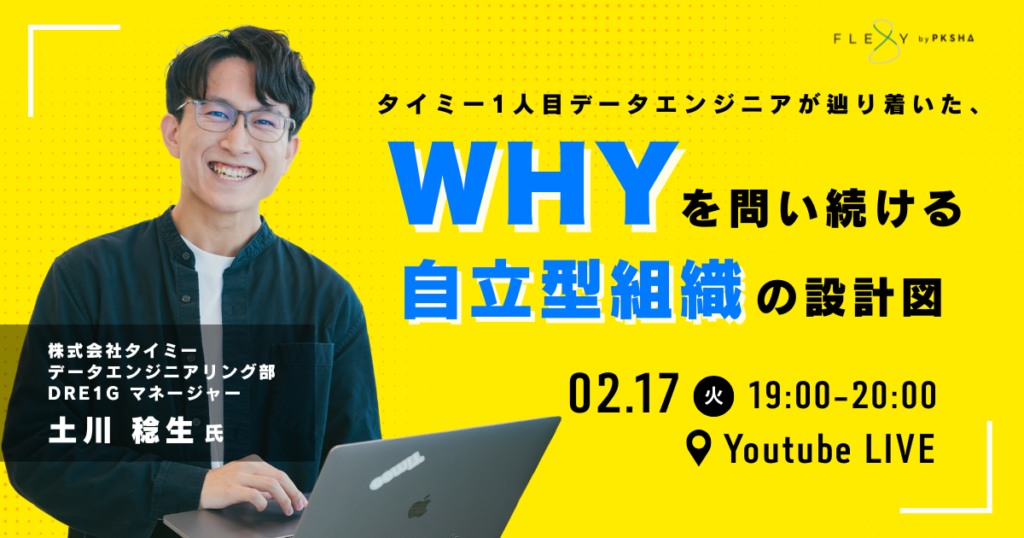CTO/Ex-CTO(技術顧問)とは?CTO/Ex-CTOが抱える悩みとキャリア・働き方について

※本記事は2016年4月に公開された内容です。
2016年3月17日(木)、目黒にある株式会社Viibarのオフィスにて、FLEXY関連イベントとして、CTOやその先にある生き方としてのEx-CTOをテーマとした「Ex-CTO meetup」が開催されました。
今回は第1回ということで、CTO/Ex-CTOとは何なのか?どう関わればいいのか? にフォーカスを当て、4名のCTO経験者にご登壇頂き、エピソードを交えながら赤裸々に語って頂きました。
目次
登壇者
パネラー
橋本 善久(はしもと よしひさ)氏
リブセント・イノベーションズ 代表取締役、ライフイズテック株式会社 取締役CTO
堀内 康弘(ほりうち やすひろ)氏
モビンギ株式会社 co-founder、株式会社LiB 社外取締役
是澤 太志(これさわ ふとし)氏
株式会社Speeeエンジニアマネジメント責任者 兼 エンジニア採用責任者
モデレータ
田邊 賢司(たなべ けんじ)氏
株式会社wizpra CTO、株式会社サーキュレーション 技術顧問
CTOとは、企業としてトータルソリューションを提供するための組織内ブリッジ
田邊 賢司氏(以下、田邊):さて、早速ですが、CTOになるためにはどうすればいいんでしょうか?
橋本 善久氏(以下、橋本):ちなみに今CTOとか、それに近い仕事をしている方、どれくらいいらっしゃるか挙手頂いてよろしいでしょうか?
(参加者の半数以上が手を挙げる) おお、、かなりいますね!
CTOになるため…みなさんもそうだと思うんですけど、目指してなった人はあまりいないんじゃないかなと思うんですけど。こういう人には託したいなっていう意味でいうと、技術をちゃんとわかっているのは当然だとしても、たぶん会社全体の視点をちゃんと持っていて、特にスタートアップに置いては、ビジネスそのものを成長させれられるかどうかというのが重要だと思っていて。
僕も今Life is TechのCTOやっていますけど、PLも見てますし、資本施策に対しても意見をいうし、申込フォームの話もするし、契約書の内容もチェックします。プロダクトのオーナーとしてサービス設計やUI/UX設計もします。ちなみにさっきキャラクターが出てきたと思うんですけど、あれ実は僕がキャラクターデザインのディレクションをしたりとか、一部は自分で描いたりしてるんです。何屋さんかよくわからない状態です、正直(笑) 。
ただ「T」の部分は維持しつつ、あと足りない部分は積極的に竹内さん(Life is Techの留学CTO)とかエキスパートに協力していただくことを含めて、とにかくトータルのソリューションをどう提供するかっていうか、何でも屋になる覚悟がある人がいいなぁというのが、資質としてはやっぱりそういう人に託したいなぁという風に思いますね。
田邊:他の方はどうですか? プラスして、こういうのがあったらいいんじゃないかというものとか。ベースの技術やスキルはどこまであればいいのか等、あればお願いします。
是澤 太志氏(以下、是澤):僕は最近、なにか圧倒的な強みがあればいいのかなという風に思っています。それはどういう分野でもいいんですけど、強みが圧倒的であるというところで、誰から見てもすげぇみたいなことを言われているっていう人。やっぱりすごいやつじゃないと一緒にやりたくないと思っている現場の人たちはいると思うので。だからCTOってその会社の一番凄いっていわれてるエンジニアがやればいいんじゃないかなと思い始めたりしてます。
あと経営者と対等に話ができる人で、それが苦にならない人。経営者のいうことを聞くだけじゃなくて、「いやそうじゃないですよ…」と、経営者に対して論理的に説明できる能力。CTOが感情的になってしまったら、組織は崩壊してしまうし、エンジニアの成長にもならないですし、そこをちゃんとブリッジしてあげることは重要だと思います。
僕の場合はそういう重要性に気づいたとき、ロジカルシンキングとか、クリティカルシンキングのセミナーに参加したりしてました。あとは学習によるインプットを重要視して、ドラッカーも読みましたし、ファイナンスについてもある程度勉強しましたし、経営者の知っている知識を自分のなかに引き入れるってところをやったりもしました。そしてアウトプットとしては実績を出すことも当然ですが、事業や開発を通じて戦友をつくることができる、そういった理解してくれる人たちを増やしていける人がCTOに向いているのかなぁと思っています。
堀内 康弘氏(以下、堀内):経営者と対等に話せて、仲良くできて、同じ方向性を向けるっていうそういう人じゃないと厳しいかもしれませんね。
是澤:はい、それで合わなかったら去るみたいな感じの方がいいのかなって(笑)。
堀内:僕はそんなに技術力なかったんですけど、国光さんと普通に話ができたので、それがうまくいったというのがあると思います。プログラムがすごい書けるっていうと、なんですかねセルフィッシュじゃないですけど、 プログラム書けるだけじゃなくて、当たり障りのない言葉で言うとコミュニケーション能力が大事だと思いますね。
是澤:たしかにですね。僕は経営者に対してホスピタリティーと傾聴力が大事っていうのを最近言ってます。相手の状況や立場を理解し、意見や話してることは最後まで黙って聴くことが出来る人じゃないとなかなかしんどいなぁと思いますね。パートナーとしての対等感がないと。
田邊:実際に代表の方とか経営メンバーの方とコミュニケーションを円滑にするために工夫していたこと等あればお願いします。
是澤:僕は、飲みに行きますね。誘われたら断らない(笑)。過去に所属していた会社のお酒の好きな経営者からは 辞めてから誘われたりもしてますし、未だに関係が続いているのはありがたいと思います。
Speeeでは社長と早朝のカフェで定例MTGをしていたり、直属の役員ともコミュニケーションの機会が多いですし、普段からラフに接する場があるというのはいいことだと思っています。たまに飲みにも誘ってサシ飲みとかも(笑)。
橋本:CTOは経営メンバーの一人であるべきだと思いますが、場合によっては代表や他の経営メンバーが最初右だと思っていなくても、右だ右だとしつこくいろいろな表現で伝えていくことで、経営メンバーもやっぱり右がいいな・・・とか最初から右が良いと考えていたように思い始める事もあります。強引に進めるのではなくて、腑に落ちて心から理解してもらっている状態にいかに持ち込むかは重要だと思います。
田邊:巻き込み力を発揮して、周りを含めて同じ方向にみんなを向かせることが大事っていうことですよね。
橋本:そうですね、はい。

約50人の参加者のうち、半数以上はCTO経験者。中には、登壇者橋本さんのLife is Techへ留学CTOとして関わっている竹内さんの姿も
“1割”の時間で十分。技術顧問として他社に関わる/関わってもらうことで劇的な効果が。
田邊:次にCTOのその先というところで、技術顧問になるためにはみたいなところで言ったら、どうしたらいいと思われますか?
是澤:僕の場合は一例としてTimeTicketを買ってくれた人から話しているうちに、技術顧問になってほしいと依頼されたことがあります。そういったサービスでいろんな人と会ってみると、 技術や開発組織に困って助けて欲しい人は思ったより多いという印象。
なので、さっきのホスピタリティーの話じゃないですけども、親身になって話を聞き、人と接して課題解決していくと自然とそういう話が舞い込んでくるって感じですかね。
橋本:個人的に言えば技術顧問やアドバイザーを受ける時って、それ自体がいい経験にもなるし、もちろんお相手の役に立つことが第一だとしても、何かが学びになるなとか、将来いろいろシナジーとかコラボのきっかけになるかとかそういうことも考えてやってます。
逆に竹内さんに手伝ってもらってる時、竹内さんに対して、対価はもちろんですが、それに加えて経験とか面白さとか含めてお返しできないかなとかすごい意識していますね。
堀内:僕の場合はアマゾン辞めた後に、転職ヘッドハンターの人から、CTOを探していると。もともとCTOをやっていた経験があったので行くんですけど、そんな働きたくないんですよ、という話をしていると、フルコミットじゃない技術顧問っていう形になったパターンと、あとは例えば、投資に興味があってVCの人に会いに行って、話してみたら、そのあとVC人から投資しているこの会社でエンジニアが足りなくてちょっとエンジニアの相談に乗って欲しいという流れから技術顧問になったというパターンもありました。技術顧問になる方法としてはVCの人は投資先でエンジニアが足りてない会社をいっぱい知っていると思うので、そこを手伝ってくれという依頼は結構くるんじゃないかなと思います。
橋本:僕がそういう意味で一個強く提案したいのが留学CTOや留学エンジニアですね。
現役エンジニアを対象とするので、所属会社の度量は必要なんですけど、その会社さんにもメリットは絶対あるはずなんですよね。サービスの初期構築時は良いのですが、運用フェイズに入るとなかなか新しい経験が出来にくくなる。他のスタートアップでサービスの新規立ち上げがある場合、特にちょっとジャンルが異なる場合なんかはとても良い経験になる。その経験はきっと所属する会社に還元できる。そして留学に来てもらう側の会社は当然助かる。Win-Winの関係が築ける可能性は高いです。まぁ会社間の信頼関係はすごい重要ですけど、留学CTOや留学エンジニアが、もっと日本中で流行るといいなと思います。
しかも1割ってすごい重要で、たったの1割の時間を活用するだけでめちゃくちゃ劇的な効果が出る、逆に言うと技術顧問ってそういう役割ですよね、5%とか月に数時間でも劇的な効果が出るという存在なので、それを現役の人たちもどんどんやると結構いろんなスタートアップに限らず、活性化していくと思うので、そういうのみんなやればいいのにと思います。
企業フェーズが進むにつれ、徐々に「人」に関する役割が増加
田邊:次に、CTOや技術顧問はどこに強みや責任をもつべきかについてお願いいたします。堀内さんいかがでしょうか?
堀内:僕は小さいスタートアップから大きくなっていくまでの経験しかないですけど、その中で役割がどんどん変わっていったなっていうのが自分の経験ですね。
エンジニアが数人って時は当然コーディングをしてましたし、規模が大きくなってくると採用とか、組織のマネジメントの方に時間を割くようになっていきましたね。意識しているところっていうのが、最終的に経営陣とか社長とエンジニアの間に入って、エンジニア側が楽しくやりがいを持って働けるようにする試みをしていましたね。
田邊:結構皆さん、ビジネスサイド含めなんでもやるとおっしゃっていましたが、そうすると組織体系にもよると思いますが、役割や責任が曖昧になってくると思います。実際に技術は当たり前のこととして、責任をどの範囲までもって、他のことをどのようにやっていたのかなというとどうですか?
橋本:僕の場合は、仲間の尻尾を踏まないことは強めに意識しています。勝手に動いてそれぞれの担当領域を踏み荒らす事は絶対にしない。自分も尻尾を踏まれる事は避けたいですし。それぞれがそれぞれの領域を尊重して協調して動く事は大切ですよね。
その上で、なにかしらボールが落ちていたり、方向が違うのではないかと思えば、その担当者と話し合うことは積極的に行います。そして責任の範囲の認識はそれぞれで完全に一致するわけではないので、時には重なり、時には隙間ができる。そのギャップがどこにあるのかもいつも見つめるようにしています。
是澤:やっぱりカオスな状況ってどうしても生まれてしまうので、正しい情報収集だったり、正しい情報ってなんだっけみたいなところを意識してやってます。それはプロダクトについてもそうですけど、僕がやっているのは主に人周りのところですかね。
CTO的役割を担う人が責任をどこで持つべきかっていうことでいうと、経営者に対しても、経営に対しても責任を持つべきだと思いますし、組織に対してももつべきだと思います。そしてエンジニア一人一人のキャリアに対しても責任を持たないといけないなと感じているところですね。

緩やかな雰囲気の中、終始笑顔の絶えないディスカッション。
役割に限界を設けず、他のCXOとシンクロ、役割分担することが重要
田邊:ありがとうございます。それでは次の質問に行きたいと思います。
CTOの役割やその限界、そもそも限界があるのかないのかとか、そういうものを含めてお話しお願いいたします。
橋本:多分、役割って一番難しいですよね。CTOの役割って。技術のみをやるのも立派なCTOでしょうし、ものすごいギークな人でガンガン引っ張るのも最高のCTOの一つだと思いますし、逆にコーディングは一切しなくてもチームを引っ張って他のこともやっているのもCTOでしょうし、 会社のフェーズとか、組み合わせですよね。
他のCの人たちやチームメンバーのスキルセットやモチベーションなどを踏まえた相対的なもので決まると思うので、それ抜きにCTOの定義はしきれないんじゃないのかなって。そこを柔軟に足りないところを埋められるっていうのが必要な役割だと思うのと、 あと限界っていうのが、本質的には多分ないと思ってるんですけど、絶対に重要なのが経営者とのシンクロで、もしCTOでやるならば、CEOとCOOとのシンクロナイズがとても大事なのかなと思います。
そこができてれば結局、自分が思っている事と会社が思っていることがイコールになるので限界はない。それがシンクロできないんだったらそれが限界点になるのかなと思います。
是澤:すごいわかります。やっぱり自分の強みっていうのと会社のフェーズの掛け合わせだなっていう風に思っていて、どちらかというとCTOっていろんなことをやらされるって役割になっている。
CTOって”ITにおいてインターネットのこと一番わかっているのこいつだよね”みたいなところがあってシス管的なところとかやることも多いですし。小さなベンチャーだったらプリンタとか電話の設定とかも普通にしますし。組織が大きくなっていくと、そこをいかに専門性で役割分担していくのかを意識して、仕組みをつくって権限委譲し、クオリティをあげ限界を切り開いていくイメージですかね。本当に先ほど橋本さんがおっしゃった通り限界はないと思うので、限界突破しまくってCTOの抱えてる役割が5分割ぐらいされてるみたいな世界が今後ありそうかな、と(笑)。
田邊:先ほどの話でもありましたが、CTOのポジションになって、会社の中でメインとする技術部分以外に、法務だったりやらなきゃいけないことはたくさんあると思うんですけども、技術以外の部分で自らがやるやらないの判断はどのようにされてますか?
橋本:僕の場合は単に会社の全体視点で見たときに、他にやれそうな人がいればやってよってなりますし、少なくとも落ちてるボール全部拾って、誰かにわたすか、受け取れないんだったらもう自分がやると、自分がやれそうなら。シンプルにそれだけですね。全体の視点で。
もう一個は今やってもしょうがないボールはあえてほったらかしとくとか、逆に拾おうとしている人を止めたりとか、そういう感じですかね。みんなで拾えそうな人が適切なタイミングで拾うようにしていくって感じですかね。
是澤:橋本さんと全く一緒ですね。僕自身マイノリティーな事が好きっていうのはあるのかなぁと思うんですけど(笑)。
マイノリティーな仕事を見つけたらそこに対して「自分がやっちゃいます!」とかいって、そこにモチベーション感じて積極的に取り組む人がいたらどんどんチャレンジさせればいいんじゃないですかね。失敗は許容するけど大失敗させないようにフォローする、そうやって成長の手助けをしてあげるべきかなと。
技術顧問は、稼働時間ではなく「じぶんごと」としてコミットする姿勢が重要
田邊:技術顧問をしている、もしくは依頼しているというところで、実際にどういう方が入っていて、どんなことをやってもらっているのかでいうとどうでしょうか?
堀内:僕が技術顧問っていう名前で何をやっていたかでいうと、関わる会社の規模にもよると思うんですが、スタートアップを立ち上げた当初の数名の会社とか、エンジニアがいない会社とか、それぐらいの会社が多くてですね。そういうところでは採用面接をしてくれとか、あとはもう手は動かさずに、採用するときにどういうことを気にしていましたかっていう過去の経験からアドバイスをしたり、ということをやってましたね。
田邊:橋本さんの場合はいかかがでしょうか?
橋本:種類がいろいろあって、やってる相手によって全部変えてるんですけど、場合によってはプロジェクトの工数管理表とかを見て、足りないパートを指摘したり、ゲーム屋をやっていたので、グラフィックスのこと全くわからないって会社さんがあったときに、”いろは”からポリゴンとは、とかそういう講座をするところから始まることもあれば、マネジメントの話をしたりとか、相手によってできることを提供できそうだったらやりますよって感じですかね。
逆に依頼するときってのは自分たちに不足しているのは何かってのを認識した上で、足りないところを相談しながら決めていくというか、あと人として信頼できるかどうか、そのプロダクトやサービスを自分ごととして思ってやってくれるかどうかは大切ですね。
結構、他人事で関わられてしまうとお互い不幸なので、ちゃんとそのプロダクトやビジョンに共感してやってくれる人にはお願いしたいという感じですね。
是澤:僕自身は顧問は経営者のメンターの側面が強いなと思うようになりました。要は壁打ち相手ですよね。例えばエンジニアやデザイナーとのやり取りをみてフィードバックしたり、この本読んでくださいって本渡したりもしますし。
他にはマーケティング用にデータが欲しいといわれてクロールしてデータ集めたりとかも。自作のクローラーフレームワークがあって、さくっとできちゃうので(笑)。あとは週末にRubyでコード書いてコミットしてたりと開発の手伝いをすることもあります。
田邊:技術顧問を依頼する方では、どういう人に入ってもらっていて、どんなことをやってもらっていますか?
是澤:Speeeでは元クックパッド技術部長の井原さんに開発部顧問で入ってもらっています。井原さんにはうちのエンジニアの組織にかなり深く関わってもらっていて、経営陣とも蜜にコミュニケーションをとってもらっていて、技術戦略の根幹までアドバイスしてもらっています。採用では面接にも出てもらっています。やっぱり多くの経験を積まれてきていて、僕らが持っていない圧倒的な強みを持った方なので、もう限界まで協力してください!みたいな感じでがっつり入ってもらってます。僕としては本当にうちのCTOになって欲しいなぐらいの感じですけど(笑)
エンジニアは井原さんをリスペクトしてますし、エンジニア以外の社員も井原さんのことを好きって方はすごく多いですね。 顧問で入っていただいて、憧れの存在としてリスペクトが生まれているのはいい傾向だなと思います。
技術顧問で入っていただいているMatzさんにしてもそうなんですけど、オフィスに来て勉強会で話してくれて、若いエンジニアにMatzさん自身のご経験や思想・考え方を伝えてくれるっていうのは、視点や視座があがってすごいありがたいですね。普通だと言語を生み出して世界的に活躍してる凄い経験の方の話をきけて、コミュニケーションをとれる機会はお金を払ってでも経験できないと思うので。

Viibar社の雰囲気のいいオフィスで、リラックスした空気が流れる。
経営層も現場も、きちんと巻き込んでいける体制を築けるかが、技術顧問活用の肝
田邊:次の質問なんですが、技術顧問とどう関わっていくべきかとか、もっとこうしたほうがいいとか、今はこうしてるけどこうしたいとかありますか?
是澤:顧問の方に対して、経営陣ががっつり関わってもらっているのはありがたく、やっぱりそれは大事かなと。経営陣の考えをちゃんと伝えてるからこそ、顧問の方が理解した上で関わってくれて結果が出てるというのがあります。だから経営陣はまず関わらなきゃいけないなってところですね。そしてもちろん、現場のエンジニアにも関わってもらわなければいけない。そこに対して顧問の方にも時間を割いてもらうことが重要だと思います。
そうやってお互いの理解を踏まえたうえで方針を決め、一旦誰かの基準に合わせるということをしなければいけない。じゃあそのとき誰の基準の合わせるのかっていうと、一番すごいやつの基準に合わせるべきで、それが顧問の方の基準にあわせた方がよい成果はでますよね。うちでいうと井原さんの基準を経営陣や僕達エンジニア陣が理解するのがより大きな成果を出すために大事でした。
田邊:では割と是澤さんとだけ話すのではなくて、他の経営メンバーも入れて、関わるというかんじなんですか?
是澤:そうですね。経営陣が井原さんとコミュニケーションを蜜にしてくれているので、僕はどちらかというとその流れで出てきたものを戦略・戦術として描き、活かしていくことを重要に思って動いています。Speeeを理解し、文化を知り、エンジニアリングを知り、Speeeで働いているみんなの為になることをやるのが僕の役割だと思っているので、違和感を感じたら逆に意見を言ったりもします。僕は顧問の方が組織に対して成果をだせるように推進するところに対して一番気を払っているって役割ですかね。
田邊:他には何か技術顧問との関わり方で注意すべき点などはありますか?
橋本:アドバイスする側からの視点としては、「アドバイザーにお腹を見せる」というのは大切だと思います。なにかしら課題や相談事があるから呼ばれているわけなので、そこで情報を変に整えて伝えようとかしない方がいい。アドバイザーや顧問にはあるがままを触れさせる方がいいです。ありがちなのは「まだ準備が出来てないので、会議を延期してもらっていいですか?」というパターン。準備とか途中でいいから、あるがままで触れ合う。
そして、他に重要なのは「アドバイスされたことをちゃんと咀嚼して実行する」ことです。これが実はクライアント側にとってもアドバイザー側にとっても結構難易度が高い。基本組織の課題って生活習慣病みたいなもので、そのチームにしかない特殊な何かというよりは、どこにでもある基礎的な事がやれていない事の方が多い。でも例えば太っている人がいたとして「食事はほどほどに」「運動しましょう」という当然の事が必要ですから、それをアドバイスしたとしても、しみついた習慣ですから簡単には直せない。それをあの手この手で導いて痩せてもらうような難しさがアドバイザーや顧問にはあるのかなと思います。
アドバイザーや顧問を頼む際は頼む側の強い覚悟も必要なのではないかなと思います。「ライザップに行くぞ!」って時はかなり気合入れないとできないと思うんです。でも「技術顧問を呼べばどうにかなるんじゃないか」とか淡い期待だけが先行すると多分うまく行かないのではないかと思います。
堀内:技術顧問ってその人が持っている経験とかスキルとかを決められた時間でお金払って素早く手に入れるっていうそういう側面があると思うんですね。なのでCTOやってて経験ありそうだからちょっと相談乗ってくださいよ、それが目的を明確にするとお互いにハッピーになれるんじゃないかていうか。
例えばCTOの人が悩んでいるので壁打ちして欲しいんですよねっていうのも一つの目的で、そういう目的をはっきりするといいかなと思いますね。
田邊:顧問側からも打ち合わせ時にアジェンダを出していくのも大事なのかもしれませんが、そこはどうでしょうか?
堀内:でも顧問側からだと出したものが会社の求めているものと違っていく場合もあるので、もっと会社側からピンポイントでアドバイスください、みたいな感じだといいんじゃないかなと思います。逆に言うと必要ないなと思ったら、もういいんでと優しく言ってもらえるといいと思いますね。
是澤:気軽に相談できるっていうのは大事だと思います。slackとかchatworkとかで、いつでもだれでも話しかけられる状況を作っていくであったり、空き時間にいかに関わるかっていうのは顧問として大事かなぁっていう風に思ってますね。
田邊:皆さん、貴重なお話ありがとうございました。
まとめ
CTO/Ex-CTOとは何なのか?どう関わればいいのか?にフォーカスを当て、4名のCTO経験者にご登壇頂き、エピソードを交えながら赤裸々に語って頂きました。
役割に限界を設けずに他のCxOと連携をして、経営層や現場を巻き込んでいける体制をつくることが重要そうですね。