Devinで変わるエンジニアの業務内容と評価軸|他のAIとの違いや今すぐ使うべき理由も解説
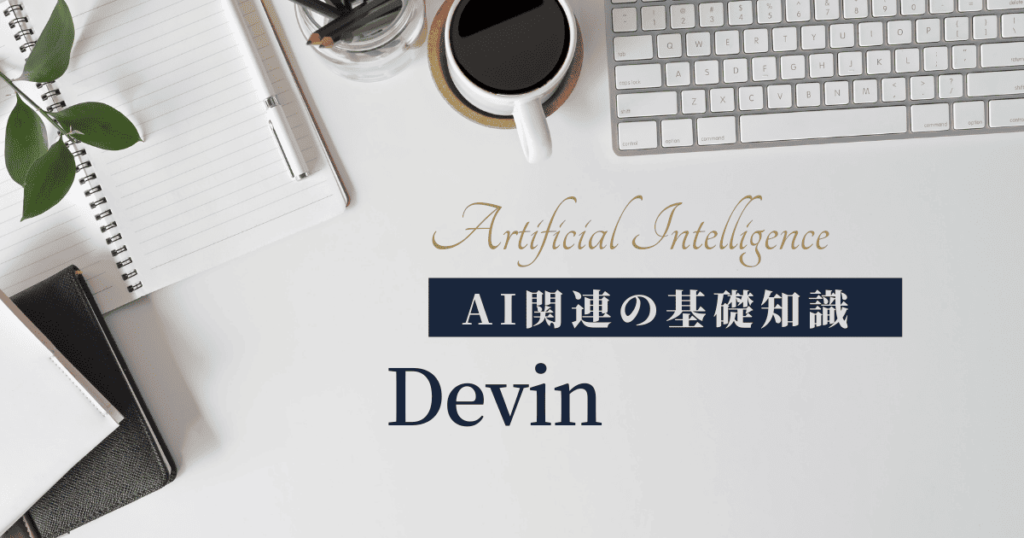
近年、生成AIの進化は目覚ましく、開発現場でも業務効率化の切り札として注目を集めています。
中でも注目されているのが、Cognition社が開発したDevin(デヴィン)です。単なるコード補助ツールではなく、開発タスク全体を自律的にこなす「自律型AIエンジニア」として、従来の開発スタイルに大きな変革をもたらす存在となっています。
本記事では、Devinの特徴や他のAIとの違い、導入時の注意点、エンジニアが身につけるべきスキルについて詳しく解説します。Devinを理解し活用できることで、開発現場での価値が高まり、高単価の案件にも挑戦しやすくなるでしょう。
FLEXY(フレキシー)では、こうした先進的なツールを活用できるエンジニア向けの週4~5稼働案件を数多くご紹介います。少しでも気になった方はぜひご活用ください。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む目次
DevinとはCognition社が開発した「自律型AIエンジニア」
Devinは、Cognition社によって開発された自律型のAIエンジニアです。従来のAIツールとは異なり、単なるコード補助ではなく、プロジェクトの目的達成に向けて自ら判断し行動する点が大きな特徴です。
コーディングからテスト、バグ修正、デプロイに至るまでの一連の開発工程を自動でこなす能力を持っており、「指示を受けて動くAI」から「自走するAI」へと進化を遂げた存在といえるでしょう。
SlackやGitHubなどの実務環境にも対応しており、実際の開発チームに組み込んで活用することが可能です。こうしたDevinの導入は、エンジニアの業務効率を大幅に向上させ、上流工程にも活かしていけます。
Devinの主な機能
Devinの強みは、ソフトウェア開発の多くの工程を一貫して実行できる点です。具体的には、コーディングや単体テストの自動生成、既存コードのリファクタリング、発生したバグの特定と修正、CI/CDによるデプロイ作業まで対応可能です。
さらに、ブラウザを操作して外部情報を収集したり、SlackやGitHub、Jiraなどのツールと連携してチームのタスク管理をこなしたりと、従来エンジニアが手作業で行っていた作業を幅広くカバーします。
エンジニアは人間にしかできない判断や調整といった上流工程に集中でき、プロジェクト全体の生産性を向上させられるでしょう。
生成AIとの違い
Devinは、ChatGPTやGitHub Copilotといった従来の生成AIと根本的に異なります。これらのツールが「開発者の補助役」であるのに対し、Devinは「開発タスクを自ら遂行する実行者」として設計されています。
例えば、Copilotはコードの提案や補完を行いますが、Devinは目的を与えるだけで、作業の計画立案からコードの作成、テスト、問題解決、デプロイまでを一気通貫で行うのが特徴です。
また、外部ツールやウェブブラウザの操作も含まれており、実際のエンジニアが日常で行う作業を模倣しながら進めていきます。つまり、Devinはタスクベースで動く「自律的なチームメンバー」として位置づけられる存在です。この自律性により、プロジェクトの初期設定や実行時の負荷を大きく軽減できます。
エンジニアが業務でDevinを今すぐ使うべき理由
Devinを現場で活用することで、以下のような利点があります。
- 反復作業を自動化でき開発効率が上がるから
- 人間は設計・判断・調整に集中できるから
- 生成AIスキルが単価アップや案件選定で武器になるから
それぞれの理由について詳しく解説します。
反復作業を自動化でき開発効率が上がるから
Devinは、コードの自動生成にとどまらず、反復的な開発タスクを包括的に代行できます。例えば、APIのルーティング設定、フロントエンドのエラーハンドリング、ユニットテストのテンプレート作成など、定型的な作業はプロジェクトごとに発生するものです。
こうした作業を人手で行えば、品質のばらつきやタイムロスが発生しやすくなりますが、Devinを活用すれば安定したクオリティで短時間のうちに処理可能です。また、CI/CDツールとの連携も想定された構成になっており、GitHub Actionsなどの設定を自動で組み立てられます。
これにより、エンジニアは1日のうちで対応できるタスク数が増え、クライアントへの価値提供スピードも向上します。結果として納期短縮、工数削減という明確な成果につながるでしょう。
人間は設計・判断・調整に集中できるから
開発現場では、エンジニアがコードを書く以外にも多くの業務が発生します。要件の整理、技術スタックの選定、UI/UXの整合性の確認、ステークホルダーとの折衝など、思考と対話を必要とする業務はAIでは対応しきれません。
出典:AIにも苦手なことがある?AIの得意分野・不得意分野とは? | Vieureka株式会社(ビューレカ)
Devinは、その前後にある手間のかかる作業を肩代わりすることで、こうした人間固有の業務に集中できる環境を生み出します。
人間が手を動かすことに終始するのではなく、価値を生み出すポジションにシフトすることで、同じ時間内でも成果の密度が高まり、プロジェクト全体の質が底上げされるでしょう。こうした働き方は、キャリアの伸びしろにも大きく影響します。
生成AIスキルが単価アップや案件選定で武器になるから
DevinのようなAIツールを使いこなすスキルは、単なる「便利な知識」ではなく、報酬や案件獲得に直結する「武器」になっています。
現場でDevinを活用するには、タスクの言語化力やプロンプト設計力、AIの挙動への理解が必要不可欠です。これらのスキルを持つエンジニアは現時点で少なく、企業としても確保したい人材となっています。
つまり、今この段階でDevinを業務に取り入れられるようになれば、それだけで他者と明確な差別化ができ、市場での競争力を高められます。生成AIの活用は、もはや先進的な取り組みではなく、プロとしての「前提条件」になりつつあるでしょう。
エンジニアが業務でDevinを使う際の注意点
Devinは高機能なAIですが、実務に導入する際にはいくつかの注意点があります。
- 操作画面は英語中心で完全な日本語対応ではない
- すべての開発を完全自動化できるわけではない
- AIの出力には必ず人のレビューが欠かせない
それぞれのポイントを詳しく解説します。
操作画面は英語中心で完全な日本語対応ではない
Devinはグローバル展開を前提に設計されており、UIやドキュメントは基本的に英語で構成されています。
例えば、プロンプトの説明文やタスクの実行ログ、エラーメッセージ、設定項目、GitHub連携の指示文など、操作全体にわたり英語ベースです。そのため、日常的に英語を使用していないエンジニアにとっては、理解に時間がかかる可能性があります。
特に、エラー発生時の対応や複雑なタスクの調整では、単語の意味だけでなく文脈まで正しく読み取る力が求められます。自動翻訳ツールの利用も一部で可能ですが、細かなニュアンスや技術的な含意までは反映しきれないケースも多いため、業務レベルでDevinを活用するには、一定以上の英語リテラシーが必須です。
すべての開発を完全自動化できるわけではない
Devinは強力な自律型AIではありますが、すべての開発業務を100%自動化できるわけではありません。特に、クライアントの要望をヒアリングして要件をまとめたり、事業戦略に沿った仕様を構築したりする工程は、Devinに任せられない重要な判断領域です。
また、プロジェクトが進行する過程で生じる仕様変更や緊急の設計見直しなどにも、AIは柔軟に対応できません。これらは、ビジネス背景やユーザー視点を理解しながら最適解を導き出す人間ならではの能力に依存します。
さらに、Devinが自動で処理できるのは、あくまで明確に定義されたタスクやプロンプトに沿った業務です。曖昧な指示や不完全な前提条件のもとでは、誤動作や誤解釈が発生するリスクもあります。
したがって、Devinの導入にあたっては、「万能な代替手段」として捉えるのではなく、「人の判断を支援するパートナー」として位置づけることが重要です。人間が主導し、AIが実行を支えるという構図を前提に業務設計を行うことで、真に効果的な活用が実現できます。
AIの出力には必ず人のレビューが欠かせない
Devinは驚異的なスピードと精度で開発業務を遂行できるAIですが、その出力が常に正確とは限りません。
例えば、コードの生成結果における意図しない挙動や、バグの見逃し、仕様との乖離など、人の目による確認を怠ると深刻な不具合を引き起こす恐れがあります。Devinは与えられたタスクを完遂しようとする一方で、背景や全体のコンテキストを読み取る力は限定的です。
そのため、ビジネス要件やセキュリティポリシー、ユーザー体験といった多角的な視点でのチェックは人間の責任領域となります。実際に、生成されたコードやテストケースは、少なくとも一度はエンジニアによるコードレビューと動作確認を経るべきです。
また、レビュー工程を通じてAIのアウトプット傾向を把握できれば、次回以降のプロンプト精度も高まります。Devinを活用する上で、最終的な品質担保を自ら担う意識は欠かせません。
Devinの登場でエンジニアの業務内容や評価軸はどう変わる?
Devinのような自律型AIの普及により、エンジニアの役割や評価の視点は大きくシフトし始めています。
- 「書くだけの人材」はAIに置き換えられやすい
- 設計・提案・推進ができる人材の需要は高まる
それぞれの変化について解説します。
「書くだけの人材」はAIに置き換えられやすい
単純なコーディングやテンプレート業務だけを担っているエンジニアは、今後AIに取って代わられるリスクが高いです。
特にDevinのようなAIは、タスクを与えるだけで設計図どおりにコードを書き上げる力を持っており、人手では数時間かかる作業を短時間でこなします。HTMLのマークアップやCRUD処理、API連携の実装など、定型化された業務はすでにAIの得意領域です。
これにより、単に「手を動かすだけ」の人材はコストパフォーマンスの面で比較されやすくなり、代替の対象になってしまいます。つまり、技術者である以上は、手を動かす能力に加えて、「何を、なぜ、どう作るか」を考えられる力が必須です。今後はスキルの再定義が避けられず、AIを扱う側に回るスキルの習得が急務といえるでしょう。
設計・提案・推進ができる人材の需要は高まる
DevinのようなAIが業務の自動化を推し進める一方で、その活用方法を定め、プロジェクト全体を前に進める人材の重要性はむしろ増しています。
出典:人工知能(AI)の導入や活用に必要なAI人材(コラム) | アーカイブ | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
例えば、顧客との要件定義、技術選定、タスクの分解とAIへの落とし込み、さらにはチーム内外の調整など、人間だからこそ担える役割は数多くあります。特に上流工程が求められる案件では、単なるエンジニアではなく、プロダクトの方向性を示せる「テックリード」や「プロダクトオーナー」的な視点が評価されやすいです。
AIの出力精度を最大限に活かすためには、人がタスク設計とプロンプト最適化を行い、意図した成果に導く力が必要です。そのため、AI時代においても設計・提案・推進といった非自動化領域を担えるエンジニアは今後さらに価値が高まり、市場でも希少な存在となるでしょう。
AIと競合するのではなく、AIを組み込む立場として働くことで、持続的にキャリアを伸ばすことが可能です。
Devinを活用した案件獲得を目指すならFLEXY(フレキシー)をご利用ください
Devinのスキルを活かしてキャリアを広げたいエンジニアの方は、FLEXYをご活用ください。
FLEXYは、週4~5日稼働のフルコミット型案件に特化したエージェントサービスです。生成AIや上流工程に関するプロジェクトが豊富で、Devinの知見を武器にできる環境が整っています。
FLEXYでは、テックリードや技術顧問などのポジションも多く、単なる開発作業ではなく、AIを活用して業務設計や提案まで担う案件に参画できます。
また、専任コンサルタントによるサポートも受けられるため、スキルや志向にマッチした案件を効率的に見つけやすい点も大きな強みです。単価交渉や稼働日数の調整も相談できるので、フリーランスとして安定した働き方を実現したい方にも最適なサービスです。
Devinを含む生成AIの知識は、今後のエンジニア市場において差別化の軸になります。スキルを収益につなげるためにも、まずはFLEXYに無料登録し、希望に合った案件の情報収集から始めてみてください。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込むエンジニアが業務でDevinを使いこなすために必要なスキル
Devinを実務で活かすためには、以下のスキルを身につけておくことが重要です。
- 英語での操作や設定、基本的なツール連携の理解
- プロンプト設計やAIへのタスク分解力
- Slack・GitHubを使ったチーム開発スキル
それぞれ解説します。
英語での操作や設定、基本的なツール連携の理解
Devinを業務で使う上で避けて通れないのが、英語UIへの対応です。現時点でDevinのユーザーインターフェースや設定画面、実行ログ、ドキュメント類はすべて英語で構成されています。
そのため、エンジニアには英語の読解力が求められます。エラー内容の把握やパラメータの微調整、タスクの指定においては、英文の意図を正しく読み取らなければなりません。
また、DevinはGitHubやSlackといった一般的な開発ツールとの連携を前提に設計されています。これらのサービスとの連携を行うには、APIキーやOAuth設定、Webhookの活用といった最低限の技術的理解も不可欠です。
英語のUIと合わせて、周辺ツールへの適応力があるかが、Devinをスムーズに扱えるかを左右します。実務での活用を見据えるなら、英語リテラシーと開発ツールの基本操作を早めに習得しておきましょう。
プロンプト設計やAIへのタスク分解力
Devinを業務に組み込む上で欠かせないのが、「AIに的確な指示を与える力」です。これは、いわゆるPrompt Engineeringと呼ばれるスキルに該当します。
例えば、「このエラーを修正して」とだけ伝えても、Devinはどこまで修正すべきか、何を前提とするかを自動で判断できません。具体的な意図や前提、成果物の条件を明確にプロンプトとして与えることで、初めて正しいアウトプットが得られます。
このスキルは、単に命令を英語で入力することとは異なります。業務全体をタスクに分解し、それぞれをAIが理解可能な粒度に落とし込む思考力が問われるでしょう。特に要件定義や非機能要件を含むタスクでは、判断ミスが後工程に大きく影響するため、プロンプトの精度が品質を左右します。
生成AIを使いこなすための土台として、プロンプト設計は今後ますます重視される分野です。Devinの出力を制御するには、技術的知識と業務全体への理解を融合させた設計力が欠かせません。案件選定や単価アップにもつながるスキルとして、積極的に磨いていく必要があります。
Slack・GitHubを使ったチーム開発スキル
Devinは単独で動作するAIではなく、チーム開発環境と連携して真価を発揮します。SlackやGitHubとの連動を前提に設計されており、Devinはタスクの進捗報告や実行ログの通知をSlackに送信したり、GitHub上でPull Requestを作成したりといった機能を活用します。
これにより、開発チーム内でAIと人間が自然に役割分担できる状態が実現されます。そのため、チーム開発でのGitHub運用(ブランチ戦略・レビュー文化)や、Slackでの非同期コミュニケーションに慣れていることは大きな強みです。
例えば、Devinが生成したコードに対してメンバーがSlack上で指摘を返す、あるいはGitHubでAIと人が交互にレビューを行うといった運用が必要になります。現場では、こうしたツールを使ったAIとの協働スタイルが徐々に定着しつつあります。
SlackやGitHubの基本操作だけでなく、AIを含めたチーム設計・情報共有の工夫まで見据えて対応できる人材は、今後ますます重宝されるでしょう。
DevinなどのAIスキルを身につけるために今からできること
AI時代のスキル習得を目指すなら、以下のステップを意識することが重要です。
- エージェントに登録して案件を獲得する
- PoCやAI連携系の案件で実務経験を積む
- Devinの操作や挙動を小さな案件で試す
それぞれ解説します。
エージェントに登録して案件を獲得する
生成AIを扱うスキルを実務レベルに引き上げるには、実際のプロジェクトに関わるのが最短ルートです。
その際、個人で案件を探すよりも、専門エージェントを活用する方が効率的です。エージェントを通じて案件を受けることで、自分のスキルセットや稼働条件に合った依頼を精査して紹介してもらえます。
FLEXYは、週4~5日でのフルコミット型案件に特化しており、上流工程を任されるエンジニアやPM職へのニーズが高いです。さらに、担当コンサルタントが単価交渉や条件面の調整も行ってくれるため、安心してキャリアを進められる点も魅力です。
これからAIスキルを実践に落とし込みたい方は、まず信頼できるエージェントに登録し、自分に合った案件を探すことから始めましょう。
PoCやAI連携系の案件で実務経験を積む
生成AIやDevinのスキルを深めたい場合は、小規模なPoC(概念実証)案件から経験を積むのが有効です。
PoCは本格導入前の実験的な開発であるため、技術検証やツール導入の自由度が高く、トライ&エラーを重ねながらスキルを伸ばせます。
こうした案件では、「とにかくAIを動かしてみる」というフェーズが多いため、Devinの挙動や可能性をつかむには最適な環境です。さらに、仕様調整やクライアントとの要件整理など、AIに任せきれない部分の業務も含まれるため、AIと人間の役割分担を理解する力も養われます。
PoC案件で一定の成果を上げれば、より大規模なプロジェクトへの参画や単価アップも狙えます。経験を積むことで、クライアントへの提案力も高まり、キャリアの選択肢が広がるでしょう。
Devinの操作や挙動を小さな案件で試す
Devinをいきなり本番環境に導入するのはリスクがあるため、まずは小規模なタスクで慣れることが大切です。例えば、自身が請け負っている副業案件の一部、あるいは社内の検証タスクなどに限定して導入することで、Devinの使い勝手や動作のクセを把握できます。
実務で使うには、Devinに適切な指示を出し、結果を検証し、修正する一連の流れを体験しなければなりません。小さなタスクであれば、失敗しても全体の進行に影響しづらいため、安心して試行錯誤できます。
さらに、Devinが苦手とするタスクや予想外の動作についても、事前に把握しておくことで、本番導入時のトラブルを防げます。実践に近い形で段階的にスキルを磨くことで、自信を持ってAI活用の提案が可能です。小さな一歩から始めて、着実にスキルを伸ばしましょう。
今後のエンジニアの活躍にはAIが必須!Devinを活用して業務効率化を図ろう
DevinのようなAI技術を使いこなせるエンジニアは、今後のIT市場で確実に求められる存在です。従来の開発業務は、人がコードを書き、テストを行い、デプロイを進めるという流れでしたが、Devinはこれらの一連の作業を自律的に処理します。
AIを扱える技術者は、プロジェクトの推進役としての信頼も高まり、報酬やポジションに直結する場面も増えています。FLEXY(フレキシー)は、エンジニア・PMO向けに高単価でハイレベルな案件が中心で、DevinなどのAIスキルを活かしたプロジェクトに参画しやすいのが特長です。
登録後は、専属のコンサルタントがキャリア目標や稼働条件をヒアリングし、最適な案件をご紹介いたします。契約交渉から稼働後のフォローまでを一貫して支援しますので、フリーランスとしての不安も軽減されます。
これからのエンジニアは、AIと共に価値を発揮する時代です。Devinなどの生成AIスキルを武器にしたキャリア形成を目指す方は、ぜひFLEXYへの無料登録をご検討ください。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む







