【CTOインタビュー】「理屈なき圧倒的当事者意識を押しつけるつもりはありません」――巨大なエンジニア組織を作ったリクルートの変化とは リクルートテクノロジーズ・米谷修さん

357社のグループ企業に、4万5000名を超える従業員数(ともに2017年3月31日時点)を誇るリクルート。巨大なグローバルカンパニーとなった現在も積極的に新たなサービスを開発し、「リクルートらしさ」を探ろうとするメディアの記事はたびたび話題を呼んでいます。
今回のCTOインタビューでは、そんなリクルートグループの技術部門を支える株式会社リクルートテクノロジーズ執行役員・CTOの米谷修さんを直撃。「リクルートのエンジニア」が担うミッションや、グループが目指す未来についてお話をうかがいました。
【米谷修さんのプロフィール】
株式会社リクルートテクノロジーズ 執行役員 CTO。1988年、リクルートへ新卒入社。大阪の経理部門に配属され、財務諸表作成などを担当する中で人手を自動化することに快感を覚え、グループ会社の会計システム開発などに関わる。2000年からは各事業のIT部隊を統合した「FIT」(Federation of IT:全社情報システム部門)において、『リクナビ』開発リーダーとして大規模システム開発や構造改革を推進。その後はシステム基盤推進室(現ITソリューション部)設立などに携わり、2012年より現職。
目次
伝統的な事業別組織から、IT部門に特化した機能別組織へ
Q.リクルートグループは、ここ数年で一気に「たくさんのエンジニアが活躍する会社」というイメージが定着したように思います。どのようにしてエンジニア組織を作ってきたのでしょうか?
米谷修さん(以下、米谷):リクルートがITに力を入れるべきだと考え始めたのは、90年代後半であったと記憶しています。『RECRUITBOOK on the Net』(リクルートブックオンザネット)という新卒向け求人メディアをリリースした頃です。初めて紙媒体からネットへの切り替えを経験し、これが現在の『リクナビ』につながっています。
誌面から写真とテキストを転載するだけでなく、説明会予約などができる機能も持たせたのですが、初期の頃はウェブサービス開発のノウハウがなかったので非常に苦労しましたね。オープンと同時に膨大なトラフィックが来るようになって、サービスを動かしていくのも大変でした。
それまでのリクルートでは、紙媒体の商品企画担当者が外部にアウトソーシングしてウェブサービスを作ったり、勘定系システムなどを外部から取り入れたりしていたんです。さまざまな領域でウェブサービスを立ち上げるようになり、事業ごとにIT部隊を持つようになっていきましたが、自前で巨大なサービスを動かすためには組織体制の変革も必要でした。そうして生まれたのが各事業のIT部隊を統合した「FIT」(Federation of IT:全社情報システム部門)という組織で、私自身もそこで『リクナビ』などの商品を担当していました。
リクルートは伝統的に事業別の組織を作り、カスタマーの声をダイレクトに聞きながらサービスを育ててきましたが、一方では技術力を伸ばしにくいという課題がありました。ウェブサービスを作る技術が目まぐるしく進化していく中、競合に勝つために、数年の試行錯誤を経て機能別組織に切り替えていったんです。
ビッグデータ専門、インフラ専門など組織がどんどん細分化していったタイミングで、グループ内の各事業がマーケットに合わせて分社化することとなりました。こうして2012年にIT部門を管掌する機能会社としてリクルートテクノロジーズが発足しました。『リクナビ』などを運営するリクルートキャリアや『HOT PEPPER』『じゃらん』などを運営するリクルートライフスタイル、『SUUMO』などを運営するリクルート住まいカンパニーといった、各事業会社と連携してサービス開発を進めています。
「リクルートっぽさ」のイメージが先行してしまっていることも
Q.そうした体制の中で、エンジニアの人数も飛躍的に増えていますね。
米谷:エンジニアやプロジェクトリーダー、デザイナーなども含めると、直近4年間でリクルートテクノロジーズのメンバーは150人から約700人に増え、その8割近くが中途採用のメンバーです。プロジェクトリーダーを担うことができる人材がまだまだ不足していることを課題に感じていて、技術の深さや品ぞろえ、さらに物量も、より充実させていくことが必要となっています。専門性の高い人材を採用するための活動には手を抜けません。
Q.外部からは「リクルートらしさ」や「リクルートの文化」といったものが注目されがちだと思いますが、中途で入社するエンジニアにもそうした考え方を求めていくのでしょうか?
米谷:「圧倒的当事者意識」のように、リクルートっぽさを表しているとして広く知られている言葉もあることは承知しています。私たちの社内用語では略して「ATI」と呼んでいるのですが(笑)。これはある種、イメージが先行してしまっている部分もあるかな、と思っています。
リクルートのDNAがあるとすれば、「カスタマーと顧客をちゃんと見て価値提供していこう」ということ。これは別に一子相伝で限られた人に受け継がれているというわけではなく、組織として、仕組みとして浸透させている考え方です。もちろん中途入社のエンジニアにはそうした考え方で仕事に向き合ってもらうことを求めますし、なじみやすい考え方でもあると思います。
それこそ私が入社した1988年頃は、「理屈がなくてもとにかくやろう!」といった、いかにも営業会社的なマッチョな風土もありましたよ。この考え方をもし今のリクルートテクノロジーズが引きずっていたら、エンジニアにはなじみづらい会社になってしまっていたかもしれませんね。当社代表の北村吉弘は、「理屈のない圧倒的当事者意識は危険だね」と話していました。
Q.「理屈のない圧倒的当事者意識」とは、印象的な表現です。
米谷:僕のようなプロパーからすれば、上司に日々「お前はどうしたいの?」と問われ、それに答えるのは、息を吸って吐くようなもの。新人の頃から染み付いている習慣なんです。しかし、SIerなどまったく違う文化の会社でキャリアを積んできたエンジニアに同じ感覚を求めるのはおかしいですよね。「そんなことをいきなり問いかけられても……」と感じるはずで。
圧倒的当事者意識を大切にする風土があるとしても、それを意味もなく押し付ける必要はない。ましてや当事者意識といったものは「自分がやるべき、やりたい」と思えた結果として生まれるもの。意識すること自体を目的にするのはおかしい。それが「理屈のない圧倒的当事者意識は危険だね」という言葉の意味です。
そんなことを意識しつつ、自分たちのサービスをとにかく良いものにしたい、そんな意識を強く持っている事業サイドの人たちとも連携する機会をたくさん設けています。
「事業」と「機能」で分担する組織づくり
Q.リクルートは巨大グループの中で多数のサービスを運営していますが、エンジニアが各事業会社と連携する上で、どのような工夫をしているのでしょうか?
米谷:率直に言って、機能会社と事業会社の間では壁ができやすいという課題があります。そのため「両者の間にどんな接点を作るか」ということを常に考えているんです。
リクルートテクノロジーズだけでなく各事業会社にもエンジニアがいて、新規事業を作る際に求められるスピーディーな対応などは彼らが担っています。事業の現場でアジャイルに動く組織はその会社に置き、私たちはセキュリティーなどの根幹に及ぶ部分も含めて専門的に対応しているのですが、さらにこの組織内でも事業別と機能別で分けています。こうしたチューニングを日々やり続けているという状況です。技術も市場も目まぐるしく変わっていくので、このチューニングを日々やらなければついていけなくなるんですよね。
Q.エンジニアに対する評価制度でも、独自の仕組みを作っているのですか?
米谷:リクルートではグレードとミッションに基づく評価制度を運用していて、半期ごとの人事考課を行っていますが、エンジニアに対しては評価の階段が極端に変化しすぎないようにしています。エンジニアのミッションは3カ月で完成するようなものは少ないので、この期間だけでは測れない部分もあるんですよね。安心してエンジニアが働ける環境を用意することが大切なので、グレードとミッションをこまかく調整するなどの運用を行っています。
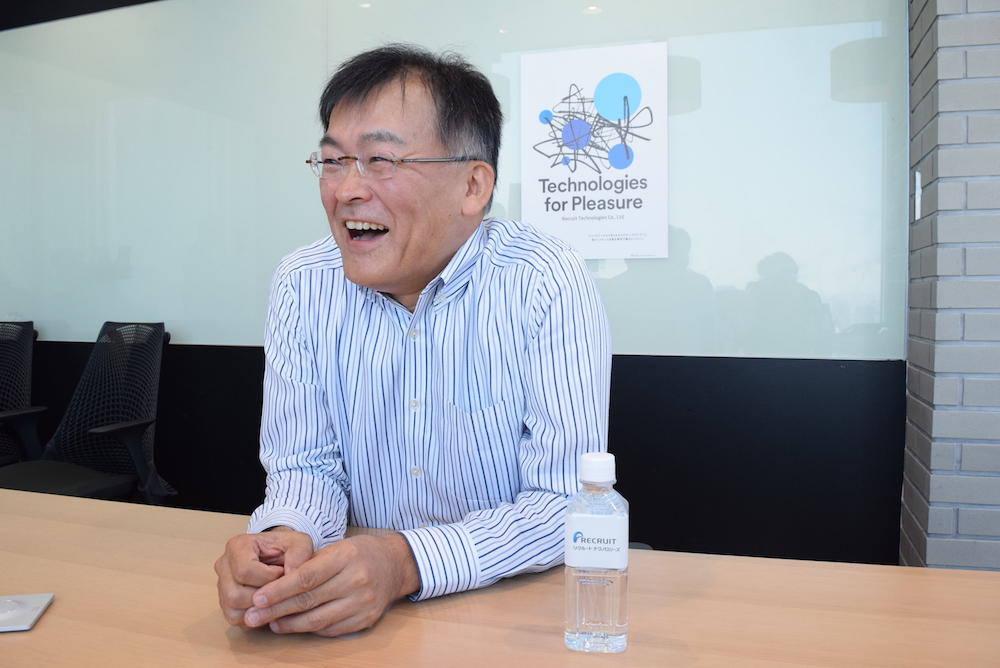
「開拓」「実装・展開」「運用」の3フェーズで、柔軟に新技術を試せる環境
Q.米谷さんはエンジニアリングによる研究開発部門「ADVANCED TECHNOLOGY LABO」(アドバンストテクノロジーラボ=ATL)の所長も務めています。
米谷:こうした部門を持てることはとても幸せですね。リクルートホールディングスの経営陣が素晴らしい決断をしてくれたんです。
以前に私たちは、世の中にあるシステム子会社の状況を調査したことがあります。そうした会社の設立背景を追っていくと、ほとんどの動機がコスト削減だったんですよ。
一時期コアコンピタンス(企業の核となる技術や特色)という言葉が流行りました。その流れで「ITはコアじゃない」「だから子会社化して給与テーブルを下げる」といった動きが増えた。そうした会社のその後を追うと、ほとんどうまくいっていないわけです。当然といえば当然ですよね。コアじゃないと言われてエンジニアのモチベーションは下がるし、本体から下りてくるトップはしょっちゅう変わる。これではR&Dは進みません。
しかしリクルートの場合は違いました。グループトップである峰岸真澄さん(リクルートホールディングス代表取締役社長兼CEO)は、「我々はITの会社を目指す。リクルートテクノロジーズはその中心としてR&Dに注力する」と宣言したんです。
Q.この宣言はどのような動きにつながったのでしょう?
米谷:R&Dに注力する会社を目指すため、私たちの仕事を「開拓フェーズ」「実装・展開フェーズ」「運用フェーズ」に分けました。
開拓フェーズでは新しい技術を試して検討します。実装・展開フェーズではこれを実際のサービスで試してみる。ここでは事業会社がコストを負担する必要はありません。そしていよいよ運用フェーズとなれば、技術をサービスに実装し、事業会社にもコストを負担してもらいながらカスタマーへの価値向上を実現していきます。
この3段階のフェーズがあることで、私たちはサービスの進化に直結するかどうか分からない新技術もどんどん試せるようになりました。システム会社でよくある「予算がないから新しい技術に挑戦できない、成長できない」という課題を乗り越えたんです。優秀な人材が集まってくれる理由としても、こうした環境があることは大きいと思っています。
組織としてはR&D専門部隊を持っていますし、エンジニア個人にも、半期ごとにミッションの何パーセントかをR&Dに振り分けるなどして新たな技術への意識を高めてもらっています。
領域を問わずにエンジニアがアイデアを出し、製品化できる
Q.ATLでは現在、どのような研究開発を進めているのですか?
米谷:例えば「スマートキー」に関する研究があります。一般のマンションなどで、スマホを使って鍵の開閉などが行えるツールです。アプリを起動しなくてもスマホを振るだけで鍵が開く「iNORTH KEY」(イノースキー)という商品を開発しました。ATLではIoT分野の試作品としてこれを作ったのですが、とあるマンションデベロッパーが興味を持ってくれて、どんどん導入が進んでいます。
中継機を介してサーバーセンターにつなぐことで、サーバーセンターを介しても鍵の開閉ができるので、不動産会社の社員が賃貸物件の内覧で入居希望者を案内するときなどは、いちいち大家さんに連絡して鍵を借りる必要がないんです。そんなイノベーションにもつながっています。
ATLではそんな風に、テクノロジーありきでエンジニアがどんどんアイデアを出し、製品化できます。領域を問わずに取り組めるので、今後はヘルスケアやブロックチェーンなどでも面白いアイデアが出てくるのではないでしょうか。
Q.ATLでは外部エンジニアに向けても無料開発スペースを提供していますね。
米谷:会員登録をしてもらえれば、「ATL客員研究員」として高額な機器も無料で使えるようになります。最も大きな理由は、こうしたオープンイノベーションスペースを設けることで外部の知見を積極的に取り入れていきたいと考えていることです。実際に外部エンジニアによって開発されたシステムやプロダクトについては、「ATLで作った」とさえ言ってくれれば、著作権を求めるようなことはありません。今後も、より多くの方にこの場所を活用していただけるとうれしいですね。
Q.最後に、米谷さんご自身の今後の展望も教えてください。
米谷:リクルートテクノロジーズのITは、まだまだ理想には程遠い状態だと思っています。冒頭でお話したような技術の深さや品ぞろえ、物量の充実や、事業サイドとITサイドのこまかいバランス調整などは、さらに力を入れていきたいと思っています。
個人的には、「アウトプットとインプットを増やすこと」でしょうか。これまで、さまざまな試行錯誤を経て物事を動かしてきました。他社の方からお悩みを聞いていると「僕たちが一度通ってきた道だな」と思うこともあります。組織の作り方や人材育成方法、さらにはストレージの組み方といったこまかなところまで、貴重な経験談として聞いていただけることがあるんです。僕自身が積極的にノウハウを外部へ提供し、外部からも新たな知見をいただく。そんな機会を増やしていきたいと考えています。




