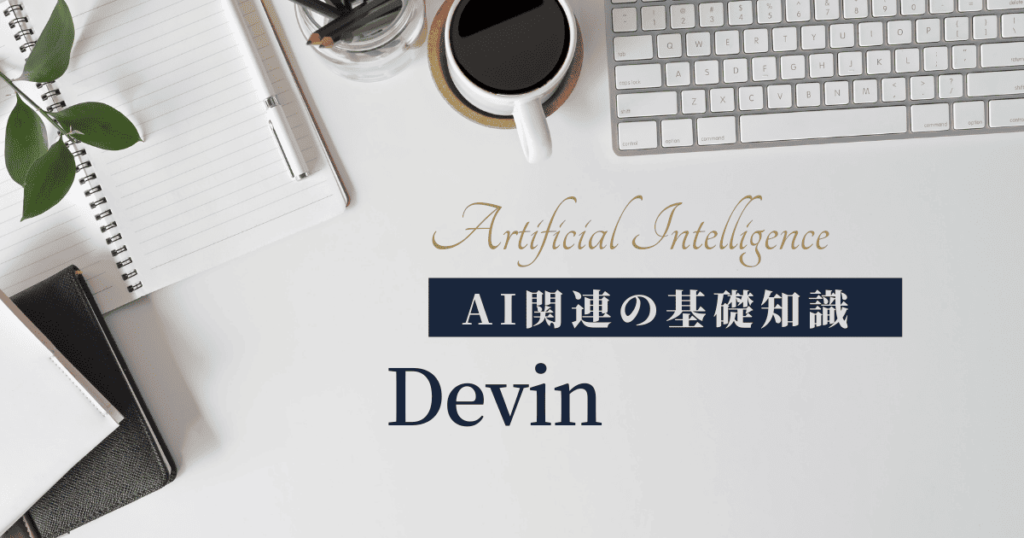LLMと生成AIの違い|仕組み・活用法・注意点をわかりやすく解説

近年、生成AIや大規模言語モデル(LLM)の進化が目覚ましく、業務効率化やクリエイティブ分野での活用が進んでいます。しかし、これらの技術がどのように機能し、何が異なるのかを正確に理解することは容易ではありません。
本記事では、LLMと生成AIの基本的な定義から、ビジネスでの具体的な活用事例、導入前に考慮すべきリスクまでを網羅的に解説します。
LLMや生成AIの知識を活かしたい方は、エンジニア案件を多数扱っているFLEXY(フレキシー)をご活用ください。
希望や経歴をおうかがいした上で、条件に合った案件をご紹介します。登録は約60秒で完了し、契約まですべて無料なので、ぜひご活用ください。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む目次
LLM(大規模言語モデル)とは?
ここでは、LLMの基本的な定義や役割、自然言語処理における重要性、そして代表的なモデルについて詳しく解説します。
LLMの定義と役割
LLM(大規模言語モデル)は、膨大なテキストデータを学習し、人間のように自然な言語を理解・生成するAIモデルです。
文章の読解、要約、翻訳、質問応答など、多岐にわたる言語処理タスクを高精度でこなします。ChatGPTやClaude、LLaMAなどが代表的なLLMとして知られています。
これらのモデルは、Transformerアーキテクチャを基盤とし、自己注意機構を活用して文脈を把握し、適切な応答の生成が可能です。LLMの導入により、業務の効率化や新たなサービスの創出が期待されており、ビジネスシーンでの活用が進んでいます。
自然言語処理におけるLLMの重要性
LLMは、従来のモデルでは難しかった文脈の理解や長文の処理が可能となり、より自然な対話や文章生成が実現されています。
例えば、カスタマーサポートにおける自動応答や、社内文書の要約、マーケティング資料の作成など、実務に直結する用途での活用が進んでいます。また、LLMは多言語対応や専門用語の理解にも優れており、グローバルなビジネス展開や専門分野での応用にも適しているのです。
代表的なLLM(GPT、Claude、Llamaなど)
現在、さまざまなLLMが開発・提供されています。OpenAIのGPTシリーズは、汎用性の高さと高精度な文章生成で広く利用されています。
AnthropicのClaudeは、安全性と倫理性を重視した設計で、法務やビジネス分野での活用が期待されているものです。
MetaのLLaMAは、オープンソースで提供されており、研究開発やカスタマイズに適しています。これらのモデルは、それぞれ特徴や得意分野が異なるため、用途や目的に応じた適切なモデルの選定が重要です。
生成AIとは?
ここでは、生成AIの定義と技術背景、そして各分野での生成AIの違いについて解説します。
生成AIの定義と技術背景
生成AIとは、既存データを学習し、新しいコンテンツを自動生成するAI技術の総称です。主な技術としては、敵対的生成ネットワーク(GAN)やトランスフォーマー(Transformer)があります。
GANは画像生成に強く、生成器と識別器の競合構造で高品質な出力を可能にします。一方、Transformerは自然言語処理を飛躍的に進化させ、文章やコードの生成など幅広い応用が得意です。
これらの技術により、テキスト、画像、音声といった多様なデータ形式の生成が現実のものとなりました。つまり、生成AIは革新的なアウトプットを可能にする仕組みであり、業務活用にも十分な実力を備えています。
画像・音声・テキスト生成の違い
生成AIは用途に応じて得意分野がわかれます。画像生成では「DALL·E」などが知られ、与えられた文章をもとに創造的なビジュアルを出力します。
音声分野では「Whisper」が代表的で、多言語対応の音声認識や文字起こしが強みです。テキスト生成では「GPT」シリーズが主流で、質問応答、文章作成、要約といった業務を高精度に支援します。
それぞれ異なるモデル構造と学習方法を持つため、導入時はタスクに応じた選定が重要です。これにより、生成AIの効果を最大限に活用することが可能になります。
FLEXYサービスを見るLLMと生成AIの違いとは?
ここでは、LLMと生成AIの関係性と相違点について解説します。
LLMは生成AIの一種?
LLM(大規模言語モデル)は、生成AIの中でも自然言語処理に特化したモデルです。生成AIは、テキスト、画像、音声、動画など、多様なコンテンツを生成するAI技術の総称であり、LLMはその一部として位置づけられます。
例えば、ChatGPTはOpenAIが開発したLLMであり、自然な会話や文章生成を得意としています。このように、LLMは生成AIの中でもテキストデータの理解と生成に特化したモデルであり、特定のタスクに対して高い精度を発揮するのが特徴です。
LLMと他の生成AI(画像/音声系)の違い
LLMと他の生成AIとの主な違いは、扱うデータの種類(モーダル)にあります。LLMはテキストデータの生成に特化しており、文章の要約、翻訳、質問応答などの自然言語処理タスクを得意とします。
一方、画像生成AI(例:DALL·E)は画像の生成、音声生成AI(例:Whisper)は音声データの生成が主な目的です。これらのモデルは、それぞれのデータタイプに最適化されており、用途に応じた適切なモデルの選択が重要です。
仕組みの違い(トークン化/ネットワーク構造)
LLMは、Transformerアーキテクチャを基盤とし、トークン化や自己注意機構(Self-Attention)を用いてテキストデータを処理します。
トークン化とは、文章を単語やサブワードなどの単位に分割するプロセスであり、これによりモデルは文脈を理解しやすくなります。
一方、画像生成AIは、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)や拡散モデル(Diffusion Models)などを用いて、画像データを処理・生成する仕組みです。音声生成AIは、リカレントニューラルネットワーク(RNN)やTransformerを活用し、音声波形の生成や変換を行います。
このように、各モデルは対象とするデータタイプに応じて、最適なネットワーク構造を採用しています。
得意なタスクの違い
LLMは、テキストデータの生成や理解に特化しており、文章の要約、翻訳、質問応答、文章生成などのタスクに強みを持ちます。例えば、カスタマーサポートにおける自動応答や、コンテンツの自動生成などで活用されています。
一方、画像生成AIは、広告やデザイン分野でのビジュアルコンテンツの作成、音声生成AIは、ナレーションや音声アシスタントの開発などに利用されることが多いです。
それぞれのモデルは、特定のタスクに対して最適化されており、目的に応じて適切なモデルを選択することが求められます。
ビジネスにおけるLLMと生成AIの活用例
LLMと生成AIは、以下の分野で活用が進んでいます。
- 業務効率化(カスタマーサポート、社内FAQなど)
- マーケティング・クリエイティブ分野での活用
- 教育・医療・法務など専門分野での利用
ここでは、それぞれの活用例を解説します。
業務効率化(カスタマーサポート、社内FAQなど)
LLMや生成AIは、日々の業務における繰り返し作業を自動化することで、効率化を実現します。
例えば、チャットボットによるカスタマーサポートは代表例です。問い合わせ対応をAIが担うことで、担当者は高度な課題解決に集中できます。
カスタマーサポートツール「Tayori」では、生成AIの導入が進んでいます。2024年1月に発表された調査では、生成AIを活用したチャットボットやメール自動応答などの導入が進む一方で、FAQの不備により75%の顧客が自己解決できず問い合わせに至っているという課題も明らかになりました。
また、社内FAQの自動生成・応答にLLMを活用すれば、情報共有や新人教育にも効果的です。こうした導入により、人的リソースの最適化と対応スピードの向上が実現可能です。
出典:生成AIのCS活用は二極化 最新カスタマーサポート調査をTayoriが公開 | 株式会社PR TIMESのプレスリリース
マーケティング・クリエイティブ分野での活用
生成AIは、広告コピーやSNS投稿の自動生成、画像制作などに加え、商品開発の現場で活用されています。
例えば、キリンビールでは「氷結®」ブランドの商品開発において、生成AIによるAIペルソナを導入しました。顧客の声を学習させたAIがユーザー像を再現し、商品コンセプトやフレーバーの仮説検証をサポートしています。
出典:生成AIをキリンビールのマーケティングに実装する検証を開始 | 2023年
これにより、従来時間を要したインサイト抽出が迅速化され、顧客理解の質向上と開発スピードの両立が可能になっています。
教育・医療・法務など専門分野での利用
専門性の高い領域でも、LLMと生成AIは補助的なツールとして価値を発揮しています。
教育分野では、学研がKnewtonと連携し、生成AIを活用した個別最適化学習を推進中です。学習効果を高めるAI教材の開発が進んでいます。
医療分野では、東北大学病院がNECと共同で電子カルテから治療経過を要約するAIを検証し、文書作成時間を約半分に短縮したと報告されています。
出典:東北大学病院、生成AIで電子カルテからの医療文書作成を検証、作成時間が半分に | IT Leaders
法務分野では、LegalForceが契約書の自動レビューや条文のリスク抽出を支援し、法務業務の効率化と品質向上に貢献しています。
出典:【公式】LegalForce(リーガルフォース)| AIレビューサービス
LLMと生成AIの導入前に知っておきたいポイント
生成AIやLLMは多くのビジネスに革新をもたらしますが、導入に際して以下の注意点を踏まえる必要があります。
- 誤情報(ハルシネーション)のリスク
- コストと学習データの問題
- セキュリティ・プライバシー面の懸念
それぞれ解説します。
誤情報(ハルシネーション)のリスク
LLMや生成AIは高性能である一方、事実と異なる内容をもっともらしく出力する「ハルシネーション」が発生する可能性があります。
これは、AIが学習した情報の中からパターンに基づいて文章を構築する仕組みに起因します。
例えば、OpenAIのChatGPTは、医学的な質問に対して実在しない文献を引用したことがあり、米国では弁護士が誤引用で制裁を受けた事例が存在します。
出典:ChatGPTで資料作成、実在しない判例引用 米国の弁護士 – 日本経済新聞
こうした誤情報を放置すれば、ビジネス上の信用を失うだけでなく、法的リスクに発展するおそれがあるでしょう。
導入時は、AIの出力結果に対して必ず人間によるファクトチェック体制を整えることが不可欠です。情報の真偽を精査するプロセスを設けることで、AIを活用していけるでしょう。
コストと学習データの問題
LLMの運用には、非常に高額なコストがかかります。とくに大規模なモデルを独自に構築・保有する場合、膨大な量の計算資源と電力が必要です。
また、学習データの質と量も重要です。不適切なデータを与えれば、出力結果に偏りや誤りが含まれるリスクが高まります。
業務に活かすには、生成AIを自社で構築するのではなく、既存の信頼性の高いプラットフォームを活用し、目的に応じたチューニング(RAGなど)を加える方法がおすすめです。
出典:RAG とは何ですか? – 検索拡張生成 AI の説明 – AWS
セキュリティ・プライバシー面の懸念
生成AIやLLMの活用に際しては、情報漏えいや個人情報保護といったセキュリティ面にも細心の注意が求められます。
とくに社内文書や顧客データを含む入力内容がAIサービス側に保存・解析されるリスクが懸念されており、2024年の消費者庁「生成AI編」でも同様の指摘がなされています。
利用するAIが外部サービスである場合、入力内容が無断でモデル学習に使われる可能性もあるため、契約書やガイドラインによる制限が不可欠です。
また、EUのAI規制法や日本の個人情報保護法も視野に入れた運用体制を整備する必要があります。
業務で活用する前には、情報の取扱範囲、保存ポリシー、管理者の責任分担などを明確化し、安心して利用できる仕組みを構築しましょう。
LLMと生成AIの違いを理解してFLEXY(フレキシー)で仕事を見つけよう
LLMや生成AIといった先端技術の習得は、キャリアアップの大きな武器になります。FLEXY(フレキシー)では、こうした最新技術を扱う企業案件を多数紹介しています。
AI関連の案件も増加傾向にあり、PythonやLLMを用いたアプリケーション開発、生成AIの導入支援など、専門性を活かせるチャンスが広がっています。
このような高単価・高スキル案件にスムーズに参画できるのがFLEXYの強みです。無料登録は約60秒で完了します。
登録後は、キャリアアドバイザーによるヒアリングを経て、希望条件に合った案件の提案が可能です。また、面談調整や条件交渉、稼働後のフォローまで一貫して支援します。
わずか60秒で無料登録できますので、ぜひこの機会にご活用ください。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む