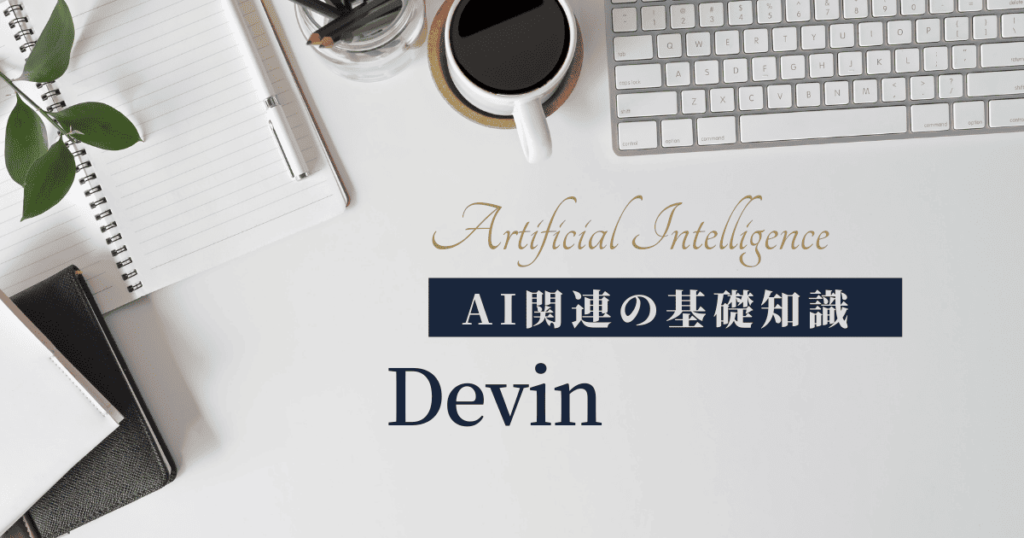企業で実施すべきセキュリティ対策とは?具体的な方法も徹底的に解説

近年、サイバー攻撃の手口が巧妙化する中で、企業におけるセキュリティ対策はもはや「任意の取り組み」ではなく「必須の経営課題」となっています。
特にリモートワークやクラウドサービスの普及に伴い、情報漏えいや不正アクセスのリスクは日々高まっています。万が一、機密情報が外部に流出すれば、企業は信用の失墜や損害賠償といった重大なリスクを負うことになるでしょう。
そこで本記事では、セキュリティ対策の基本から個人・企業それぞれが講じるべき具体策までを網羅的に解説します。
セキュリティ分野の知見を活かして高単価案件に関わりたい方は、FLEXY(フレキシー)をご活用ください。FLEXYでは、専門性を活かしたセキュリティ関連の案件も豊富にご紹介しています。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む目次
セキュリティ対策とは?
ここでは、セキュリティ対策の基本的な定義や考え方、そして導入の背景について詳しく解説します。
セキュリティ対策の定義とは
セキュリティ対策とは、情報資産を保護するための予防・検知・対処の3段階から成る施策です。
ウイルス対策だけでなく、不正アクセスの防止やインシデント時の対応なども含まれます。例えば、社内のアクセス制御や通信の暗号化、定期的な脆弱性診断も重要です。加えて、検知にはログの監視やアラートの設定、対処にはマニュアル化や初動対応体制の構築が不可欠です。
これらの対策は単体ではなく、複数の手段と運用を組み合わせて効果を発揮します。企業も個人も、自らの資産に応じた「守り方」を設計し、継続的に見直すことが欠かせません。
情報セキュリティの3要素(CIA)
情報セキュリティの基本は「機密性・完全性・可用性」の3要素(CIA)に集約されます。
機密性は情報を許可された人のみが扱える状態、完全性は情報が正確かつ改ざんされていないこと、可用性は必要なときに情報へアクセスできる状態です。
例えば、クラウドサービスに保存されたデータは、アクセス制限で機密性を、編集履歴や監査ログで完全性を、サーバーの冗長化で可用性をそれぞれ確保しています。
3要素をすべて満たすことが、日常の業務運用から緊急時対応まで、あらゆる場面で重要となります。
セキュリティ対策が必要な背景と現状
高度化するサイバー攻撃と急速なデジタル化により、今やセキュリティ対策は不可欠な経営課題です。
近年は標的型攻撃やランサムウェアが横行し、特にテレワークやクラウド活用によって攻撃対象が拡大しています。IPAが発表する「情報セキュリティ10大脅威2025」でも、企業活動への影響が深刻化していることが確認可能です。
また、人的ミスによる漏えいや委託先からの侵入も後を絶たず、対策の範囲は組織外部にも及びます。中小企業も含め、被害は決して他人事ではなく、被害時の対応力や備えが今後の信頼を左右する時代に突入しています。
個人に必要なセキュリティ対策7選
個人に必要なセキュリティ対策としては、以下の7つが挙げられます。
- OS・ソフトウェアの常時アップデート
- ID・パスワード管理を徹底する
- ウイルス対策ソフトの導入と活用
- 2段階認証・多要素認証の導入
- フィッシング詐欺への注意
- スマホやタブレットの設定見直し
- クラウド利用時の注意点
それぞれの対策について解説します。
OS・ソフトウェアの常時アップデート
セキュリティ対策で最も基本かつ効果的なのが、OSやソフトウェアのアップデートを怠らないことです。実際、2017年に世界中に被害をもたらしたランサムウェア「WannaCry」は、Windowsの脆弱性を突いたもので、更新されていない端末が標的となりました。
出典:ランサムウェア「WannaCrypt」が世界中で猛威を振るう
こうした脅威は企業だけでなく、一般ユーザーの家庭用PCやスマホも例外ではありません。OSやブラウザ、ウイルス対策ソフトなどは、脆弱性を塞ぐために定期的に修正プログラム(パッチ)が提供されます。
自動更新をONにする・サポート切れ製品は使わないなど、日頃から「放置しない」意識が重要です。アップデートはわずかな手間で大きな被害を防ぐ効率的な手段です。
ID・パスワード管理の徹底
IDやパスワードの管理が甘いと、あなたの個人情報や資産が一瞬で奪われる危険があります。特に複数のサービスで同じパスワードを使い回す「リスト型攻撃」は、一般ユーザーの間でも大きな脅威です。
出典:PowerPoint プレゼンテーション – リスト型攻撃対策集について
SNSアカウントの乗っ取りや、クラウドに保存されたファイルの流出などが代表的な被害例です。推測されにくい英数字・記号を組み合わせた文字列を使い、各サービスごとにパスワードを変えるのが欠かせません。
ただしすべてを記憶するのは難しいため、信頼できるパスワードマネージャーの活用が推奨されます。
また、一定期間ごとの変更を習慣化することで、漏洩リスクをさらに抑えられるでしょう。
ウイルス対策ソフトの導入と活用
ウイルス対策ソフトの導入は、個人でも「最低限の防衛線」として不可欠です。インターネットを介したマルウェア、スパイウェア、ランサムウェアなどの脅威は日々進化しており、無防備な端末は格好の標的となります。
市販されているセキュリティソフトには、リアルタイム監視、不正アクセスのブロック、ウイルス検出・駆除、ファイル隔離、定義ファイルの自動更新など多くの防御機能が統合されています。
無料ソフトもありますが、ビジネス用途や重要なデータを扱う場合は、有償ソフトの導入を検討すべきです。特に、EDRの機能をもつウイルス対策ソフトを導入することで、侵入の検知だけではなく、侵入後の対策も強固にできます。
2段階認証・多要素認証の導入
ログイン時にパスワードのみを使用している状態は、鍵が一つしかない家のようなものです。
現代のサイバー攻撃において、パスワードの流出は避けられない前提で対策する必要があります。そこで推奨されるのが、2段階認証(2FA)・多要素認証(MFA)の導入です。
これは「IDとパスワード」+「確認コード(SMSやアプリ)」「生体認証」など、複数の方法で本人確認を行う仕組みです。
MFAの導入は多くの公的機関でも設定が推奨されており、不正ログインの抑制には欠かせない仕組みといえます。
出典:2段階(だんかい)認証(にんしょう)や多要素(ようそ)認証でセキュリティを高めよう
主要なクラウドサービスやSNSでは無料で利用できるため、必ず設定して防御力を強化しましょう。
フィッシング詐欺への注意
フィッシング詐欺は、今や誰もが狙われる身近な脅威です。実在する金融機関や大手ECサイトを装ったメール・SMSにリンクを記載し、偽サイトへ誘導してIDやパスワード、クレジットカード情報を盗み取る手口が主流です。
手口はますます巧妙化しており、公式サイトそっくりに偽装されたページを見抜くのは困難なケースもあります。対策としては、メール内のリンクを安易にクリックせず、公式アプリやブックマークからアクセスする習慣が有効です。
また、不審なURLの構造や文面の不自然さにも注意を払いましょう。加えて、セキュリティソフトのフィッシング保護機能やメールフィルタの活用も防止策として有効です。疑わしい場合は、情報を入力する前に一度立ち止まることが重要です。
スマホやタブレットの設定見直し
スマートフォンやタブレットは、日常の生活インフラとなっている反面、サイバー攻撃の格好の標的です。
特にロックが未設定の端末や、正体不明のアプリを許可している場合、紛失や盗難時に重大な情報漏えいにつながります。基本対策としては、画面ロック(PIN・指紋認証・顔認証)を必ず有効にし、アプリのアクセス権限も定期的に見直しましょう。
また、信頼性の低いアプリのインストールは避け、定期的なアンインストールも大切です。公共Wi-Fi使用時は、VPNの活用や機密情報の送受信を避けることでリスクを軽減できます。
モバイル端末の設定見直しは、すぐにできる対策でありながら高い効果を発揮します。小さな意識が大きな被害を防ぐでしょう。
クラウド利用時の注意点
Google DriveやDropboxなどのクラウドサービスは便利な反面、情報漏えいのリスクを常に抱えています。
クラウド上に保存されたデータは、インターネット経由でどこからでもアクセスできる反面、不適切な共有設定や不正アクセスによって第三者に閲覧・流出する恐れがあります。
例えば「誰でもリンクを知っていればアクセス可」に設定していると、意図しない人にも情報が渡る可能性があります。
対策としては、共有範囲の制限・閲覧権限の設定・アクセスログの確認が重要です。加えて、アカウント保護のために2段階認証を併用することで、さらなる安全性を確保できます。
業務用途であれば、企業向けクラウドのセキュリティポリシーを遵守することも不可欠です。
企業が実施すべきセキュリティ対策10選
企業が実施すべきセキュリティ対策としては、主に下記の10個が挙げられます。
- アカウント・権限管理のルール化
- 社内ネットワークのファイアウォール設置
- ゼロトラストの導入と考え方
- UTMなどの包括的セキュリティシステム活用
- 従業員向けセキュリティ研修の実施
- インシデント対応マニュアルの整備
- 物理的な端末の盗難・紛失対策
- リモートワーク環境のセキュリティ強化
- 外部委託先との情報共有ルール策定
- 情報漏えい発生時のリスクマネジメント
それぞれの対策について解説します。
アカウント・権限管理のルール化
企業におけるアカウントと権限の適切な管理は、情報セキュリティの基盤です。退職者のアカウントが残存していたり、業務に不要な権限が付与されていたりすると、内部不正や外部からの不正アクセスのリスクが高まります。
これらを防ぐためには、アカウントの作成・変更・削除に関する明確な申請・承認フローを整備し、定期的な棚卸しを実施して不要なアカウントや権限を削除することが重要です。また、役職や部署に応じたアクセス権限の設定を行い、最小権限の原則を適用することで、情報漏えいのリスクを低減できます。
さらに、ID管理ツールやシングルサインオン(SSO)の導入により、アカウント管理の効率化とセキュリティの強化を図ることが推奨されます。
社内ネットワークのファイアウォール設置
ファイアウォールは、社内ネットワークと外部ネットワークとの間で不正なアクセスを遮断する重要なセキュリティ対策です。
企業では、ポート制御や外部通信の監視を行うことで、外部からの攻撃や不正アクセスを防げます。
また、ネットワークアドレス変換(NAT)や仮想プライベートネットワーク(VPN)の構築、侵入防止システム(IPS)や侵入検知システム(IDS)の設定など、複数のセキュリティ機能を組み合わせることで、より強固な防御体制を構築できます。
設定ミスによるセキュリティホールを防ぐためにも、定期的な設定の見直しや監査証跡の維持管理が欠かせません。
ゼロトラストの導入と考え方
ゼロトラストは、「すべてのアクセスを信頼しないことを前提とする」セキュリティモデルであり、従来の境界型防御からの転換を図るものです。
ユーザーやデバイスの認証を強化し、アクセス制御を厳格に行うことで、内部不正や情報漏えいのリスクを低減します。
具体的には、多要素認証(MFA)の導入や、ユーザーやデバイスの状態を常に監視し、アクセス権限を動的に調整する仕組みが求められます。
また、クラウドサービスの利用が増加する中で、ゼロトラストの考え方は、社内外問わずすべてのアクセスに対してセキュリティ対策を講じる必要性を強調しています。
UTMなどの包括的セキュリティシステム活用
UTM(統合脅威管理)とは、ファイアウォール、アンチウイルス、侵入防止システム(IPS)、Webフィルタリングなど、複数のセキュリティ機能を一元的に管理できるセキュリティアプライアンスです。
中小企業にとっては、専門的な知識がなくても導入・運用が容易であり、コストパフォーマンスにも優れています。UTMを導入することで、外部からの脅威を包括的に防御し、セキュリティ対策の効率化と強化を実現できます。
また、定期的なアップデートやログの監視を行うことで、最新の脅威にも対応可能です。
従業員向けセキュリティ研修の実施
技術的な対策だけでなく、従業員のセキュリティ意識を高めることも重要です。従業員がフィッシングメールや不審なリンクに対して適切に対応できるよう、定期的なセキュリティ研修を実施することが求められます。
研修内容には、情報セキュリティの基本的な運用ルール、適切なパスワード管理、マルウェア感染の予防策、ランサムウェアの感染経路と被害事例、内部不正による情報漏えいの防止策などが含まれます。
また、eラーニングやワークショップなど、多様な形式での研修を取り入れることで、従業員の理解と実践力を高められるでしょう。
インシデント対応マニュアルの整備
セキュリティインシデントが発生した際に迅速かつ適切に対応するためには、事前に対応マニュアルを整備しておくことが不可欠です。
インシデント対応マニュアルには、インシデントの検知から初動対応、報告・公表、復旧・再発防止までの一連の手順が含まれます。
また、CSIRT(Computer Security Incident Response Team)の整備や、緊急連絡先の明確化、対応フローの定義、シナリオ演習の実施など、実務に即した準備が求められます。
参考:日本シーサート協議会
これにより、被害の拡大を防ぎ、早期の復旧と再発防止が可能です。
物理的な端末の盗難・紛失対策
ノートパソコンやスマートフォン、USBメモリなどの物理的なデバイスの盗難や紛失は、情報漏えいのリスクを高めます。これを防ぐためには、デバイスの物理的な管理を徹底し、盗難防止策を講じることが重要です。
また、万が一の際には、遠隔操作でのデータ削除やロックができる仕組みを導入することで、被害を最小限に抑えられます。
さらに、デバイスの暗号化やアクセス制御の強化、定期的なバックアップの実施など、複数の対策を組み合わせることで、セキュリティレベルを向上させることが可能です。
リモートワーク環境のセキュリティ強化
リモートワークの普及により、社外からのアクセスが当たり前となった今、企業は新たなセキュリティリスクに直面しています。
VPNやVDI(仮想デスクトップ)の導入により、通信の暗号化や業務環境の隔離が可能となり、不正アクセスや情報漏えいのリスクを軽減できます。
また、社用端末の貸与、個人端末の業務利用制限といったデバイス管理も不可欠です。さらに、カフェや自宅のWi-Fiなど、公共・私用ネットワーク利用時のセキュリティ教育も重要な要素となります。
端末のセキュリティ設定やOSの定期更新、セキュリティソフトの導入など、従業員自身の対策も促すことで、企業全体の安全性を高めることが可能です。
外部委託先との情報共有ルール策定
外部委託先や業務委託パートナーとの情報共有には、明確な管理ルールの策定が不可欠です。業務に必要な最小限の情報提供に留める原則と共に、秘密保持契約(NDA)の締結や、アクセス権の限定、監査記録の保管といった対策が求められます。
とくにクラウドやオンラインストレージを通じたやり取りが一般化している今、共有フォルダの範囲やファイルのダウンロード制限、アクセスログの取得といった設定が重要です。
また、フリーランスやSESといった外部人材にも、企業と同等のセキュリティ意識を持ってもらうため、ガイドラインや運用ルールを明文化して共有することが、安全な業務推進に直結します。
情報漏えい発生時のリスクマネジメント
情報漏えいが発生した際の影響は、企業の信用失墜、法的責任、取引停止など多岐にわたります。そのため、事前にインシデント発生時の対応体制とフローを整備しておくことが非常に重要です。
具体的には、CSIRT(セキュリティ対応チーム)の設置、緊急連絡網の構築、対外発表用テンプレートの準備などを通じて、迅速かつ的確な初動対応が可能になります。
また、影響範囲の特定や原因調査、関係者への報告といったプロセスを踏んだ後、再発防止策を明文化し社内外へ公表することも信頼回復に不可欠です。単なる一時対応に終わらせず、恒常的な改善につなげる姿勢が、組織の持続的なリスク対応力を高めます。
セキュリティ対策でよくある失敗と注意点
セキュリティ対策でよくある失敗と注意点としては、下記のようなことが挙げられます。
- 同じパスワードの使い回し
- 古い端末の放置と更新忘れ
- 「うちは大丈夫」と思い込む心理的バイアス
それぞれ詳しく解説します。
同じパスワードの使い回し
複数のWebサービスで同一のパスワードを使い回すことは、セキュリティリスクの最たる例です。
一つのサービスからパスワードが流出すると、攻撃者はその情報を使って他サービスへ不正ログインを試みる「パスワードリスト攻撃」を仕掛けてきます。
特に、仕事用とプライベートで同じID・パスワードを使用している人は要注意です。被害が個人の範囲を超えて、企業全体へ波及する恐れもあります。回避策として、各サービスでパスワードをわける、パスワードマネージャーを活用するなどが有効です。
セキュリティ意識の向上と具体的な対策の実践が求められます。
古い端末の放置と更新忘れ
サポートが終了したOSや古いソフトウェアを放置して使用し続けることは、深刻なセキュリティリスクを招く要因です。例えば、サポートが切れたWindows 7や古いスマートフォンは、既知の脆弱性が修正されないままになり、攻撃者の格好の標的となります。
特に中小企業では、古い業務用端末を「まだ使える」と放置しがちですが、重大な被害のきっかけになります。
機器の棚卸しを定期的に実施し、アップデートが滞っているデバイスを把握して対処することが重要です。更新作業をルーチン化する仕組みづくりも、安定した運用の鍵となります。
「うちは大丈夫」と思い込む心理的バイアス
セキュリティ対策を軽視する背景には、「自分は大丈夫」という思い込み(正常性バイアス)が影響しています。特に「うちは小さい会社だから狙われない」「個人情報なんて持っていない」という考えは危険です。
実際には、中小企業や個人を狙ったサイバー攻撃も年々増加しており、脆弱なシステムが標的にされる傾向があります。IPAが毎年公開している脅威レポートでも、「無差別型の攻撃」が増加している事実が明らかになっています。
出典:戦いの原理・原則と攻撃者の視点を参考に 適切なセキュリティ対策の考え方を理解する
対策を怠ったことによる被害は、信用失墜や業務停止など深刻な結果を招きかねません。常に危機意識を持つことが、最善の防御策です。
セキュリティ対策を成功させる5つのポイント
セキュリティ対策を成功させるためには、以下5つのポイントが重要です。
- 情報資産の棚卸しを定期的に行う
- 予算とリソースをしっかり確保する
- セキュリティ専門家の協力を得る
- 定期的な診断と見直し
- ツールだけに頼らない「人」の対策も忘れない
それぞれのポイントを解説します。
情報資産の棚卸しを定期的に行う
セキュリティ対策の第一歩は、自社が保有する情報資産の全体像を正確に把握することです。
例えば、顧客データ、社内資料、システムログ、業務アプリケーションなどはすべて対象になります。それらをExcelや管理ツールで一覧化し、「機密性」「重要度」「保管場所」などの指標で分類することで、守るべき範囲と優先順位が明確になります。
特にクラウドや外部委託が増える中、社内外に分散した資産の所在を把握することはリスク管理上欠かせません。最低でも年1回の棚卸しを実施し、実態に応じて更新しましょう。
また、棚卸し結果をセキュリティ方針や運用ルールと連動させ、全社的に共有することで、現場とのギャップを埋める施策にもなります。
予算とリソースをしっかり確保する
多くの企業がセキュリティ対策を後回しにする理由として、「予算が足りない」「人がいない」が挙げられます。
しかし、一度の情報漏えいで受ける損害は、対策費用を大きく上回る可能性が高いです。顧客離れや株価下落、行政処分のリスクまで含めると、対策は「コスト」ではなく明確な「投資」です。
そのため、経営層がセキュリティの重要性を理解し、継続的な予算と人材確保にコミットすることが欠かせません。
例えば、年次予算に一定割合をセキュリティに充てる、専任者や外部協力者を確保するといった体制づくりが効果的です。加えて、限られたリソースでも最大限の効果を出せるように、リスク分析や優先順位付けを行い、計画的な運用を心がけることが求められます。
セキュリティ専門家の協力を得る
セキュリティ対策は技術の進化と共に常に変化しており、すべてを社内だけで対応するのは困難です。特にゼロトラストやEDRといった高度な概念は、専門知識を持つプロフェッショナルの知見が不可欠です。
社内に専門家がいない場合でも、外部のセキュリティコンサルタントを活用することで、必要な支援をスピーディに得ることが可能です。
例えば、リスクアセスメントの実施、ポリシー策定の支援、脆弱性診断の実行など、具体的なアウトプットを委託できます。コストと時間を抑えつつ、対応の質を高める有効な手段です。
関連記事:情報セキュリティ分野で活躍する宮崎 啓さん、政府機関におけるセキュリティコンサルタントから学ぶリスク管理
定期的な診断と見直し
セキュリティは一度導入して終わりではなく、定期的なチェックと改善が不可欠です。
例えば、脆弱性診断やパッチ適用状況の確認、アクセス権の棚卸し、ログ監査などを年1回以上実施し、現場での運用とポリシーのズレを早期に発見することが求められます。
また、テレワークの拡大や新しい業務システムの導入など、環境が変化したタイミングでのスポット見直しも重要です。加えて、過去のインシデントを振り返り、再発防止策として何を強化すべきかを整理する作業も欠かせません。
PDCAサイクルに基づく対策の運用体制を整えることで、社内全体が「動的な防御力」を持つようになり、継続的な改善とともにセキュリティレベルの底上げが実現できるでしょう。
ツールだけに頼らない「人」の対策も忘れない
最新のセキュリティツールを導入しても、それを扱う人の理解と意識が不十分であれば、本来の効果は発揮されません。実際、情報漏えい事故の多くはヒューマンエラーが原因とされています。
例えば、重要なファイルを誤送信した、社外持ち出しのデバイスを紛失した、フィッシングメールに反応してしまったなどの人的ミスは、どの企業でも起こり得ます。
リスクを減らすには、継続的な教育と習慣化が必須です。eラーニングや集合研修、フィッシング訓練、啓発ポスターなど、多様なアプローチを組み合わせることで、社員のリテラシーを底上げできます。
とくに新入社員や契約社員への早期教育、部門ごとの研修内容のカスタマイズも重要です。
セキュリティ対策に関わる案件を見つけるなら「FLEXY(フレキシー)」がおすすめ
サイバーセキュリティに関する知識や経験を活かして働きたい方には、プロフェッショナル人材向けのマッチングサービス「FLEXY(フレキシー)」の活用をおすすめします。
FLEXYでは、フリーランスや副業、業務委託など柔軟な働き方を希望するIT人材を対象に、企業のセキュリティ支援などの高単価案件を豊富に取り扱っています。
専任のコーディネーターがキャリアの相談に乗り、スキルや希望に応じた案件を個別に提案。契約までのフォローもすべて無料です。
セキュリティ専門人材としての市場価値を高めたい方、企業の情報資産を守る役割を担いたい方にとって、FLEXYは最適なステップとなるでしょう。登録は最短60秒分で完了し、すぐにスカウトも受けられるので、今すぐチェックしてみてください。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む