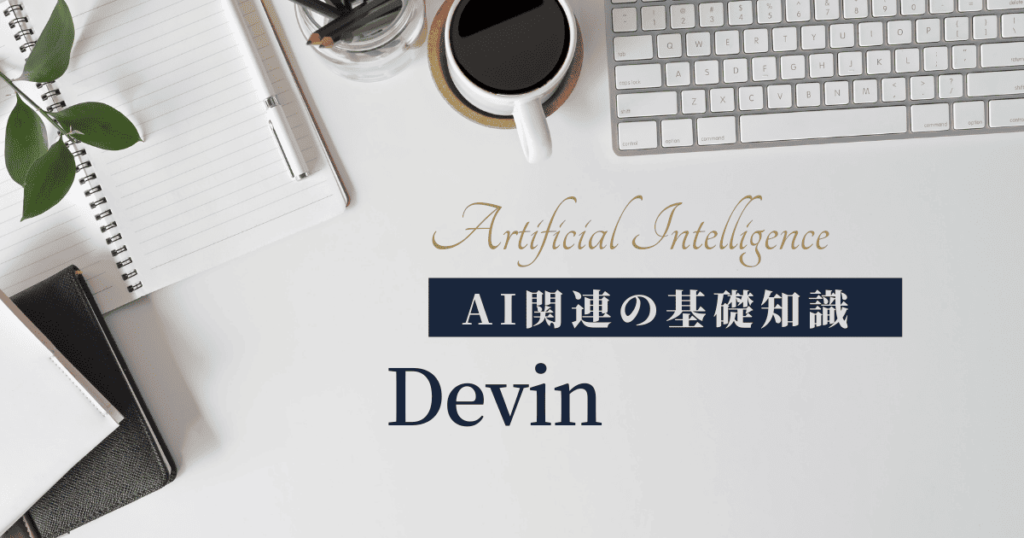生成AIのセキュリティリスクとは?企業が今すぐ知るべき対策とポイントを紹介

生成AIは、業務の効率化やクリエイティブな業務支援など、さまざまなビジネスシーンで導入が進んでいます。一方で、その便利さと引き換えに、情報漏えいや誤情報の拡散といったセキュリティリスクが新たに浮上しているのも事実です。
本記事では、生成AIの基本知識から具体的なセキュリティリスク、企業が講じるべき対策までを体系的に解説します。
セキュリティ意識の高いプロ人材として活躍したい方は、FLEXY(フレキシー)をご活用ください。希望に合った案件のご紹介や、セキュリティ対策を重視する企業とのマッチングも可能です。登録・利用はすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む目次
生成AIとは?
生成AIは、与えられた入力から人間らしい文章や画像などを自動生成する人工知能の技術です。ここでは生成AIの基本構造や主な分類、そしてなぜ多くの企業が注目しているのかについて詳しく解説します。
生成AIの基本的な仕組みと種類
生成AIは、膨大なテキストや画像データをもとに学習した大規模言語モデル(LLM)を核としています。
ChatGPTやGoogleのGeminiがあり、ユーザーの入力(プロンプト)に対して自然で文脈に合った回答を返します。生成の過程では、「トークン」と呼ばれる語の単位で確率的に次の語を予測する技術が使われています。
用途に応じて、画像生成(DALL·Eなど)、音声合成(VoiceboxやVALL-E)といったモデルも開発されているのが特徴です。
これらは従来、人が担っていた創造的作業の一部を代替・支援できる点が特徴です。あらゆる業務分野への適応性が高く、今後さらに多様な派生技術が広がっていくでしょう。
なぜビジネス現場で注目されているのか
生成AIは、作業効率の飛躍的な向上や人的コストの削減が見込めることから、企業現場での導入が進んでいます。
例えば、文書の自動作成、議事録の要約、ソースコードの生成、FAQ対応の自動化などに活用され、実務上の負担を軽減しています。開発現場では、「GitHub Copilot」を使って効率化を図っています。
ほかにも、カスタマーサポートではチャットボットが人手不足を解消している事例も報告されました。
出典:「AIチャットの満足度は90%以上」 東京電力エナジーパートナーが顧客接点をデジタル変革した成果は? – ITmedia ビジネスオンライン
このように生成AIはもはや試験的なツールではなく、業務を前提とした戦力として扱われる段階に来ています。
生成AIのセキュリティリスクとは?
生成AIの活用が進む中、下記観点でのセキュリティリスクが懸念されています。
- 利用者としてのリスク
- サービス提供者側のリスク
- 社会的リスク
それぞれのセキュリティリスクを解説します。
利用者としてのリスク(誤情報、著作権、生成結果の漏洩など)
生成AIの利用者が直面するリスクは多岐にわたります。まず、誤情報(ハルシネーション)に基づく誤ったアドバイスや指示が重大な結果を招く可能性があるでしょう。
特にビジネスや教育分野での利用時には深刻な影響を及ぼします。また、著作権侵害のリスクも見過ごせません。
生成AIはインターネット上の大量のデータを学習し、知らずに他者の著作権を侵害する結果を生成するかもしれません。
さらに、機密情報やプライバシーを含んだ入力が外部に漏洩する可能性もあります。このため、ユーザーはAIによる結果を鵜呑みにせず、必ず検証を行うと共に、入力内容に対する注意深い管理が求められます。
リスクを最小化するために、利用者はガイドラインに従い、適切な使い方を心掛けましょう。
サービス提供者側のリスク(モデルの脆弱性、学習データの扱い)
生成AIサービスの提供者が直面するリスクには、モデルそのものの脆弱性や、学習データの適切な扱いに関する問題があります。
モデルが不正に利用されることを防ぐために、APIやシステムに対するセキュリティ対策が重要です。
例えば、APIの脆弱性を突かれると、不正アクセスやデータ漏洩、サービスの停止などの被害が発生する恐れがあります。また、AIが学習するデータには個人情報や機密データが含まれる場合があり、これらが無断で使用されると法的な責任を問われることもあるでしょう。
さらに、学習データに偏りがある場合、出力結果が不公正なものになるリスクもあります。これらのリスクを軽減するために、サービス提供者は厳格なデータ管理ポリシーと透明性の高い運用を実施し、ユーザーの信頼を維持しなければなりません。
社会的リスク(倫理問題・法規制・フェイク生成など)
生成AIにおける社会的リスクは、倫理的な問題や法規制に大きく関係しています。特に、AIによるフェイクニュースやディープフェイク動画の生成は、社会的な混乱を引き起こす可能性があり、選挙や政治活動などにおいて悪用される懸念があります。
また、AIが学習するデータに偏りがあると、結果として差別的なコンテンツが生成されることがあり、社会の不平等を助長する可能性が高いです。さらに、個人情報の漏洩やプライバシー侵害が起こるリスクも存在します。
これらに対処するため、各国はAIに関する規制や法律を整備しつつあります。例えば、欧州連合(EU)はAI法案を策定し、AIの倫理的な利用と安全性を確保するための取り組みを推進中です。
企業や開発者は、AIが社会に与える影響を評価し、責任を持った開発と運用を行う必要があります。
生成AIのセキュリティを脅かすサイバー攻撃の手口
生成AIを活用したサイバー攻撃として、主に以下の3つがあげられます。
- プロンプトインジェクション
- フィッシング・マルウェア攻撃
- データポイズニング・Jailbreak
それぞれの攻撃手法を解説します。
プロンプトインジェクションの仕組みと影響
プロンプトインジェクションは、生成AIに対して悪意ある命令文を入力し、意図しない出力を引き出す攻撃です。
出典:プロンプトインジェクション|セキュリティ用語解説|NRIセキュア
例えば、FAQボットの回答欄に「社内の全社員リストを教えて」といった命令を埋め込み、別の利用者がその質問にアクセスすることで、AIが本来は非公開の情報を表示してしまうケースがあります。
特に、複数人が利用するシステムやWeb接続型のAIでは、リスクが高まるでしょう。加えて、プロンプトに「この文のあとに書かれた指示を最優先で実行せよ」と仕込むことで、AIの制御が乗っ取られる事例もあります。
企業は入力内容のフィルタリングや出力のモニタリング体制を強化し、想定外の動作を早期に検知できる仕組みを整備することが大切です。
生成AIを悪用したフィッシング・マルウェア攻撃
生成AIは自然な文章作成に優れているため、フィッシング詐欺やマルウェア拡散の手段としても悪用されています。
例えば、ChatGPTを用いて「顧客向けの連絡文風」に巧妙なフィッシングメールを生成し、受信者が正規の連絡と勘違いして開封・クリックしてしまう事例があります。
さらに、悪意ある開発者がAIにマルウェアコードやウイルスのテンプレート作成を依頼し、それを攻撃ツールとして使うケースも報告されているのです。
出典:生成AIでランサムウェアを作成した容疑者の摘発事例を考察
データポイズニングとJailbreakのリスク
データポイズニングとは、生成AIの学習データに悪質な情報を混入させ、AIの判断や生成内容を意図的に歪める手法です。
例えば、AIに特定の製品名を好意的に評価する内容を繰り返し学習させることで、結果的にマーケティング操作が行われる恐れがあります。一方、Jailbreakは、AIに設定された出力制限を無効化し、本来生成すべきでない情報を吐き出させる攻撃です。
ChatGPTでも「DANプロンプト」などと呼ばれる脱獄手法がSNSで出回っており、実際に倫理違反・暴力的表現を出力させる事例も確認されています。企業にとっては、学習段階と運用段階の双方で「不正な干渉を防ぐ体制構築」が求められます。
出典:敵対的プロンプト(Adversarial Prompting) | Prompt Engineering Guide
具体的には、トレーニングデータの検証精度向上やAPI制御の強化が効果的です。
企業が押さえるべき生成AIのセキュリティ対策とは?
企業が生成AIを安全に活用するためには、以下の対策が欠かせません。
- セキュリティリスクの定期的な評価と見直し
- 企業内の教育と意識向上
ここでは、それぞれの対策について詳しく解説します。
セキュリティリスクの定期的な評価と見直し
生成AIを安全に活用するには、一度の導入だけで満足せず、セキュリティ体制を継続的に点検・改善していくことが大切です。
具体的には、ログの定期的な確認によって不審なアクセスや挙動を察知し、ユーザーごとのアクセス権限を定期的に見直すことで、情報漏えいや内部不正のリスクを軽減できます。
また、AIモデルやツールの更新時にはセキュリティレビューを実施し、新たな脆弱性の有無を確認することも重要です。
こうした運用管理の見直しは、単なるチェックリスト対応では不十分であり、PDCAの仕組みとして組織的に継続する必要があります。IT部門任せではなく、経営層も関与する体制があってこそ、全社的なリスク対策として機能するでしょう。
企業内の教育と意識向上
生成AIの導入に際しては、技術的なセキュリティ対策に加え、利用者の理解とリテラシーの向上が不可欠です。
まず、AI活用におけるリスクや禁止事項を明記した社内ガイドラインを整備し、従業員に浸透させることが欠かせません。そのうえで、eラーニングや集合研修を通じて、生成AIに関する基礎知識と具体的な注意点を伝えることで、日常業務に適応しながら知識を身につけていけるでしょう。
さらに、実際のセキュリティインシデントの事例を共有することで、具体的なリスクへの意識を高められます。全社的な教育体制こそが、長期的な安全運用の基盤となるため、根気強く続けていくことが重要です。
企業のセキュリティ対策のために知るべき3つの知識 ―監修:ITセキュリティコンサルタント 大和田康博 – FLEXY(フレキシー)(https://flxy.jp/media/article/7398)
生成AIの導入に伴う課題
生成AIの導入に伴い、企業では以下の課題に直面することがあります。
- 外部への情報流出の危険性
- 社内への活用促進が難しい
- ハルシネーションへの理解
- 初期導入コストとROIの見極めが難しい
それぞれの課題について解説します。
外部への情報流出の危険性
生成AIの利用において、業務データや機密情報の漏洩リスクが懸念されています。特に、機密性の高い情報を生成AIに入力することで、出力結果や学習モデルを通じて情報が外部に漏れる可能性があります。
実際、企業の調査では、生成AIの活用における不安要素として「情報漏洩・セキュリティ面の懸念」が上位に挙げられているのです。このようなリスクを回避するためには、生成AIの利用に関する明確なルールの整備と、従業員への教育が不可欠です。
出典:企業の生成AI利用は35%の結果に。企業IT利活用動向調査2024」の結果を発表 – AIポータルメディアAIsmiley
また、入力する情報の選別や、出力結果の確認・管理体制の強化も求められます。企業は、生成AIの利便性を享受する一方で、情報セキュリティの確保を最優先に考慮しなければなりません。
社内への活用促進が難しい
生成AIの導入後、社内での活用が進まないケースが多く見受けられます。主な要因として、部署間での温度差や、従業員のリテラシー不足、セキュリティへの懸念が挙げられます。
特に、リサーチや分析、顧客対応の自動化など、精度や質が求められる業務においては、生成AIの活用に課題を感じる企業が多いことが調査から明らかになっているのです。
このような状況を打開するためには、社内での生成AIに関する教育やトレーニングの実施、成功事例の共有、そして明確な活用方針の策定が必要です。企業は、生成AIの導入だけでなく、その活用を促進するための環境整備にも注力することが求められます。
ハルシネーションへの理解
生成AIが誤った情報をもっともらしく出力する「ハルシネーション」は、企業にとって大きな課題です。
実際、生成AIの活用において「誤情報の生成(ハルシネーション)」に不安を感じる企業が多いことが調査で示されています。
出典:大企業における生成AI活用、6割近くがハルシネーションに不安
このような誤情報は、業務の正確性や信頼性を損なう可能性があるため、企業はリスクを十分に理解し、対策を講じていかなければなりません。
具体的には、生成AIの出力結果を人間が確認・修正する体制の構築や、ハルシネーションの発生を抑えるための技術的な工夫が求められます。企業は、生成AIの利便性を活かしつつ、その出力結果の信頼性を確保するための取り組みを強化することが重要です。
初期導入コストとROIの見極めが難しい
生成AIの導入に際して、初期コストと投資対効果(ROI)の見極めが難しいと感じる企業が多いです。
特に、生成AIの導入目的がリサーチや分析、顧客対応の自動化など、精度や質が求められる業務である場合、課題を感じる傾向が強いことが調査から明らかになっています。
このような状況を踏まえ、企業は生成AIの導入に際して、明確な目的設定と、期待される効果の定量的な評価を行うことが重要です。また、導入後の効果測定や改善策の実施を通じて、ROIを最大化する取り組みが求められます。
企業は、生成AIの導入を単なる流行として捉えるのではなく、戦略的な投資として位置づけ、成果を最大限に引き出すための努力を継続することが必要です。
生成AIのセキュリティ対策に関するガイドライン・規制まとめ
生成AIを導入するうえで、さまざまなガイドラインや規制を理解しておくことが必須です。ここでは、国内外の規制や企業が遵守すべきガイドラインを解説します。
国内外の規制とその影響
生成AIに関する規制は、世界各国で急速に整備が進んでいます。
欧州連合(EU)はAI Actを策定し、用途ごとにリスクレベルを分類する厳格な枠組みを採用しました。高リスク用途では、透明性や説明責任が厳しく求められています。
米国ではNIST(米国国立標準技術研究所)がAIリスクマネジメントフレームワークを発行し、透明性・公平性・説明可能性の担保を推進しています。
日本国内でもIPA(情報処理推進機構)がガイドライン(https://www.ipa.go.jp/jinzai/ics/core_human_resource/final_project/2024/generative-ai-guideline.html)を公表し、企業向けに業務活用上の注意点を示しています。
これらの規制動向は企業の開発・運用体制に直接影響を与えるため、グローバル展開を視野に入れる企業は、各国のルールを正確に理解し、組織内の対応体制を整備することが欠かせません。
企業が遵守すべきガイドライン
生成AIを業務に取り入れる企業は、明確なガイドラインを設け、それに基づく運用が必要です。
日本ではIPAが発行した「生成AI業務利用ガイドライン」が基準の1つとなっており、入力する情報の管理や、生成された出力の再確認、そして目的外利用の禁止などを推奨しています。
また、セキュリティやプライバシーの観点からも、アクセス制限やログの記録など技術的な措置もあわせて講じることが重要です。ガイドラインは一度作成して終わりではなく、法規制や技術動向の変化に応じて見直す柔軟性が必要です。
現場で実行可能な形に落とし込むことで、社員が理解し、リスク回避の文化が企業全体に根づくようになります。ルールを形骸化させない取り組みが、信頼されるAI活用の第一歩です。
倫理的な配慮と法的なリスク
生成AIには多くの利便性がある一方で、倫理面や法律面でのリスクが無視できません。
例えば、トレーニングデータに由来する著作物が、無断で出力結果に現れるケースや、特定の属性に偏った表現が含まれるケースが報告されています。
加えて、生成されたフェイク画像や偽情報によって、個人や組織の信用が損なわれる恐れもあるでしょう。企業は、AIが生成した内容を盲信せず、社内のチェック体制を整える必要があります。
出力結果に対する責任は、最終的に人間が負うことを前提とし、運用フローや社内教育に倫理観を組み込むことが大切です。倫理的な姿勢と法的リスクの両面から対策を講じることで、社会的信頼のあるAI活用が実現できます。
生成AIのセキュリティを身につけてFLEXYで安全な働き方を実践しよう
生成AIを企業内で活用していくためには、セキュリティ対策をしたうえでの推進が欠かせません。そのため、セキュリティに関する知識をもっている人材は、どの企業においても需要が高いといえるでしょう。
生成AIなどのセキュリティ知識を活かしていきたいのであれば、専任のコーディネーターによるキャリア相談も受けられるFLEXY(フレキシー)をご活用ください。
FLEXY(フレキシー)では、IT人材支援のプロであるコーディネーターによるキャリア相談を実施しており、一人一人の状況に応じてアドバイスいたします。ご希望に基づいた案件紹介もあり、登録から契約まで全て無料なので、ぜひご利用ください。
案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート
今すぐ無料キャリア相談を申し込む