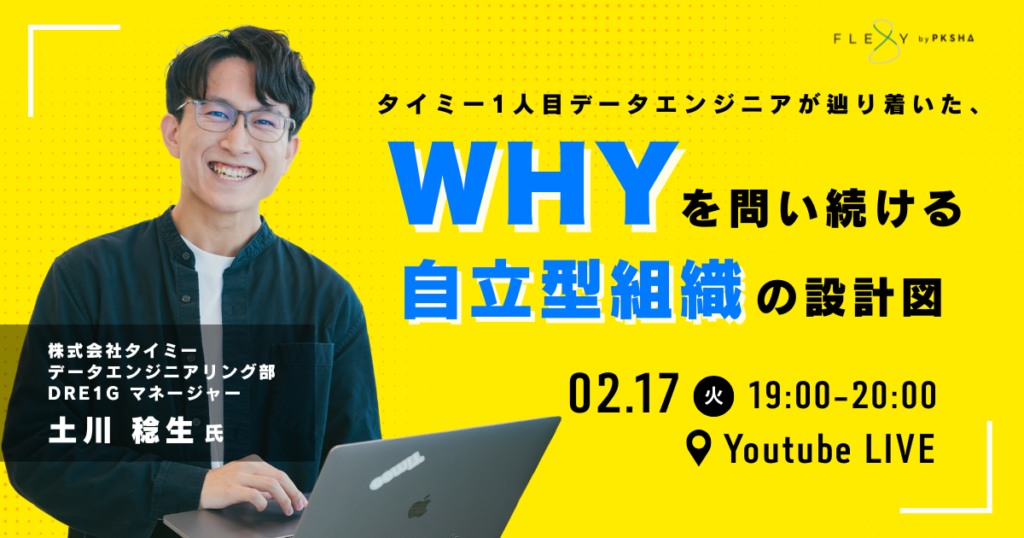AI時代、エンジニアはどう勝ち抜くか? 変化を乗りこなし価値を高めるための思考法 [FLEXY Meetup イベントレポート]

2025年4月23日に開催されたFLEXY Meetupのテーマは「AI時代にエンジニアはどう勝ち抜くか」です。 生成AIの進化は凄まじく、ソフトウェア開発の現場にも大きな変化をもたらしています。コード生成・レビュー・ドキュメンテーション作成など、AIの活用はもはや当たり前になりつつあります。
このような時代に、エンジニアは自身の価値をどのように高め、変化の波を乗りこなしていけばよいのでしょうか。 今回は、株式会社SI&Cの春日 重俊さん、株式会社ログラスの斉藤 知明さんをお招きし、AIが開発プロセスに与えるインパクトから、AIを使いこなす組織の条件、そして変化に対応できるチーム作りまで、多岐にわたるテーマでディスカッションいただきました。
目次
登壇者
春日 重俊さん|株式会社SI&C Corporate Officer
明治大学経営学部を卒業後、電通国際情報サービスに入社、大手企業の基幹会計システム導入の経験を積む。その後リクルートに入社、新規事業の業務に従事し、組織マネジメント・サービス企画・BPRなどに携わり、2016年1月にChatworkに開発本部長として入社。2020年7月に執行役員CTO兼開発本部長に就いた後、2023年3月に執行役員CTO、2023年10月に、グループ全体の技術基盤となるインフラ・データ・AIの構築を推進する技術基盤戦略室室長に就任。2024年10月に株式会社SI&CのCorporate Officerとして入社し、『Cloud Native Unit』の立ち上げを牽引。
斉藤 知明さん|株式会社ログラス執行役員 CPO
1992年大阪生まれ。東京大学工学部卒。東京大学在学時にAI研究に従事、動画像を対象としたDeepLearningの研究で国際学会ICMEに論文が採択される。在学中に英単語アプリmikanを運営する株式会社mikanを共同創業しCTOに従事。その後Fringe81株式会社(現Unipos株式会社)に入社、ピアボーナスサービスUniposを立ち上げ子会社化、代表に就任。2023年5月、株式会社ログラスに入社。「すべての挑戦が報われる社会に」を個人ミッションとする。
AI情報のキャッチアップと開発プロセスへのインパクト
日々進化するAI、トップランナーはどう情報を追っているか?
すさまじい速度で進化するAI技術。その最新情報をどのようにキャッチアップしているのでしょうか。お二人の情報収集術からセッションは始まりました。
春日氏: X(旧Twitter)で拡散されているトピックを追うのはもちろんですが、最近は「Product Hunt」で流行りのAIプロダクトをチェックしたり、AIに特化したVCと情報交換をしたりしています。また、Yコンビネーターの動向を眺めることで、新しいプロダクトの潮流を掴んでいます。ただ、情報収集だけに時間を使いすぎないよう、自分の事業にどう活かせるかという視点で取捨選択するようにしていますね。
斉藤氏: 私も基本的にはフローの情報をキャッチアップして、自分で使ってみることを徹底しています。日々の業務のほとんどをまずAI、特に「Cursor」でやってみる。最初は教え込むには時間がかかりますが、議事録作成や面接評価など、あらゆる業務に落とし込んでいます。 また、ChatGPTのタスク機能を使い、「昨日の日付で発信された面白いAIニュースを5個集めて」というプロンプトで、グローバルソースから技術だけでなく相場感も含めたデイリーのニュースを収集しています。これはXには流れてこない情報も多く、非常に役立っています。
AIは開発プロセスをどう変えるか?~設計・コーディング・レビューの未来~
AIはすでに開発の現場に大きなインパクトを与え始めています。開発プロセスは今後どのように変わっていくのでしょうか。
斉藤氏: 我々のようなプロダクト開発の現場では、設計はAIが知恵を貸してくれるようになり、コーディングはまだ人間の方がアーキテクチャに沿ったものを作れると感じています。一方で、レビューやドキュメンテーション、リンターといったルールベースの作業は自動化が進んでいます。例えば、CIでプルリクエストがマージされたら、その内容をAIに投げてドキュメンテーションを自動更新させるといったことが可能になりました。これにより、エンジニアは本質的なコード開発に集中できるようになってきています。
春日氏: 私はこの変化を、過去にフレームワークやクラウドが登場した時のような、業界をディスラプトする動きだと捉えています。AI技術の進化は、ソフトウェア開発の参入障壁を大きく下げました。これまでは一部の凄腕エンジニアしか持っていなかった知見が、AIによってブーストされたり、初学者が短期間でキャッチアップできるようになったりしています。これにより、私たちが想像もつかないようなプロダクトが生まれてくるのではないでしょうか。
斉藤氏: まさにその通りで、ライトなアプリケーションなら、CursorとAIエージェントの「Devin」を使い、VercelのようなPaaSにデプロイする、という流れで本当に数時間で作れる世界になってきました。まだヘビーなアプリケーションのアーキテクチャ設計の強みは残ると思いますが、それもいつまで続くかは分かりません。
現場で実践するAI活用術:面倒な業務を自動化し、本質的な開発に集中する
お二人は、普段の開発業務の中で具体的にどのようにAIを活用しているのでしょうか。
斉藤氏: 大事だけれど時間がかかるドキュメンテーション作成や議事録の整理は、本当に楽になりました。日常の会話を録音しておき、壁打ちした内容を後からAIにPRDとしてまとめさせ、それをもとに開発を進めることもあります。アイデアを「作って試す」までのハードルが劇的に下がりましたね。
春日氏: 私のいるSI業界、特にクライアントワークでもAIは力を発揮し始めています。例えば、ドキュメントが不十分な既存システムを引き継ぐ際、以前はコード解析に膨大な時間がかかっていましたが、Cursorなどを使うことで解析が非常に速くなりました。当初半年を予定していた作業が2ヶ月で終わった事例もあります。 また、要件定義の打ち合わせが終わった瞬間に議事録が生成されたり、テスト工程で「Codium」のようなツールを使ってテストコードを自動生成したりすることで、開発全体の生産性が向上しています。
AIを組織に実装する~勝ち残るための条件~
AIを「活かせる組織」と「活かせない組織」を分けるもの
AIの恩恵を最大限に受けるためには、組織としてどのような環境を整えるべきか。活かせる組織とそうでない組織の違いについて、議論が深まります。
斉藤氏: 多くの人がAIを活かせない最大の理由は、シンプルに「使ってはいけない」と組織から言われているからです。AI活用には、お金・権限・時間の「余白」が不可欠です。我々の組織では、使ってはいけないNGゾーン(例えば、お客様の経営データをAIに渡すことなど)だけを明確に定義し、それ以外は基本的に自由に使えるようにしています。この「やっていいこと」の範囲をどれだけ広く取れるかが、組織のスピードを左右するのではないかと思います。
春日氏: 私も余白は重要だと思います。それに加えて、メンバーが「これ便利だ!」と感じる「アハモーメント」をどう作るかが鍵になります。一度便利な体験をすると、もう後には戻れません。経営陣がAI活用の重要性にコミットし、リスクを管理しつつも、メンバーが気軽に試せる体験を設計することが大切です。例えば、「この企画書作成、AIを使えば5分で終わるよ」と実際にやってみせる。そうやって、仕事の前提に対する思い込みを少しずつ変えていくことが重要です。
変化を乗りこなすために必要なスキルとスタンス
AI時代にエンジニア個人、そして組織に求められるスキルやスタンスとは何でしょうか。
春日氏: 組織ごとによって変わりますが、普遍的に重要なことでいうと変化がある前提で揚げ足を取らずに、失敗を恐れずチャレンジしたことを称賛する風土が不可欠なのではないかと思います。今回のイベントをきっかけに社内でもイベントを行うように言われましたが、AIを使う機会を拡散していくことが組織として必要になってくるのではないでしょうか。
斉藤氏: その通りですね。加えて、最先端のものを、コストを度外視してでも使ってみるという姿勢が経営に求められます。AIの進化はムーアの法則を超える勢いです。今、高価なものでも半年後には10分の1のコストになっているかもしれません。だからこそ、常に最高のツールを試すというスタンスが、将来の競争力に繋がります。
AI活用の「知」をどう組織に流通させるか?
一部の先進的なメンバーだけでなく、組織全体でAI活用のレベルを上げるにはどうすればよいのでしょうか。
春日氏: 一歩踏み出せない人たちのために、知を流通させる仕組みが重要です。例えば、グローバルファームでは、業界ごとに有効なプロンプトをまとめて資産化し、組織内で共有しているそうです。このように、ガイドラインや成功事例を共有することで、活用の敷居を下げることができます。
斉藤氏: 弊社では、Cursorのルールを共通化しています。プロダクト開発におけるテストの書き方やリンターのルールなどを覚えさせた設定ファイルを共有することで、新しく参加したメンバーでもすぐに一定のクオリティで開発を始められるようにしています。このように、個人が持つ優れたやり方をテンプレート化して共有することが、組織全体の生産性向上に繋がります。
AI時代のチームマネジメントと変化への対応
AI活用を前提とした開発チームのリード方法
AIの活用が当たり前になったチームを率いるリーダーは、何を意識すべきでしょうか。
春日氏: 新しいことに挑戦する際には、心理的安全性が何よりも重要です。経営陣から積極的に新しいことへのチャレンジを後押ししたり、何かを試してみてたとえ失敗しても、それを咎めるのではなく「チャレンジしたことが素晴らしい」と称賛する文化を作ること。そして、そのチャレンジがどう良かったのかを具体的にフィードバックすることが、次の挑戦に繋がります。
斉藤氏: エンジニアチームに対しては、とにかく自由に試せる「余白」を用意し、良い事例が生まれたらすぐに承認することを心がけています。一方で、事業開発の観点では、まずリーダー自身が誰よりもAIを使いこなし、その体験から得た引き出しを多く持つことが重要です。自分たちが「AIで何ができて何が難しいのか」を深く理解しているからこそ、現実的で価値のある活用法をチームに提示できます。
変化に強いチームを作るためのアプローチ
最後に、AIに限らず、あらゆる変化に強く、しなやかに対応できるチーム作りの秘訣について語られました。
春日氏: お客様の変化を促す際にも、この考え方は応用できます。例えば老舗和菓子店の「とらや」が、伝統を守りつつもフラッグシップ店で革新的な試みを続けているように、変化することは悪いことではない、むしろ良い影響があるという成功事例を、お客様と一緒に体感し、伴走する姿勢が大切です。
斉藤氏: 全社を一気に変えようとすると、抵抗が大きくなります。まずは特定の小さなチームで実験的に新しいことに取り組み、そこで成功事例を作る。その成果を他のチームに展開していくアプローチが有効です。変化への影響範囲を限定することで、組織はより能動的に、そして安全に変わることができます。
Q&Aセッション
AI活用のNGゾーンの決め方、判断基準は?
Q. AI活用のNGゾーンの決め方、判断基準は?
斉藤氏: 基本的にはリスクとオポチュニティの天秤です。弊社は主にエンタープライズのお客様を相手にしているので、①お客様のデータが流出するリスク、②レピュテーションリスク、という2つの観点から、NGゾーンを判断しています。例えば、お客様の経営データは絶対にAIに渡さない、といったルールです。この基準は、最終的にはCEOや取締役が責任を持ってコミットすべきだと考えています。
春日氏: 斉藤さんのお話に加えて、セキュリティのフレームワークを参考にするという観点もあります。例えば、NIST(アメリカ国立標準技術研究所)が提唱するフレームワークのように、AIのセキュリティに関する概念やガイドラインも成熟してきています。そういったものを参考に、自社の組織レベルに応じて「どこまでやっていいか」を判断していくことが重要です。
現場は変えたいが上が変わらない場合はどうすれば?
Q. 現場は変えたいが上が変わらない場合はどうすれば?
斉藤氏: 非常に耳が痛い質問ですね…。経営には経営の事情があり、シンプルにお金がなかったり、セキュリティ要件が厳しかったりすることもあります。その上で、経営に対して働きかけるのであれば、「AIを使うことのメリット」「使わないことのリスク」を合理的に説明し、投資対効果を示すことが重要です。
お客様へのAI浸透・活用のアプローチ方法は?
Q. お客様へのAI浸透・活用のアプローチ方法は?
春日氏: まずはお客様の業務をよく観察し、「この作業、AIを使えばもっと楽になりますよ」という共感ポイントを見つけることが大切です。相手の立場に立って、自分ごととしてメリットを感じてもらえるように、様々な角度から繰り返しアプローチします。そして、少しでも一歩踏み出してくれたら、それを見逃さずに称賛することが、次の変化に繋がります。
斉藤氏: 私はひたすら「ドヤ顔」をしています(笑)。「こんなことがAIで一瞬でできるようになったんですよ!」と楽しそうに見せていると、「何それ、どうやるの?」と興味を持ってくれます。そこで、自分が使っているプロンプトやワークフローをプレゼントする。やらせるのではなく、面白いものを見せて、ショートカットキーを教えてあげるような感覚ですね。
全体のまとめ
今回のイベントでは、AIが単なる生産性向上ツールではなく、開発プロセス、組織文化、そしてエンジニア個人のスタンスそのものを変革する強力なドライバーであることが浮き彫りになりました。セッションを通じて一貫して語られたのは、変化を恐れず、むしろ楽しむ姿勢の重要性です。
「余白」を設け、「チャレンジすること」を恐れず、自ら「一次情報」を取りに行き、コストを度外視してでも最先端の技術を試す。そして、そこで得た学びや「小さな成功体験」を組織全体で共有し、称賛する文化を育むこと。これらが、AIという大きな波を乗りこなし、エンジニアとして、そして組織として勝ち抜いていくための鍵となるでしょう。AIの進化はまだ始まったばかりです。私たち一人ひとりが、この変化の時代をどう生き抜くかを問われる、刺激的なセッションとなりました。